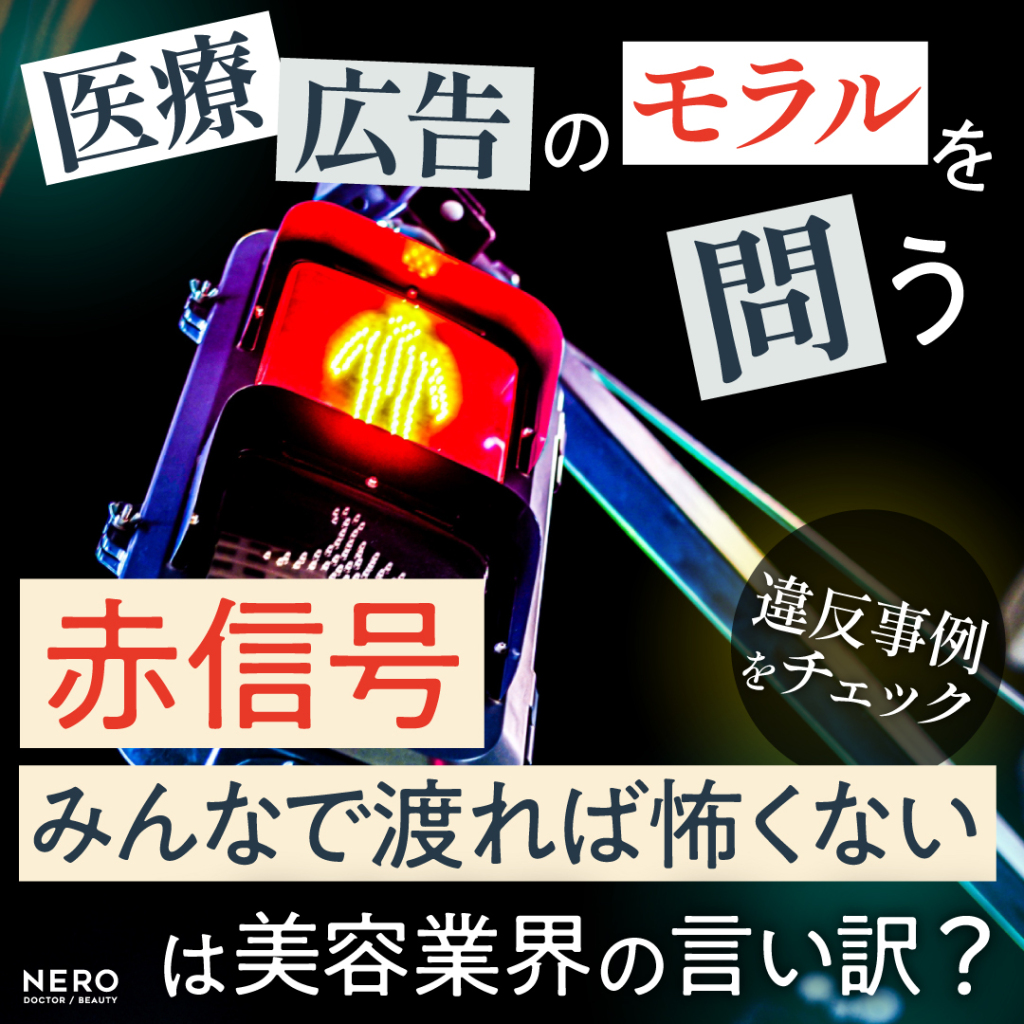
皆さんは「憧れの美しい顔になれる!」「必ず痩せられる!」と、力強くアピールする美容医療広告に見覚えはありませんか?
これらの広告には「本当かな?」「うさんくさい……」と疑いの目を向ける人もいれば、魅力的な謳い文句ばかりが目について副作用などのネガティブな面が見えなくなる人も。
しかし、美容医療は間違いなく“医療”であり、人体に何らかの影響を与えることは事実。
施術の良い面だけを伝え、誤認を招くような広告には厳しい対処が求められます。
今回は、昨今の美容医療広告の現状に触れつつ、医療広告ガイドラインの基本ルールや違反事例などを改めて確認していきましょう。
INDEX
なぜ美容医療の広告には問題表現が多い?“グレーな広告”が横行するリスク

病院やクリニックによる医療広告は、一般的な広告に適用される景品表示法に加え、医療法によって表現のルールが決められています。
医療広告の規制の対象となるのは、次の2条件にあてはまるとき。
- 患者に受診などをしてもらおうと誘引する意図がある(誘引性)
- 医師・歯科医師などの氏名/病院・クリニックの名称が特定可能である(特定性)
このルールで言えば、クリニックのホームページや医師が個人で運営するSNSも該当することになります。
ただし、医療広告の禁止事項は細部まで理解しようとするとなかなか複雑なもの。
そのため、分かりやすくまとめたものが「医療広告ガイドライン」です。
■美容医療の違反広告が多い背景とは?

厚生労働省によると、2023年度の美容医療に関する広告でガイドライン違反が確認されたのは、362サイトで2,888ヶ所とのこと。
このように、美容医療の広告の中には、ガイドラインのルールから逸脱する“違反広告”や、違反まではいかないまでもルールの隙をつくような“グレーゾーンな広告”が横行していると言われています。
その背景には、次のような事情があると考えられています。
- 医療広告ガイドラインの内容が複雑で理解できない
- 競合との競争意識からつい誇張しすぎてしまう
- 違反しても摘発されない、規制がゆるいという認識がある
医療広告ガイドラインをしっかり理解するには、広告制作知識だけでなく医療の知識もある程度必要。
そのため、一般的な広告制作会社や代理店に広告を外注すると、理解不足から違反になってしまうケースもあるようです。
また、美容クリニックの飽和状態ともいえる今、少しでも広告で目立つためについ誇張表現を入れてしまったということも少なくないかもしれません。
その裏には「他のクリニックも似たような広告を出しているし大丈夫だろう」「少しくらい違反してもすぐには摘発されないだろう」という誤った認識の広がりも影響しているようです。
■違反広告が横行することで懸念されるリスク
美容医療の違反広告は、ときに重大なトラブルに発展する可能性もゼロではありません。
例えば、次のようなリスクがあります。
- 患者が自身に適さない施術を選択してしまう
- 治療後に想定外の副作用や健康被害が出てしまう
厚生労働省の「医療広告ガイドラインの基本的な考え方」にもあるように、医療は生命や身体への影響が大きい分、不当な広告に誘われて適切でないサービスを受けたときの被害は少なくありません。
とはいえ、広告の受け手が正しく情報を取捨選択することはそう簡単ではないはず。
違反広告かどうかを判断するためには専門的知識が必要不可欠です。
また、クリニックの中には悪気なくガイドライン違反してしまい、ブランドイメージが著しく落ちてしまったというケースも。
行政処分に加え、信頼も失うという事態になれば「知らなかった」では済まされないほどの損失を被ることになります。
医療広告ガイドラインで違反になる事例とは?

ガイドライン違反の広告は、患者にとっても、クリニックにとっても大きなリスクを伴うもの。
「知らなかった」「複雑すぎて理解できない」で済ましていたら違反広告として摘発された、とならないように、基本のルールを頭に入れておきましょう。
■医療広告ガイドラインの基本ルール
まず、医療広告ガイドラインの基本ルールを解説します。
違反とみなされるのは、主に以下の6つです。
虚偽広告
大前提として、広告に嘘があってはいけません。
患者が施術内容を誤認し、適切な治療が受けられないリスクがあるため、事実と異なる記載がないかしっかりと確認する必要があります。
<違反事例>
・「〇〇医師なら絶対に成功します」
・「〇%の満足度を誇る施術です」
→“絶対”や“確実”とは言い切れないためNG。
効果に個人差があるにもかかわらず、“100%成功する”など根拠のないデータも入れてはいけません。
比較優良広告(他のクリニックとの比較)
他のクリニックと比較し、自身のクリニックが優良であると示すような広告は違反です。
また、著名人との関係性を示唆すると患者を不当に誘引することにつながりかねないため、禁止されています。
<違反事例>
・「当クリニックは日本一の症例数を誇ります。」
・「有名モデルの○○さんも推薦!」
→キャッチコピーなどでよく見かける“日本一”や“最先端医療”などの最上級を示す表現はNG。
有名人との関係をアピールに利用するのも、その有名人が利用していない他クリニックとの比較になるため禁止されています。
誇大広告
事実を不正に誇張した広告は、受け手側の誤解を招いてしまいます。
注意すべきは、広告を出している側に意図がなくても、受け手側が誤った認識をしたと感じたら誇大広告とみなされる可能性があるということ。
自院のウリを強調しすぎて誇大広告に該当してしまったケースも多くあります。
<違反事例>
・「〇〇県知事に認可されたクリニックです」
・「最先端の医療である〇〇治療を提供!」
→クリニック開設時に知事の許可を得るのはルール上、当然のこと。
それを特別なことのように記載すると違反になります。
また、“最先端”“最適”も誇大表現として注意が必要です。
費用訴求広告(割引やキャンペーンなど)
費用を強調することは“品位を損なう表現”とされ禁止されています。
違反事例の中でも多く見かけるケースです。
<違反事例>
・「今だけ◯%OFFキャンペーン中!」
・「無料で初診は受けられます」
→費用のお得感を感じさせる表現はNG。
二重価格表示(「¥100,000円→\80,000円」)もしてはいけません。
患者の主観にもとづく施術の体験談
施術内容・施術効果には個人差があるため、患者から聞いた体験談は掲載不可。
クリニックのSNSでも患者の直筆や音声による体験談を見かけることも多く、実際にトラブルに発展したケースもあります。
ただし、「待合室が清潔で快適でした」など、施術に関係ないレビューなら違反にはなりません。
<違反事例>
・患者に広告掲載のための体験談を書いてもらう
・口コミメディアから治療内容や効果について自院に有利なものを抜粋、広告へ転載する
→効果の出方に個人差がある施術について体験談を掲載することは誤認を招く恐れがあります。
施術前後(ビフォーアフター)の写真を掲載した広告
治療前後の変化を示す写真は、施術の効果を高く見せる可能性があるため禁止されています。
写真を加工するのも、当然NGです。
しかし、限定解除というルールが適用されれば、掲載が認められるケースもあります。
<違反事例>
・写真のみ、または一部の情報のみを掲載
・施術内容の説明はあるが、表示にクリックやページ遷移が必要
・複数の治療方法を一度にまとめて紹介
→限定解除に必要な要件が満たされていないためNG。
説明は載せていても、分かりにくい場合には違反になることもあります。
公序良俗に反する広告
わいせつ画像や残虐な画像、差別を助長するような表現など、公序良俗に反する場合は広告として適切ではありません。
■違反とみなされないために!広告制作の注意点
ガイドラインで禁止されている表現の中には、記載の仕方次第で違反にならないケースもあります。
以下に、その中の一部を挙げましょう。
- 症例写真を載せるときは近くに限定解除要件*を明記する
- 自由診療は「自由診療」と明記する
- 費用は「税込・税抜」などを正確に記載し、事実だけを載せる
*限定解除要件……治療の詳細、費用、副作用、リスクなどの情報。
また、医療広告には、先ほども例として挙げた「最先端」などの表現の他、「○○センター」「専門医」など誤認を誘うような要注意ワードもあります。
これらは注意していてもつい使ってしまう場合も多いでしょう。
違反に該当しそうな言葉をチェックリスト化し、漏れのないように確認することが大切です。
【編集長コメント】“だからNEROはこうしている”読者と信頼を育てる姿勢

NERO編集部は、広告を単なる売り込みではなく、読者様にとって本当に価値のある情報を届ける手段と捉えています。
私たちは、各クリニックが持つ深い価値や、まだ広く知られていない医療の真実に焦点を当て、その情報を真摯に発信しています。
美容医療に関する広告は、時に誇大表現や過度な売り込みに見られることがありますが、NEROではそれに流されず、何を伝え、どのように解決策を提供できるのかという視点に徹しています。
広告を通じて伝えるべきことは、単なる成果を誇るものではなく、読者様が抱える悩みに対する解決策の糸口を示すことだと考えています。
このような情報発信が、読者一人一人の情報リテラシーを高め、やがては社会全体に正しい知識を広めていくと信じています。
また、NEROでは取引先のクリニックとも真摯に向き合い、その価値を正しく伝えることを最優先にしています。
タイアップ記事においても、クリニックの強みや特長が、誰かの悩みを解決するきっかけになると信じているからこそ、その本質をしっかりと伝えるよう努めています。
私たちが提供するコンテンツが、業界の透明性向上やより良い情報社会の構築に繋がる一歩となることを目指し、これからも信頼性の高い情報をお届けし続けます。
そのためにも、法令遵守や医療広告ガイドラインの厳守は不可欠です。
NEROでは、法律に準じた正確な情報発信を行い、業界全体の健全な発展に貢献することを誇りに思っています。
今後も、この姿勢を貫き、読者と取引先の信頼を育みながら、美容医療業界の発展をサポートしていきます。
まとめ
美容医療のニーズが高まり、クリニック数も増え続けている今、集患のために広告に力を入れているクリニックも多いことでしょう。
広告の受け手側にとっても、魅力的な効果を謳う広告にはつい飛びつきたくなるパワーがあるかと思います。
ただ、違反広告によってトラブルに見舞われないためには、広告を作る側も見る側も冷静な視点を持つことが大切。
広告の違反事例をしっかりと頭に入れておくことが求められます。
美容医療情報メディアであるNEROも読者の誤認を生まないために、責任感を持って記事制作に当たっています。
今後、違反として摘発される医療広告が少しでも減るように、業界全体で高い意識を持っていきましょう。
この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事
| ・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。 ・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。 ・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。 |











