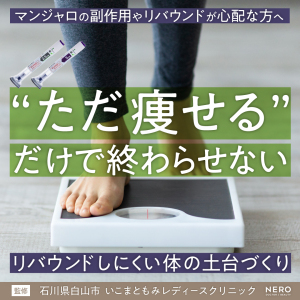老化とは、具体的にどのような意味を指す言葉かご存知でしょうか?
加齢に伴う心身の衰えなど、ネガティブなイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかし、近年の研究では「老化とは受け入れるべき自然現象ではなく改善できるもの」という認識が広がりつつあります。
そこで今回は、美容医療の観点から「老化とは何か」を深掘り。いつまでも健康で、若々しく生きるための具体的アプローチもご紹介します。
老化とは?

出典:photoAC
老化とは、一般的に成人を迎えてから起こる生理機能の衰退を意味します。
年を重ねることによる自然な現象ですが、そのスピードは人によって千差万別。
ここでは、老化の原因や加齢との違い、老化が早い人の特徴などを見ていきましょう。
■人が老化する主な原因
老化の原因は大きく2つ。
体の酸化と糖化が関係していると考えられています。
体の酸化
酸化とは、活性酸素によって体の細胞が錆び付いてしまう現象のこと。
活性酸素は、車の排気ガスやたばこ、紫外線、ストレスなど、さまざまな要因が引き金となり発生するものです。
呼吸をして酸素を取り込む過程で生まれることもあります。
活性酸素は、ウイルスや細菌から体を守る免疫機能としての側面も持ちますが、過剰に発生すると健康を害する原因に。
体の中が錆び付くことで細胞がダメージを受け、老化を促進させる可能性があると考えられています。
体の糖化
糖化もまた、老化をもたらす原因の1つ。
糖化とは、食事によって過剰に摂取した糖がタンパク質と結び付き、変性する現象を指します。
糖化の問題は、タンパク質と糖がくっつくことで化学反応を起こし、AGEsと呼ばれる終末糖化産物を作り出してしまうこと。
これにより体内が焦げ付き、筋力や骨密度の低下、心身の衰えなどを引き起こしてしまうリスクが高まります。
■加齢と老化の違い
老化と似た言葉に、『加齢』があります。
加齢とは、生物が生まれてから死ぬまでの物理的な時間の経過。
「加齢とは何歳から始まるの?」と疑問に思う方もいるようですが、単なる時間の経過であり老いや衰えを指す言葉ではありません。
生まれたときから誰にでも等しく起こる現象です。
多くの方がイメージする身体能力や生理機能の低下は、老化現象といいます。
具体的には、老眼や白髪、骨や筋力の衰え、シワやシミの出現、臓器や消化吸収能力の機能低下、運動機能の衰えなどが老化現象に伴う変化です。
加齢と老化は似て非なるもの。
年を重ねることと、体が衰えることは、決してイコールではありません。
人によって老化の進行速度が異なるからこそ、同じ年齢でも、見た目や体力に差が生じるのです。
■老化とは何歳から?
そこで「老化はいつから始まるのか」と気になる方もいるでしょう。
老化が始まる年齢に明確な答えはありませんが、一説によれば、34歳、60歳、78歳で老化の波が訪れるようです。
アメリカ・スタンフォード大学の研究チームは、血液中のタンパク質を分析した結果「老化は34歳、60歳、78歳で急速に進む」ことを発表しています。
この報告から分かったのは、老化は一定ペースではなく段階的に進むということ。
中でも、歩く速度が遅い、握力が弱い、バランス能力が低い、視力が弱いほど、老化が早い人の特徴に当てはまるとされています。
もちろん個人差はありますが、いつまでも若々しくいたいと願うのなら、年齢や個人の身体的な特徴が老化の症状をもたらす可能性があることを、理解しておいたほうが良いのかもしれません。
美容医療における年齢の捉え方

出典:photoAC
老いと正しく向き合うには、生物学的年齢についても知っておかなければなりません。
美容医療では、暦年齢ではなく生物学的年齢にアプローチするための取り組みが進められています。
■暦年齢ではなく生物学的年齢に着目
「年齢」というと、一般的には誕生日を迎えるたびに1つずつ増える数字、いわゆる「何歳」という暦年齢を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、この暦年齢は、単に時間の経過を示す数字に過ぎません。
実際の体の状態や老化の進行度合いとは、必ずしも一致しないのが現実です。
そこで、美容医療の分野では、生物学的年齢に着目。
健康状態や心身の機能に基づく年齢、つまり生物学的年齢こそが見た目年齢に深く関係していると評価し、老いを防ぐには、暦年齢と生物学的年齢の差を知ることが重要であると示しています。
■生物学的年齢を調べるには?
生物学的年齢を調べる方法に、エピジェネティッククロック検査があります。
エピジェネティッククロック検査とは、老化の進行に関与するDNAのメチル化の度合いを測定することで、体の年齢を割り出す検査のこと。
DNAの配列は生涯変わることはありませんが、DNAに結合するメチル基のパターンは時間の流れやライフスタイルとともに変わってくることが研究の結果から明らかになっています。
エピジェネティッククロック検査で分かるのは、体の老化度や老化の要因、改善プランなど。
この結果を活用して、美容医療の分野では、エイジングケア施術前後の生物学的年齢を比較し、治療の効果を検証する目的で用いられることもあります。
また、臨床現場で活用されることも。
健康診断などで疾患の指摘がない場合でも、実年齢よりも生物学的年齢が高ければ、体は老化の一途を辿っている可能性があることに気付けるかもしれません。
現状を知り、適切な対策を講じることは、健康を守ることにもつながるのです。
■生物学的年齢にアプローチするための美容医療
生物学的年齢にアプローチする美容医療には、「ホルモン補充療法(HRT)」や「オーソモレキュラー栄養療法」があります。
ホルモン補充療法(HRT)
加齢に伴い減少するホルモンを内服薬や外用薬で補充し、心身の不調をケアする治療法。
一人ひとりのホルモン状態を確認し、必要最低限を投与することでホルモンを適正バランスに近付け、若々しさや健康にアプローチします。
アメリカをはじめとした海外では、エイジングケアのスタンダードな治療として位置付けられています。
オーソモレキュラー栄養療法
血液と尿を採取し、食事療法や栄養補助食品を必要に応じて取り入れることで、足りない栄養素を補充する治療法です。
栄養バランスの良い食事は健康的な生活を送るうえでの基本となりますが、実はバランスの良い食事がすべての人に適しているわけではありません。
大切なのは、健康状態に合わせて必要な栄養素を摂取すること。
オーソモレキュラー栄養療法は、栄養素を過不足なく、適正な状態に保つことが人間に本来備わっている自然治癒力を高めるという考え方に基づいています。
日々の習慣も大切。生物学的年齢に影響を与える3つの要素

出典:photoAC
生物学的年齢を若く保つには、日々の習慣も大切です。
ここでは、生物学的年齢に影響を与える可能性がある、3つの生活習慣について詳しく説明します。
■食事
食事は、生物学的年齢に影響を与える要素の1つ。
人を構成する筋肉や骨、脂肪は食事から摂取した栄養素を原料につくられます。
つまり「何を食べるか」が老化の速度を左右すると言っても過言ではないのです。
とくに、良質な脂質、食物繊維、ポリフェノールなどは細胞の炎症や酸化ストレスを抑制する効果が期待されています。
また、体の糖化を防ぐという意味では、糖分の摂りすぎにも注意が必要です。
オーソモレキュラー栄養療法を取り入れるのも方法の1つですが、まずは日々の中でバランスの良い食事を心がけることが、内側から若々しさを保つことにつながります。
■運動
見た目の老化を防ぐには、運動も欠かせません。
適度な運動は、老化や生理機能の低下を抑制し、生物学的年齢を若返らせると考えられています。
ただし、過度な運動はかえって逆効果になることもあるため、ほどほどの強度で継続することが大切です。
目安としては、息が弾み、軽く汗をかく程度。
もちろん運動習慣がない方は、できることからで構いません。
毎日続けることが、生物学的年齢を若く保つ秘訣となります。
■睡眠
睡眠もまた、生物学的年齢へのポジティブな影響が期待されています。
慢性的な睡眠不足は、生活習慣病を引き起こすリスクを高めるほか、体内のホルモンバランスや自律神経機能にも悪影響を及ぼし、老化を加速させる要因に。
理想的な睡眠時間は人によって異なりますが、一般的には6時間半〜8時間とされており、睡眠の質も重要です。
老化が気になる場合は、就寝前の生活習慣の見直しなどにより睡眠環境を整え、質の高い睡眠をしっかりと確保することを心がけましょう。
まとめ
これまで老化とは、年齢を重ねることによる自然な変化であり、受け入れるしかないものと捉えられてきました。
しかし、老化に関する研究が進む中でその認識は、徐々に変化してきています。
実際、美容医療の分野では、ホルモン補充療法やオーソモレキュラー栄養療法といった科学的根拠に基づいた治療法が確立。
日常生活においても、バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠といった基本的な生活習慣の改善により、生物学的年齢を若く保つ方法が明らかになりつつあります。
年を重ねることは避けられませんが、老化の進行をコントロールすることは可能な時代です。
美容医療と生活習慣の改善を組み合わせることで、理想的なエイジングを実現し、充実した人生を歩んでいきましょう。
この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事
| ・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。 ・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。 ・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。 |
【治療の内容】オーソモレキュラー栄養療法
【治療期間および回数の目安】計2~5回程度(約3ヶ月~1年程度)※治療期間・回数等は解析結果や医師の判断によって異なります。
【費用相場】
・栄養解析1回 約¥20,000~¥35,000
・1か月分のサプリメント約 ¥5,000~ ¥80,000
※検査項目数や、購入するサプリメント数によって金額は変動します。
【リスク・副作用等】便秘、嘔吐、消化不良、頭痛、肝機能の低下など
【未承認機器・医薬品に関する注意事項について】
・本治療には、国内未承認医薬品または薬事承認された使用目的とは異なる治療が含まれます。
・治療に用いる医薬品および医療機器は、各クリニック医師の判断のもと導入しています。
・重大なリスクや副作用が明らかになっていない可能性があります。
・万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。