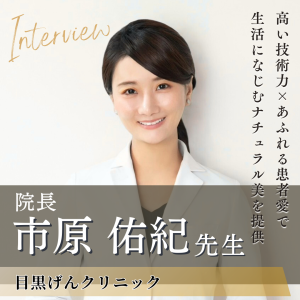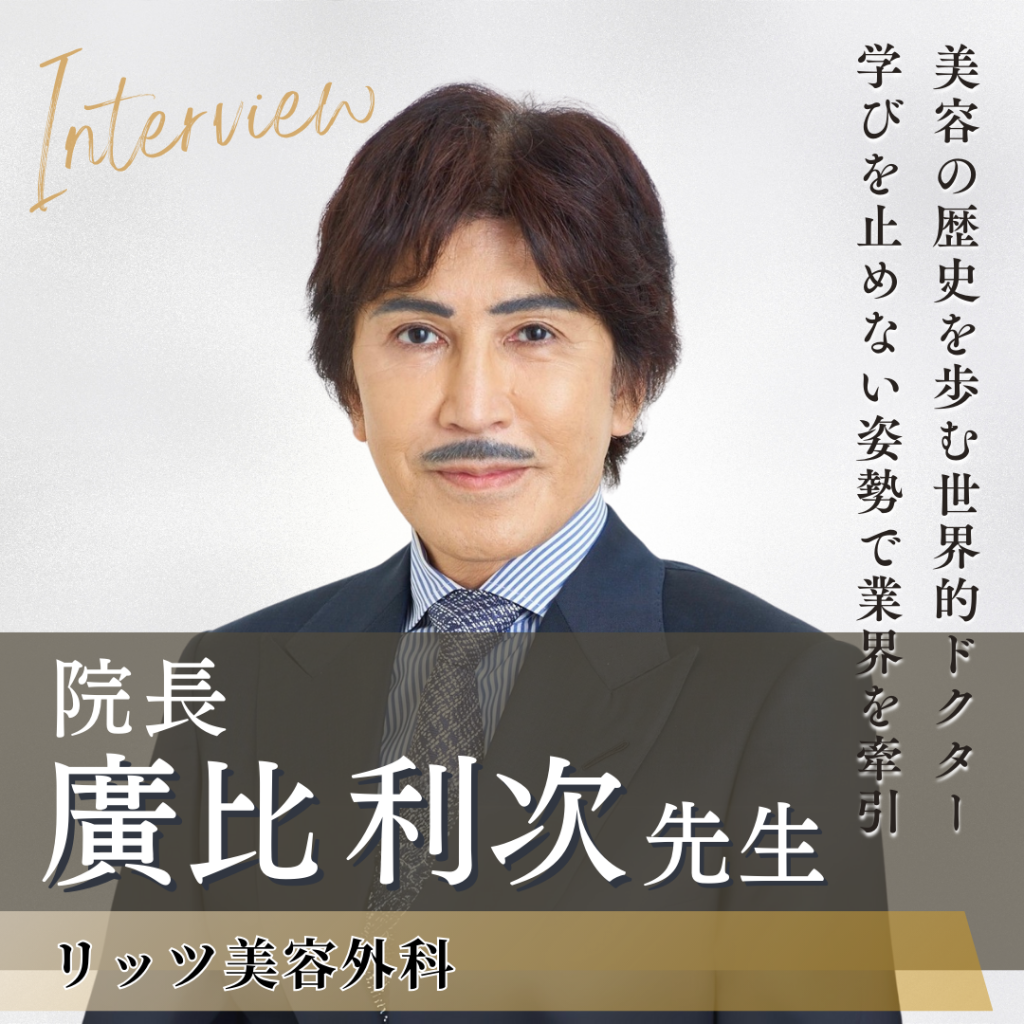
リッツ美容外科 院長 廣比 利次(ひろひ としつぐ)先生へインタビュー。美容外科医として30年ものキャリアを持つ廣比先生は、顔面骨骨切り術をはじめとする唯一無二の手術技法が高い評価を集め、世界的な医学ジャーナル誌へ数々の論文を掲載。第113回日本美容外科学会(JSAS)では会長職を務めています。今回は、2025年5月に3日間開催される「第113回日本美容外科学会」への思い、そして技術力よりも発信力が注目されがちなSNS時代において、若手医師・患者が身につけるべき美容医療の本質についてお聞きしました。
65歳を超えて現場に立ち続ける廣比先生の医師としての姿勢、解剖学を深く理解しているからこそ行える顔面骨骨切り術の魅力について知りたい方は、ぜひチェックしてください。
INDEX
ドクターズプロフィール
リッツ美容外科 院長
廣比 利次(ひろひ としつぐ)先生
1959年 東京都目黒生まれ。東京大学医学部 形成外科学教室にて波利井清紀教授に師事する。その後、複数の総合病院などで美容外科の基礎となる形成外科学を修得。2つの美容クリニックで美容外科全般を学び、形成外科医として12年目の年に「リッツ美容外科」開業。その間、論文発表を国内外で精力的に実施。日本美容外科学会総会で発表した「頬骨骨切り手術」が、最高栄誉の日本美容外科医師会会長賞を受賞。第32回日本美容外科学会総会 新手術手技コンテストで発表した「下眼瞼下制術」が会長賞を受賞。海外では、世界最高峰の形成外科医学誌『Plastic and Reconstructive Surgery』や、『Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery』『Aesthetic Plastic Surgery』等の世界的に著名な医学ジャーナルへ論文が掲載される。自身が考案した手術技法「Hirohi Methodsヒロヒメソッド)」は、顔面骨骨切り術、鼻形成術、眼瞼形成術といった幅広い領域で、海外に広く浸透している。
2025年5月、The Okura Tokyoにて第113回日本美容外科学会を史上初の3日間開催。
| (経歴) 1979年 東京大学理科II類入学 1989年 山梨医科大学(現・山梨大学医学部)卒業後、東京大学形成外科学教室へ入局 東京警察病院・都立広尾病院・静岡県立総合病院・竹田総合病院などで勤務 1994年 伊藤クリニック 入職 1997年 コムロ美容外科 入職 2000年 リッツ美容外科 開院 2025年 第113回日本美容外科学会(JSAS)会長に就任 (資格) 日本美容外科学会(JSAPS)専門医 ハワイ大学医学部客員教授 国際美容外科学会(ISAPS) FACULTY(2016KYOTO) (所属学会) 日本美容外科学会(JSAPS) 日本美容外科学会(JSAS) 日本形成外科学会 アメリカ形成外科学会 国際美容外科学会 日本口腔外科学会 日本顎変形症学会 日本頭蓋顎顔面外科学会 |
▷リッツ美容外科 公式HPはこちら
▷廣比利次先生公式インスタグラム(@ritz_hirohi)はこちら
「第113回日本美容外科学会」への思い ~テーマに込めた信念と警鐘~

―――2025年5月開催「第113回日本美容外科学会」を会長として先導されました。テーマである“TO BE THE BEST ~知の旅に終わりなし~”に込められた思いをお聞かせください。
「TO BE THE BEST」というテーマには、美容外科医として“3つの最高水準”を追求しようという思いを込めました。1つ目は、当たり前ですが技術面です。世界レベルの知識・スキルを身につける目的で本学会を開催しました。2つ目は、患者さまにとって最良の選択肢となること。技術だけでなく、患者さま一人ひとりのニーズを汲み取り、満足度を高める美容医療を追求しています。そして3つ目は、倫理的にも信頼される存在になること。美容医療は商業主義と隣り合わせになりがちですが、誠実さや透明性を重んじる姿勢が不可欠です。
サブタイトルである「知の旅に終わりなし」には、常に学び続ける姿勢の大切さを込めました。どれだけ経験を積んでも自身の無知である点に気づき、学び続ける覚悟が医師には必要です。特に若い先生方には、この学会が学びの第一幕となることを願っています。
―――学会での登壇者選定にあたり、こだわったポイントは何ですか?
私がこれまでに参加してきたアメリカの美容外科学会では、登壇するのは40年以上の経験を積んだベテラン医師が中心で、術後数十年のフォロー期間*を経た症例に基づく発表が主流でした。
対して日本では、数ヶ月という短期間のフォロー期間での発表もみられ、信頼性に欠ける場合もあります。それを踏まえて「第113回日本美容外科学会」では一般演題*をなくして、美容外科分野の登壇者は全員上席といえる先生方を私が直接スカウト。3日間で質の高い学びを届けることを重視しました。
*フォロー期間…経過観察の期間
*一般演題…若手・ベテランを問わず、広く参加者から募集した発表
―――廣比先生が“知の探求”を怠らない姿勢を保つための、支えとなったものは何でしょうか?
“知の探求”を続ける原動力は、日々患者さまと向き合う中で感じる責任の重さにあります。医師にとっては数多くの手術のひとつでも、患者さまにとっては一度きりの人生を左右する選択です。その重みを常に意識し、「この方の人生を背負っている」という覚悟で治療にあたっています。
過去には、技術不足の医師の手術によって、深刻な精神疾患を抱えたケースや自ら命を絶ってしまったケースも見てきました。そうした現実を知るからこそ、技術と知識の向上を怠らず、自分の引き出しを広げ続ける必要があるのです。

―――若い医師たちが今の時代において、学ぶべき“基礎”とは何だとお考えですか?
日本では美容外科医への転身が容易で、20代で転身する若手医師も増えています。しかし私は「急がば回れ」の姿勢、つまり医局に入って外科・形成外科を学んでから美容の分野に入ることを勧めています。アメリカでは美容外科医になるためのハードルが高く、一般外科・形成外科を計12年ほど学んでから美容に進むのが一般的。治療だけでなく精神的なケアの提供も必要とされる、高い専門性と責任を求められる分野なんです。
日本でも、基礎となる外科や形成外科の修行が不可欠です。特に自らの手術結果に責任を持ち、トラブルにも対応できる力は、しっかりした下積みがあってこそ身につきます。若いうちは給与面や当直が大変に思えるかもしれませんが、きっと美容外科医として長く成長し続けるための財産になるはずです。
美容医療業界への危機感 ~SNS時代の医師に問う信頼のあり方~
―――美容医療業界においても、“SNS上の発信力”が注目される時代になっています。この風潮について、どんな思いを抱かれていますか?
正直、非常に困った時代だなと感じています。特に若い医師の中には、SNSを駆使して多くの患者を集めている方も多く、症例写真よりも医師のルックス、親しみやすさを前面に出すほうが支持される傾向にあるようです。
しかし若い医師にとっては、SNSで集客できなければ手術経験も積めず、結果的に技術も伸ばせないという悪循環になっている現状があると聞きます。SNSが一概に悪いとは言えませんが、美容医療の本質を見失わせる側面もあり、私は“功”より“罪”の方が大きいと感じています。
―――SNS以外にどのような評価軸があればいいのでしょうか。
美容医療の評価軸として本来重視されるべきなのは技術や知識ですが、現代ではそれだけでは伝わりづらいのが現実です。そこで医療版の「ミシュランガイド」のような、客観的な評価ツールがあればと考えています。内科など一般の医療のように、名医を紹介する仕組みが美容医療には乏しいため、論文実績や学会での活動、顧客満足度などを総合的に評価できる仕組みが必要だと感じています。
―――先生は「美容外科医にも形成外科的な構造への深い理解が重要」と広く伝えていらっしゃいますね。
美容外科医にとって、構造への理解は基本中の基本だと考えています。特に切開リフトのような手術は糸リフトのような手技とは大きく異なり、詳細な解剖の理解が必要です。しかし日本では、アメリカのようにご献体を用いて解剖を学ぶ機会が限られており、それが美容外科医の成長進歩に少なからず影響を与えています。そこで今回の学会では、トップクラスの美容外科医たちによる手術映像を通じて、手技を実践的に学べる機会を提供しています。
―――美容外科医の倫理観において、今どのような課題があると思われますか?
若い医師が美容医療の世界に入ると、クリニックによっては「SNS発信を頑張って売り上げをアップしなさい」といった指導を受けるケースがあり、医師としての誠実さを育む機会が失われがちです。もともと病気の治療に携わってきた形成外科出身の医師とは、倫理観の形成過程が大きく異なります。こうした背景を踏まえ、今回の学会では医師が倫理観について深く考える機会も提供しています。
世界から見た日本の美容医療とは ~国際的に認められた“Hirohi Methods”~

―――日本の美容医療が世界に打って出るには、どのような課題があると思われますか?
日本の美容医療業界が抱える大きな課題は、国際的な発信力の弱さですね。特に英語力の不足によって、海外への学会参加や英語での論文発表がサイエンスの分野全体としても少ない状況です。一方、韓国や中国の医師は積極的に英語で論文を発表し、世界的な影響力を高めています。
ただ海外の医師たちが日本に来ると、皆さん「日本の美容外科医は手術が上手い」とおっしゃいます。英語力の問題や論文執筆の意識が乏しいことで、その技術が世界に伝わっていないことは非常にもったいなく感じますね。今後、若い医師たちがSNS以上に、論文執筆や国際発信に力を入れることを期待してやみません。
―――廣比先生の顔面骨切り術「Hirohi Methods(ヒロヒメソッド)」は、唯一無二の技術として国際的に評価されています。難易度の高い分野である“骨切り”をライフワークにされたきっかけは?
形成外科医時代、交通事故などによる複雑な顔面骨折の治療を数多く経験したため、骨という深い層へのアプローチに抵抗がなかったことが大きいですね。また、美容外科医として育てていただいた「伊藤クリニック」でも骨切りを中心に行っていたため、さらに専門性が深まりました。
美しさを追求するためには、目や鼻といったパーツだけでなく、骨格そのものを整える必要があるケースもみられます。そのような患者さまに、満足いただける結果をもたらす“顔面骨骨切り術”に意義と魅力を見出しました。
「リッツ美容外科」では、「小顔になりたい」「エラ張りが気になる」「顔の非対称を改善したい」といったお悩みがある患者さまに対し、形成外科専門医の高い技術力と美的センスを活かした顔面輪郭形成術を提供しています。ぜひご相談いただきたいですね。
―――2025年以降、美容医療はどのような進化を遂げると予想されますか?
美容外科の領域で今年や来年、急に新技術が生まれる可能性は低いと感じています。というのも、美容外科では基礎研究と臨床現場の連携がまだ不十分で、現在の手術も従来の技術に頼っている部分が大きいためです。
ただ、今後最も注目しているのは再生医療、特にiPS細胞(人工多能性幹細胞)の美容医療への応用です。例えば将来的に、切られすぎた骨の再生を自家軟骨で補うことが可能になるかもしれません。
さらに、AIを使った診断技術や手術プランニングの進化にも期待しています。こうした技術が、美容医療の進化を大きく後押ししていくと考えています。
読者へのメッセージ ~医療としての美容を守り抜き、患者を幸せに~

―――美容医療に興味を持つ読者に、アドバイスなどはありますか?
美容医療を検討する際は、SNSのイメージだけで判断せず、医療としての信頼性を重視していただきたいですね。誰もが「名医」と名乗れてしまう現状、正しい情報を見極めるのは難しいものです。私たち医師側も誠実な情報発信を続けて、患者さまが幸せになれる美容医療にたどり着ける環境を整えていきたいと思います。
―――最後に若手医師へのメッセージをお願いします。
初任給などの条件を理由に美容の医師を目指す方も増えていますが、一般の形成外科や外科に入って得られる経験も大切です。トラブルへの対応力や、やけど治療における知識など、医師としての常識が身につくのはそういった現場です。
美容医療の世界で長く活躍したいなら、まずは基礎を固めてからでも全然遅くありません。総合病院などで5年間しっかり過ごすと、その後はむしろ一気に加速して成長していけると思います。焦らず地道に学びながら、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。