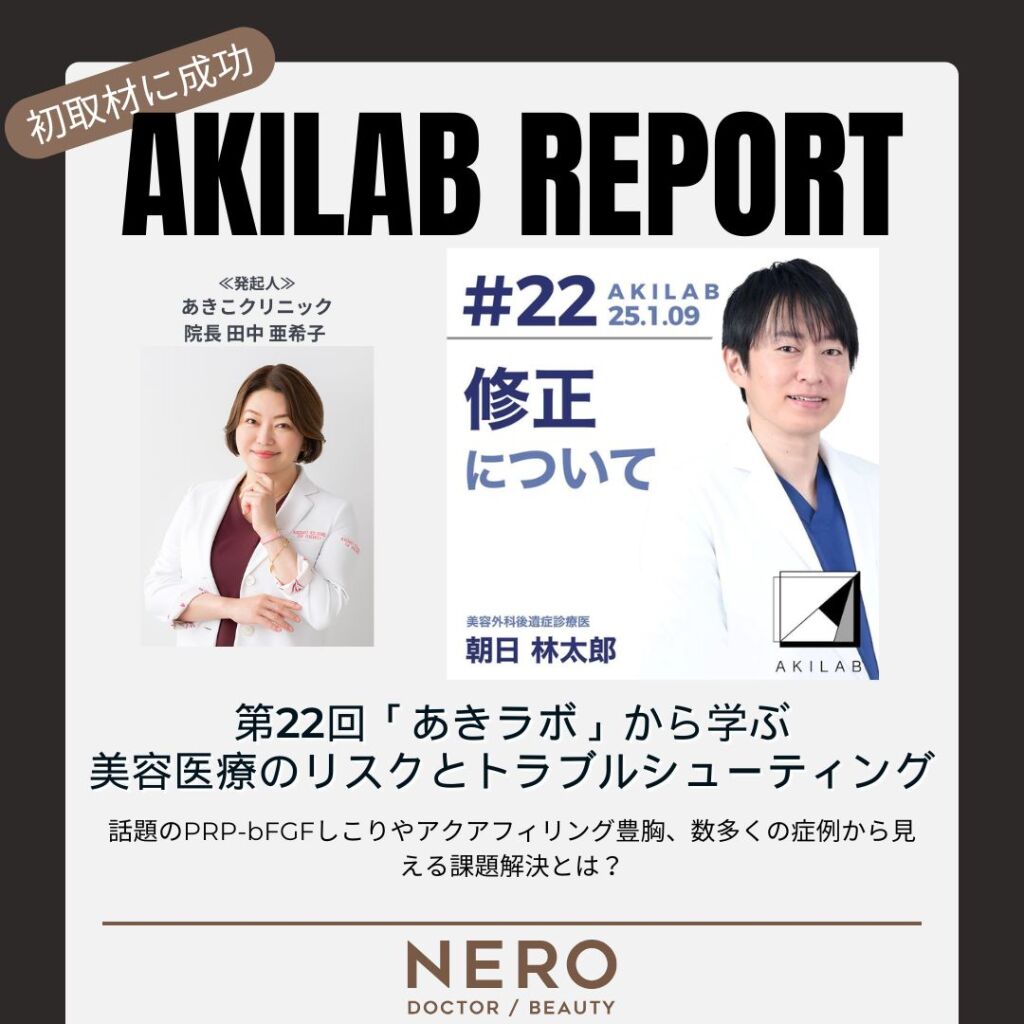
INDEX
- 美容医療を良くする医師たちがフラットに学び合う医師の集まり「あきラボ」って何?何が目的で、どんな場なの?
- 『あきラボ』 発起人 田中 亜希子 先生
- 第22回 朝日先生 『修正について』
- 編集長コラム—「美容医療の未来を共に創る場」
INDEX
美容医療を良くする医師たちがフラットに学び合う医師の集まり「あきラボ」って何?何が目的で、どんな場なの?
~垣根を超えた学びと成長の場を目指して~
「あきラボ」は、田中亜希子先生(あきこクリニック院長)が2022年11月にスタートさせた美容医療のスタディーグループで、現在までに22回を迎えています。この会は、美容医療における知識の共有や臨床経験の深化を目指し、講義だけでなく活発なディスカッションを通じて、医師たちがフラットに学び合う場を提供しています。
あきラボ誕生の背景
開業医としての実体験から「孤独感」や「相談できる場の少なさ」を感じていた田中先生は、「日々の疑問を気軽に相談できる場を作りたい」との思いから、あきラボを立ち上げました。特定の年齢や経験に縛られることなく、「学びたい」「成長したい」という意欲があれば誰でも参加できるフラットな雰囲気が特徴です。クリニックや分野の垣根を超えたこの勉強会は、若手からベテランまで、多様な医師が集まり、それぞれの視点から意見を交わす貴重な場となっています。
「あきラボ」がもたらす価値
現代の美容医療は目まぐるしく進化を遂げる一方で、誤った情報や不適切な施術がリスクとなることも少なくありません。そんな中、あきラボは「正しい知識を共有し、現場の課題を解決する」ことを目的に掲げています。
新規参入を考える医師には正しいやり方を学ぶ機会を提供し、ベテラン医師には自身の悩みを共有し合える安心感のある場を提供します。「ただ講義を聞くだけでなく、参加者全員で話し合う」このスタイルは、他の勉強会とは一線を画しています。
平日の夜を中心に開催しているあきラボですが、田中先生は「今後は合宿形式での開催も企画したい」と一泊二日程度のスケジュールで、参加者同士がフランクに意見を交わしながら、医療の知識を深めるだけでなく、楽しい思い出も作れるような場を目指しています。
また、遠方の医師にも参加しやすい時間帯や形式での開催も積極的に取り入れ、美容医療の未来を支える学びの場をさらに広げていく計画だと語っている。
※商標申請中の「あきラボ」
「あきラボ」は現在、「AKILAB アキラボ」の名称で商標申請中です(第41類:教育、娯楽、スポーツ、文化/第44類:医療、美容、農林)。田中先生のリーダーシップのもと、この勉強会は医療現場で直面する課題に向き合いながら、美容医療業界の進化と発展に寄与する存在として、今後もその価値を高めていくことに期待が止まらないと筆者は感じます。
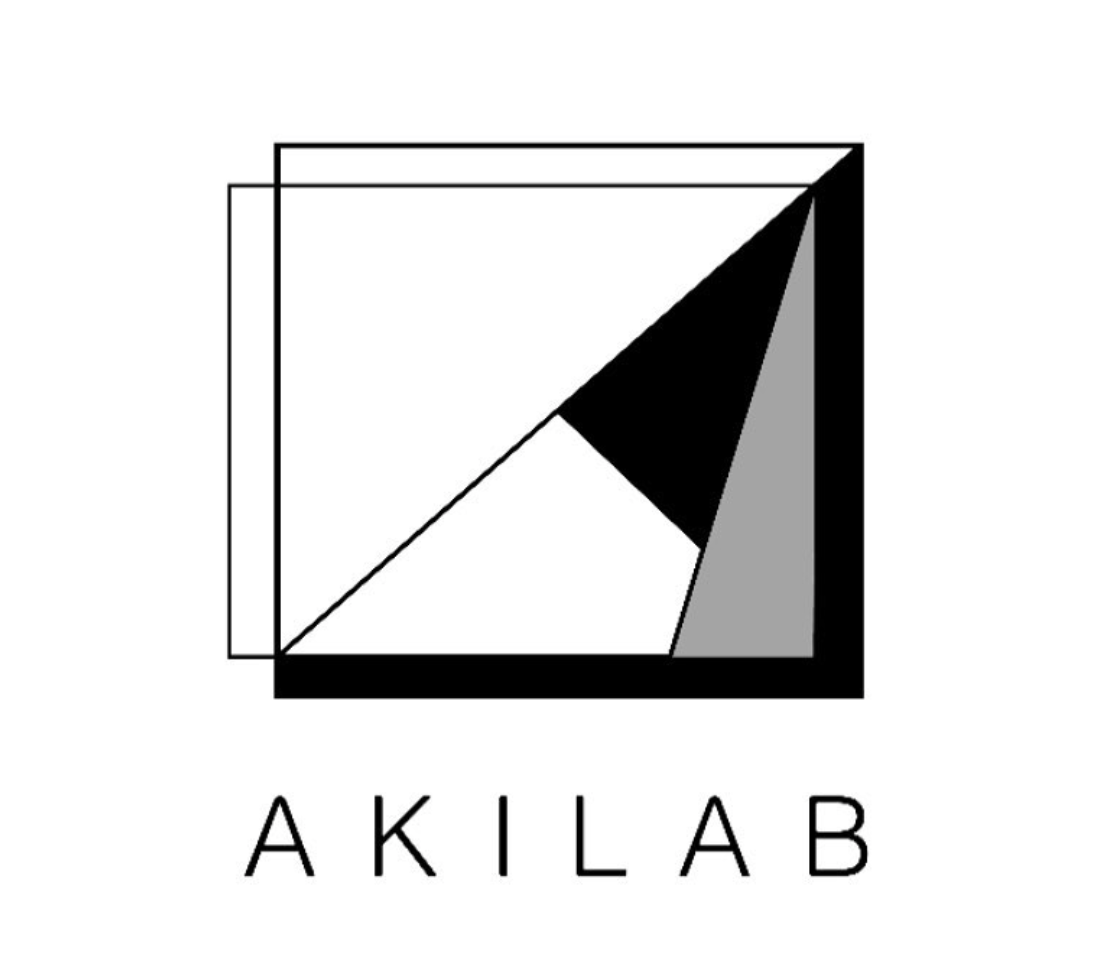
※このイベントはセミクローズドにて写真撮影禁止のものも多かったのですが、講義内容を聴取しながら記載しております。
『あきラボ』 発起人 田中 亜希子 先生
あきラボの発起人は、美容医療分野で活躍する田中亜希子先生。
ドクタープロフィール

出典:あきこクリニックHP
医療法人社団 英僚会 理事長
あきこクリニック院長
田中 亜希子 先生
●東京大学医学部卒業後、大手美容外科副院長などを経て2009年にあきこクリニックを開院。2013年に医療法人社団英僚会を設立し、院長と兼任で理事長に就任。
第22回 朝日先生 『修正について』
第22回目を迎える今回のあきラボは、特に注目の「修正について」の内容です。また、このイベントはセミクローズド形式での開催のため、登壇内容の詳細は公開されませんが、NERO編集部が現場に潜入し、臨場感たっぷりにその様子をレポートいたします!
今回の登壇者は朝日 林太郎 先生!
今回のメインスピーカーは、美容外科の分野で国内トップクラスの実績を持つ 朝日 林太郎 先生。特に、FGF後遺症治療の第一人者として知られ、多くの医師や患者から厚い信頼を寄せられています。修正治療において圧倒的な症例数を誇る朝日先生の知見は、美容医療の分野において極めて貴重です。
朝日先生が今回お話しされるテーマは『修正について』。美容医療の現場では、他院での治療後に発生した問題を修正するケースが少なくありません。その中で、正確な診断と適切な治療法を提案する能力が求められます。今回の講演では、朝日先生が実際の症例を交えながら、その具体的な手法や課題を共有する場となりました!!

出典:あきラボ Instagram
美容外科後遺症診療医
朝日 林太郎(あさひ りんたろう)先生
美容医療が広がりを見せる中、その影でトラブルや後遺症に悩む患者の存在が浮き彫りになっています。1月9日、都内で開催された勉強会にて、国内トップの症例数を誇る朝日りんたろう医師が講師として登壇。医療従事者を対象に、美容後遺症の現状や解決策について語りました。会場には医師や看護師、そして美容医療関係者が多数集まり、熱気に包まれた議論が繰り広げられました。
美容後遺症外来とは?
美容医療市場は近年、技術革新とともに急速に成長を遂げています。しかしその一方で、患者教育や医療者間の連携が不十分であることが大きな課題として浮上しています。
朝日医師は「施術を受ける患者の多くがリスクや術後のメンテナンスに対する知識を十分に持っていません。提供する側もデメリットを伝えていないなど、目指したい治療が適切に行われず、後遺症やトラブルが発生するケースが増えています」と指摘しました。
また、こうした状況を放置すれば患者の信頼を損ねるだけでなく、美容医療全体の信頼性にも影響を与える可能性があると強調。「医療従事者間での情報共有や、患者が十分な知識を持つための教育プログラムの整備が急務です」と提言し、具体的な統計データを基に現状を共有しました。
実例から見る治療の難しさと重要性
講演では、具体的な症例が紹介され、美容医療後遺症治療の複雑さや実態に会場の空気は一層熱気に包まれ、真剣な眼差しで食い入るように聞いていた参加者が印象的でした。
✅ PRP-bFGF治療の後遺症
このセクションでは、特に会場の注目を集めたPRP-bFGF注射後の症例が紹介されました。朝日医師は、しこりが大きく形成されるケースをいかにして改善したかを具体的な治療プロセスとともに解説。術前・術後の経過写真や細かいプロセスがスクリーンに映し出されると、医師たちは真剣な表情でスライドを見つめ、質問の手が次々と挙がりました。
bFGF(成長因子)の注入治療後に発生するしこりや腫れとして知られており、
特に異常増殖を伴うケースでは、患者が元々目指していた効果を達成することが非常に難しい部分などの議論も印象的でした。
ある参加医師からは、しこりの治療方法に関する具体的な質問が寄せられ、朝日医師はその場で詳細に解説しました。また、他の医師からの専門的な意見が交わされ、議論が白熱し、会場全体に熱気が広がる瞬間となりました。
※PRP(Platelet Rich Plasma)とbFGF(遺伝子組換えヒト線維芽細胞成長因子)は、肌のシワやたるみ、薄毛などの改善を目的とした再生医療の治療法PRP(Platelet Rich Plasma)とbFGF(遺伝子組換えヒト線維芽細胞成長因子)は、肌のシワやたるみ、薄毛などの改善を目的とした再生医療の治療法
 ※イメージ図
※イメージ図
✅ アクアフィリングのトラブル
特殊な注入剤によるトラブルの症例で、完全除去が困難なケースが多く、患者と医療者双方に高いストレスをもたらす状況が紹介。
例えば、アクアフィリング注入後の異物反応や肉芽形成の症例が挙げられ、実際の患者の治療経過をもとにした具体的なプロセスが解説されました。会場では「これほど詳細に実例を示しながら解説してもらえるのは貴重」という感想が多く聞かれました。
その他、上記以外にも様々な症例が紹介され、美容医療のリスクやその対応の重要性について深く議論されました。これらの症例は、医療従事者が現場で直面する課題をよりリアルに浮き彫りにし、今後の医療体制の改善に向けたヒントを与えるものでした。
未来に向けた医療体制の構築
症例ケースや議論を交えた後、朝日医師は、「リスク管理と患者の健康リテラシー向上が、美容医療の持続的な発展の鍵です」と述べ、次の提案も非常に感慨深く印象的な内容でした!!
| NERO編集部解説 ✅POINT✅
 ※イメージ図 ※イメージ図「患者が安心して治療を受けられる社会を目指したい」と語る朝日医師の言葉には、医療の未来を見据えた力強い信念が込められていました。 |
セッション終わりに記念撮影!
心理的安全性が高く、研鑽し合う熱気から溢れる笑顔が印象的でした。

出典:あきラボ Instagram
編集長コラム—「美容医療の未来を共に創る場」
今回の勉強会は、美容医療の課題を明確化するとともに、医療従事者たちの垣根を越えたリアルな議論が展開される貴重な機会となりました。朝日医師の具体的な症例紹介と、それに基づく治療法の解説は、参加者にとって即実践に活かせる内容であり、多くの学びを提供している「あきラボ」は世代関係なく美容医療の発展の場となると感じました!!
特に、若手医師が経験豊富な医師たちと意見を交わし、直接知識や技術を学ぶこのような場は、業界全体のレベルアップに大きく寄与します。医療従事者が一丸となって学び合う文化が根付くことで、日本の美容医療がさらに信頼される存在となり、世界に誇れるブランドへと進化することを期待しています。
「良き美容医療の団結の輪」の精神で築かれる連携と学びの場が、美容医療の未来にとって重要な基盤となるでしょう。患者が安心して治療を受けられる社会を目指し、私たちは引き続きこの取り組みをNEROは応援していきます。







