
今回のNews Topicsでは、フェムテック医療の新しい学術的地盤となる「フェムメディカル協会」発足と第1回オンライン学術集会の開催された。
膣ヒアルの適応、女性性機能障害(FSD)診療、ホルモン・ペプチド療法まで、3名の専門医が登壇。「美容だけ」でも「婦人科だけ」でもなく、第3の“女性医療”の胎動が始まったといえる。
フェムテック界隈では、誤情報が横行する今こそ、専門医の集合知が問われている。
また、医療従事者だけでなく、社会全体に問われるこのテーマの今後とは?
 出典:運営してる自費研株式会社様:フェムメディカル協会
出典:運営してる自費研株式会社様:フェムメディカル協会
📌 3つのポイント
✅日本初「フェムテック医療」専門学会、フェムメディカル協会が設立
✅ 第1回オンライン学術集会が開催され、膣ヒアル・FSD・ペプチド療法が議論
✅ 年2回の学術集会や医療連携・啓発活動を通じ、“実践型フェムケア医療”を推進
INDEX
フェムゾーン医療の新章開幕──なぜ今、“専門医によるフェムテック学会”なのか
■ オープニング:協会設立と学術集会の開催背景
2024年6月24日、日本初のフェムテック医療専門学会「フェムメディカル協会」が第1回オンライン学術集会を開催。設立の中心には、産婦人科・女性泌尿器科・美容内科など、実臨床に根差したスペシャリストが集結した。
代表発起人でもある宮本亜希子医師の呼びかけで始まったこの学会は、誤情報の氾濫と知識格差が進むフェムテック領域に「医療の視点」を取り戻すべく、明確な診療基準と啓発を目指す。
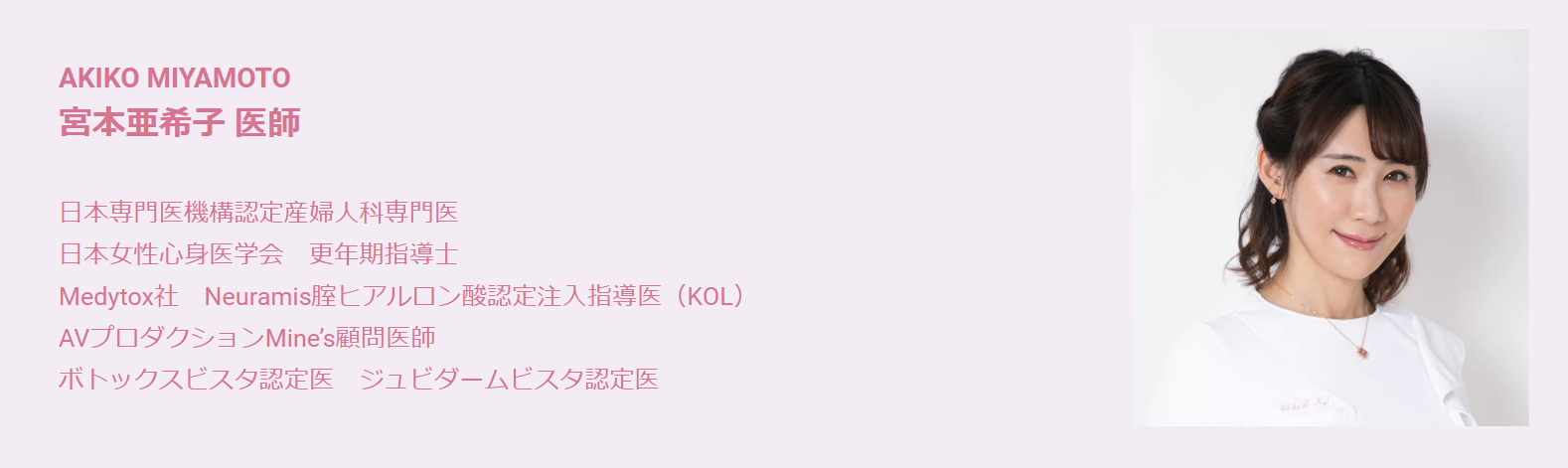 出典:運営してる自費研株式会社様:フェムメディカル協会
出典:運営してる自費研株式会社様:フェムメディカル協会
■ 学会の主旨と開催目的
フェムテックは美容外科や企業主導で市場拡大を遂げたが、医師による知識共有や適正使用の議論は後手に回っていた。今回の学術集会では、「膣ヒアル」「性機能外来」「ペプチド療法」の3テーマで講演を実施。
宮本先生、中村先生、前田先生の登壇医師3名による「多職種連携によるFSD対談」も行われ、診療科横断の連携構築に光が当てられた。
 出典:運営してる自費研株式会社様:フェムメディカル協会
出典:運営してる自費研株式会社様:フェムメディカル協会
■ 協会の展望とフェムゾーン医療の未来
今後は年2回の学術集会を軸に、膣ヒアル注入技術講習、緊急時の医療連携体制、専門医による一般向け啓発イベントなども展開予定。顧問として、関口由紀医師(女性医療クリニックLUNA理事長)、丹羽咲江医師(咲江レディースクリニック院長)も参画し、臨床と啓発の両面からフェムケア医療の再定義を進める構えだ。
 出典:運営してる自費研株式会社様:フェムメディカル協会
出典:運営してる自費研株式会社様:フェムメディカル協会
~膣ヒアルは魔法じゃない、本当の適応と治療法~宮本 亜希子 医師
▍“見えない不調”が“見えないまま”にされている現実
「膣ヒアル=魔法の若返り」という幻想が広がる一方、宮本医師は現場で直面する課題として、性交痛・乾燥・膣の菲薄化といった明確な疾患症状に悩む患者が見過ごされている現状を訴えた。
患者の声には、「性行為ができない」「トイレの後に違和感がある」など、
“外からは見えない苦しみ”が潜んでいる。それにも関わらず、美容目的の“膣の若返り”に注目が偏り、本来の医療的価値が置き去りにされつつあると問題提起した。
▍治療適応を見極める“科学”と“倫理”の視点
ヒアルロン酸注入は保水性・修復促進作用を有し、一定の治療効果がある。
だが、「すべての不調に効くわけではない」という冷静な視点が必要だ。講演では、注入層の選定、量、深度、適応の分類など詳細な治療アルゴリズムが示された。
また、単に効果を謳うのではなく、「医師がどこに、なぜ注入するのか」を
患者に正しく説明し、合併症リスクにも対応できる技術が求められると強調。
そのうえで、“美容”と“医療”の線引きは、医師自身の倫理観に委ねられていると語った。
▍フェムテックブームの裏で求められる“再教育”
現在、「膣ヒアル」は婦人科であっても手薄な領域である。
にもかかわらず、美容医療のトレンドとして急速に普及している背景には、正しい教育と臨床スキルの乖離がある。
宮本医師は、「専門医であっても、膣注入はあらためて学ぶ必要がある」とし、正しい診断、医療としての位置付け、リスク管理を含めた再教育の重要性を説いた。
今後、学会による標準化・技術講習・プロトコルの整備が求められる中、
「“なんとなくの経験値”ではなく、再現性ある医療行為として確立していくべきだ」と
力強いメッセージで締めくくった。
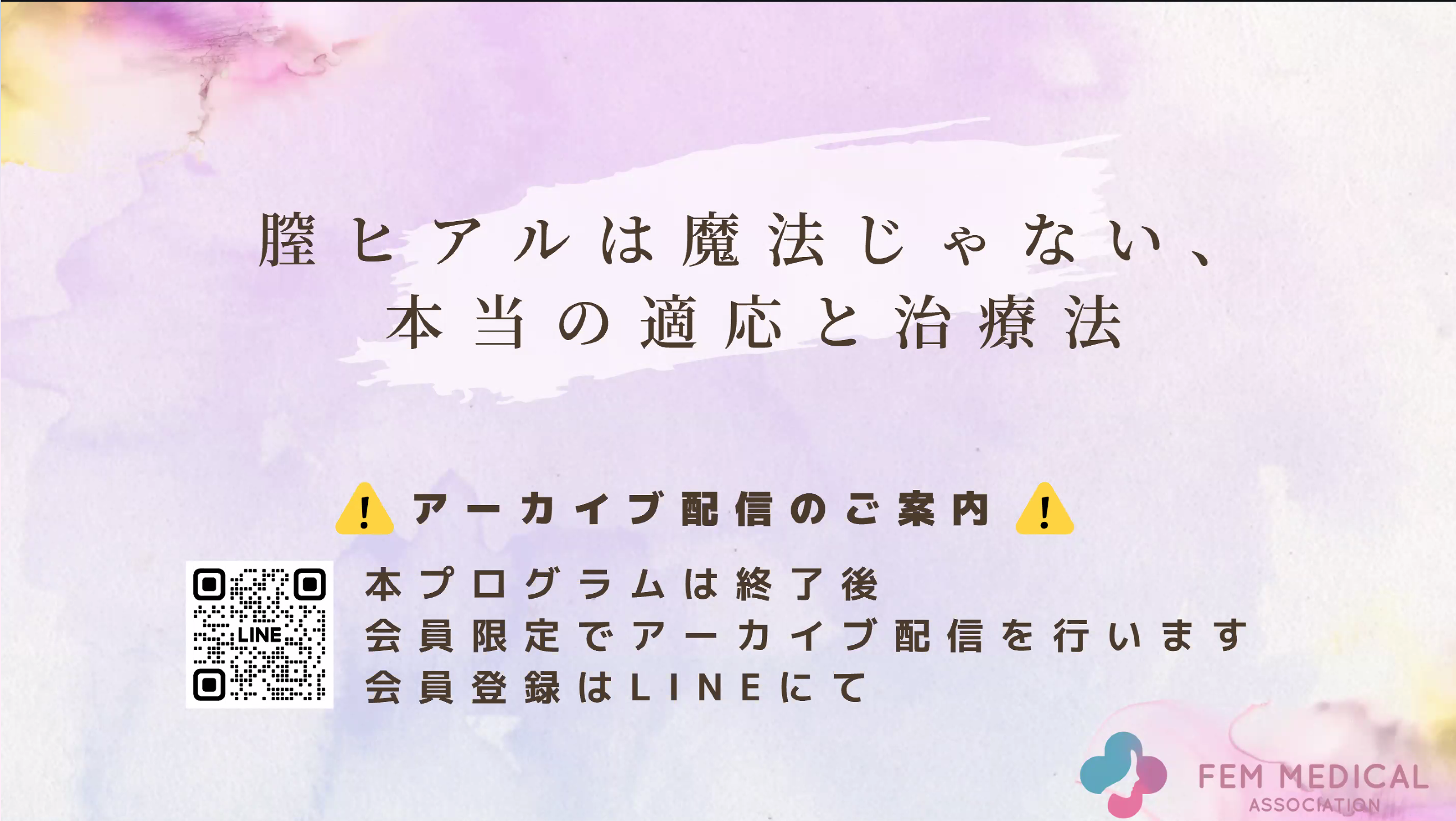
~女性性機能外来の実態~中村 綾子 医師
▍若年層にも広がる“性交痛”というサイレントペイン
開設から1年、女性性機能専門外来には154名が来院。
そのうち、20~30代の女性が約9割を占めていた。
彼女たちの悩みは、性交痛、挿入困難、快感の欠如——
「産婦人科では話せなかった」「誰に相談していいかわからなかった」という声が多い。
未妊・未産の若年女性たちに共通していたのは、医療にたどり着くまでの孤独なプロセス。
中村医師は、この現実に警鐘を鳴らすとともに、「性機能障害は病気ではなく、“人生に関わる課題”」と明言。話せる環境、受け止める姿勢が、何よりも“最初の治療”であると強調した。
▍診断だけでは解決しない、多層的な支援の必要性
性機能障害は大きく「性的興奮障害」「オーガズム障害」「性行疼痛症」の3つに分類されるが、
中村医師は「実際には分類不能なグラデーションケースが多い」と現場の複雑さを説明。
医療面では骨盤リハビリや心理的サポート、パートナー教育も必要になる。
さらに、「初診では本音を話せなくても、3回目の診療で涙ながらに語られることも多い」とし、
時間・雰囲気・信頼構築がセットで診療の本質になると説いた。
▍本来の“性の健康”に国家的支援を
治療現場では、20代は心理的ブロックが多く、40代はホルモンバランスや加齢変化への対策が主軸となる。しかし、日本では「性の健康」への制度的支援や医師教育がまだ乏しい。
中村医師は「産婦人科、泌尿器科、精神科の間に漂う“無関心の谷”に
本来の性機能外来が落ち込んでいる」と問題提起。
全国で診られる医師を増やし、チーム医療と社会制度の構築を進めなければ、
この問題は可視化されないまま放置され続けると締めくくった。
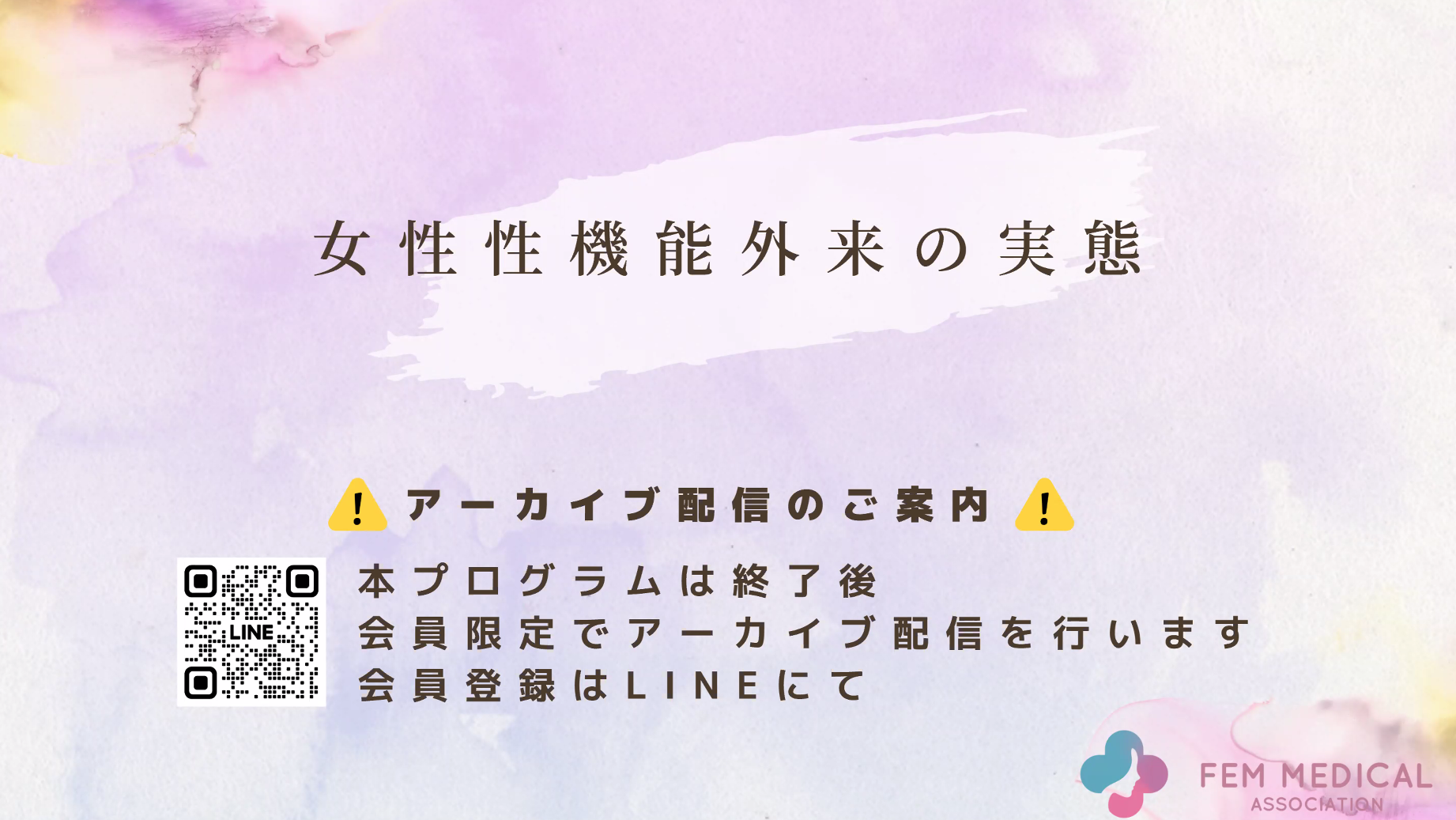
~女性の健康と美容のためのホルモン、ペプチド療法~前田 陽子 医師
▍“見た目の老化”は内分泌のサイン
前田医師は、肌・体型・気分の変化など、加齢による表面の不調が「ホルモンバランスの乱れ」のサインであることを強調。エストロゲンやDHEA、成長ホルモンなどを中心とした内分泌の理解なくして、美容医療の限界は突破できないと語った。
▍鍵となる「ペプチド」と「ホルモン補充」
ペプチド製剤(例:セマグルチド、テスモレリンなど)を用いた再生医療的アプローチの可能性を紹介。さらに、米国で主流となっているバイオアイデンティカルホルモン(BIH)補充療法にも触れ、「加齢=劣化」ではなく、「加齢=再設計のタイミング」と捉える思考転換を促した。
▍健康寿命延伸とQOL向上に資する医療へ
美容医療がQOL(生活の質)を向上させる“入口”であるならば、ホルモンやペプチド療法は“土台”だと語る前田医師。
単なる美容目的にとどまらず、プレ更年期や更年期女性の医療アクセス改善に向けた連携の必要性を訴え、包括的な健康支援の在り方を提示した。
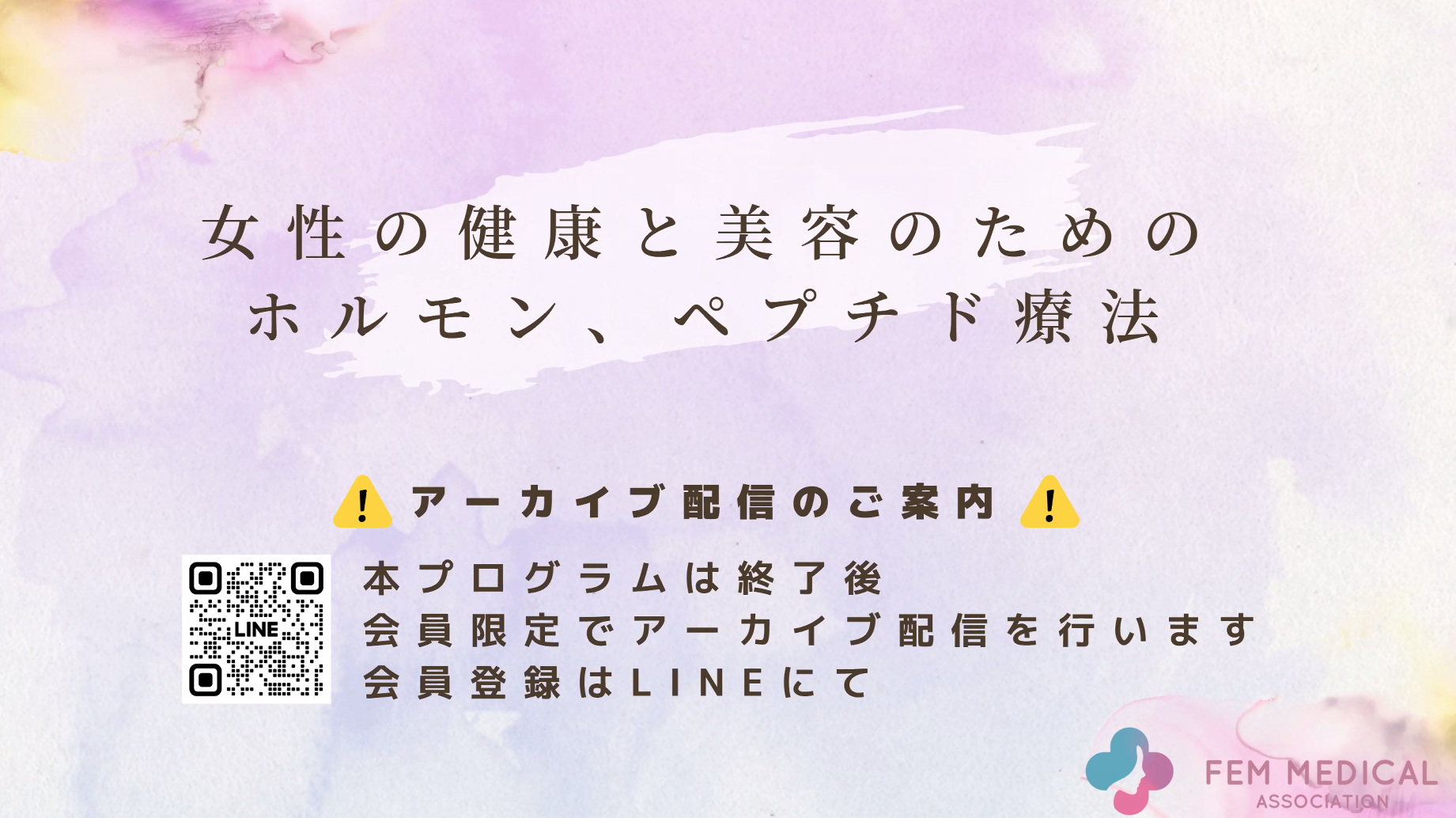
編集長POINT
~ホルモン・性・膣――美容医療がタブーとされてきた領域に踏み込む日~
フェムゾーン医療の“次の当たり前”をつくる学会が始動した。
女性のQOL(生活の質)と美容医療の“あいだ”にある未開の地。いま、医師たちはその“沈黙領域”に手を伸ばし始めた。
今回の学会で浮き彫りになったのは、「美容医療」だけでは解決できない“声なき不調”とどう向き合うかという問題だ。膣ヒアルやホルモン療法といった領域は、依然としてタブーとされやすく、情報の非対称性が極めて高い。
その中で、宮本医師は「過剰治療への警鐘」を鳴らし、中村医師は「性機能の実態」と「医師の関わり方の難しさ」を語り、前田医師は「抗加齢医療としての内分泌ケア」を提示した。
いずれも共通していたのは、「美容=外見」という旧来の枠組みを超え、“個の健康”と向き合う意思である。
今後、美容医療が真に進化するには、「膣」「ホルモン」「性」など、これまで曖昧にされてきた分野と誠実に向き合い、“健やかさ”と“美しさ”の境界線を再定義することが求められる。技術だけでなく、知識・倫理・対話力が問われる時代に入ったのだ。
女性の身体と感情に寄り添い続ける医師の存在が、“見えない課題”の可視化と、治療の新たな基準づくりへとつながっていくと信じたい。
まとめ
“女性の声なき痛み”に、医療がどう応えるか——。
今回のオンライン学術集会は、単なる専門医の知識共有にとどまらず、**「女性の身体と心の悩みを、正しく語れる社会をどうつくるか」**という問いを私たちに投げかけた。
“恥ずかしいこと”“加齢のせい”“仕方ない”とされてきた症状を、エビデンスに基づいた医療として扱う。これこそが、次世代フェムケアの出発点だとNEROは考える。
オンラインだからこそ届いた声もある。
地方の医師や、日々の診療に追われる現場の人々に、“隠された領域の医療”の必要性を伝える場となったことは大きな意義である。
NEROは、医療者・患者・社会のあいだを繋ぎ、知ること・語ること・向き合うことを応援していきたい。フェム医療は、未来の当たり前になる——その第一歩を、私たちは確かに見届けた。
 出典:PRTIMES
出典:PRTIMES





