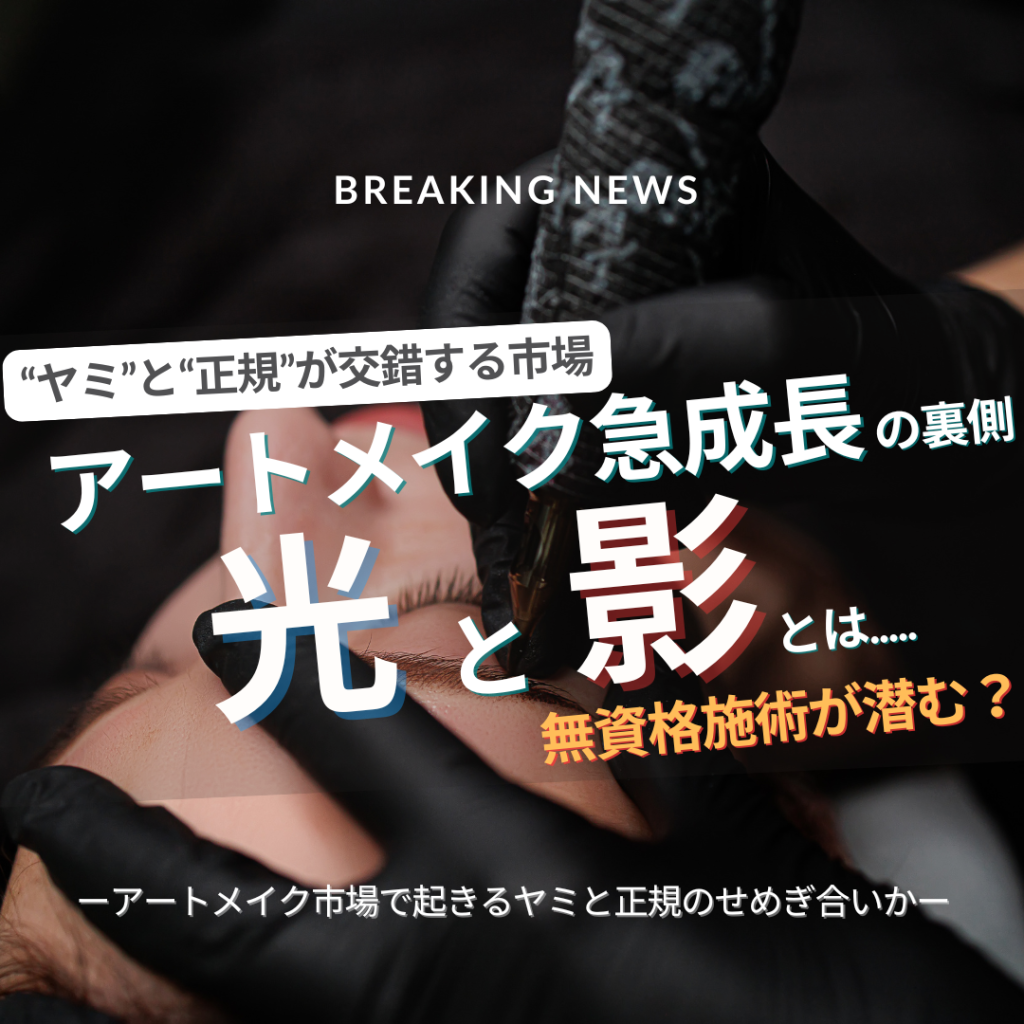
眉や唇に色素を入れ、数年間持続する「アートメイク」
その人気は、コロナ禍以降の美容需要拡大を背景に、性別や世代を超えて広がっている。
しかし、都市部では医師の指示を受けない“ヤミ看護師”や、資格すら持たない無資格者がマンション一室やレンタルスペースで施術を行うケースが後を絶たないという報道がちらほら...。
過去には肝炎感染や角膜障害の事例も報告され、厚生労働省はアートメイクを医療行為と位置付けているが、制度的な隙間を突くグレーゾーンは温存されたままだ。
その狭間で、正規の医療従事者による安全確保の枠組みが試されている。

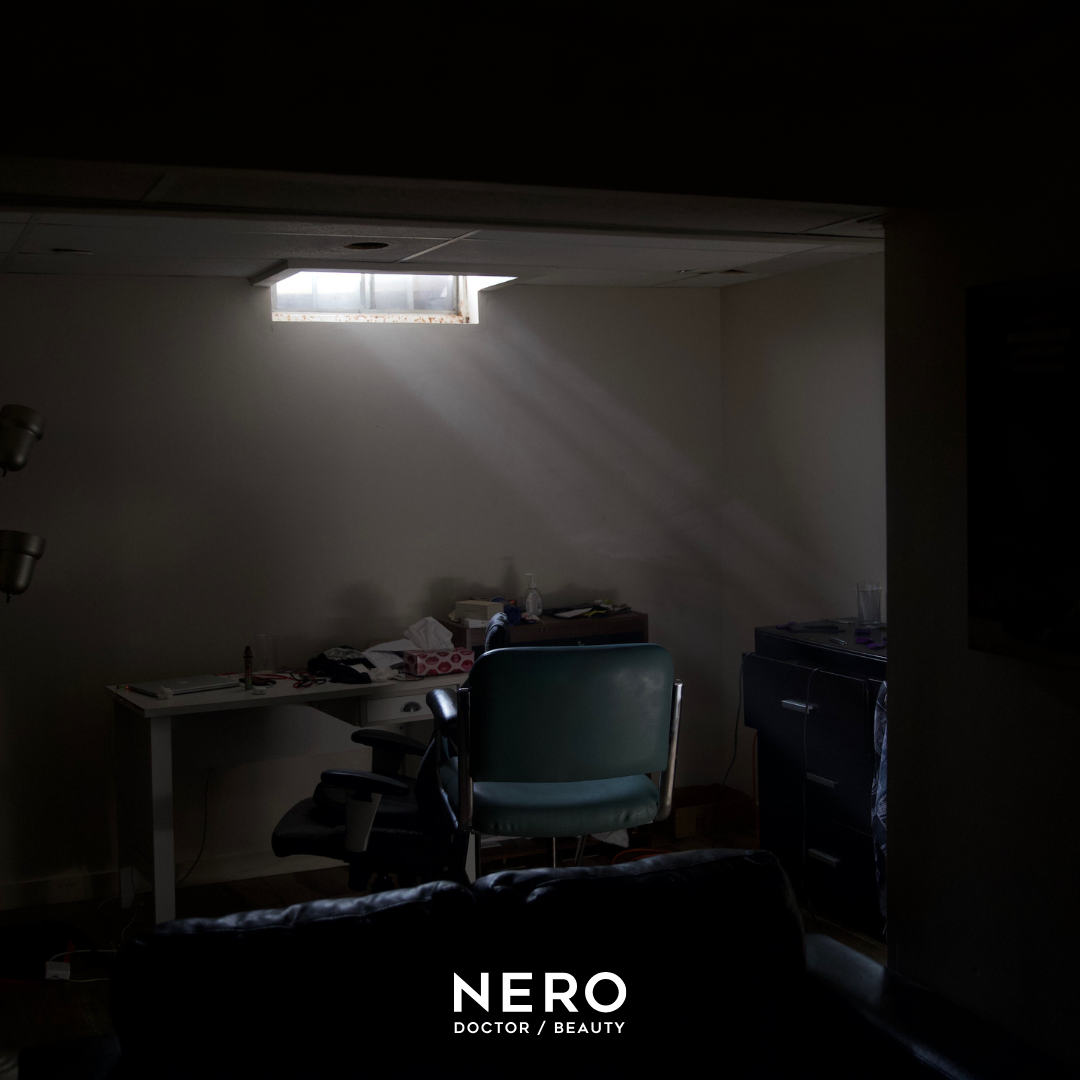
【4】今こそ制度の明文化を
アートメイクは美容目的だけでなく、がん治療による脱毛や外傷後の再建など医療的意義も持つ。
しかし、この価値を守るには、
-
施術者資格の範囲と要件の明確化
-
施設衛生基準の法的義務化
-
色素・機器の国内安全基準の設定
-
広告・価格表示ルールの厳格化
といった包括的な法整備が急務だ。
グレーを放置すれば、正規の努力が市場ごと侵食されかねないとNEROでも以前から言及してきた。
編集長ポイント
~安全と美の均衡をどう取るか、業界の覚悟が問われる~
ヤミの温床を断ち、正規の価値を守るための法整備を
アートメイクは、美容医療の新しい象徴であると同時に、医療安全の試金石でもある。
制度の穴を突くヤミ施術は、単に違法というだけでなく、業界の信頼資本を毀損する“構造リスク”だ。
正規従事者と消費者の双方に安心をもたらすためには、規制強化ではなく正規ルートの明文化と社会的浸透が鍵になる。
この分岐点を見誤れば、成長市場は一転して不信市場へと傾くリスクもある。

▲以上で終了▲
NEROでは美容医療に関連するニュースをキャッチ次第、投稿していきます!
編集長のコメントも記載していくので、情報をトレンドキャッチしたい人はぜひお気に入りに登録してくださいね。







