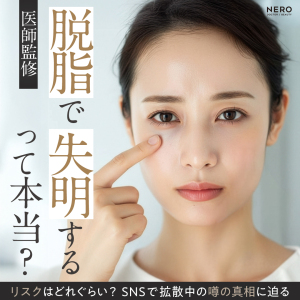垂れ乳の改善は、年齢や妊娠によって変化したバストを、自分にとって納得のいくように整えるためのステップです。
まずはバストが垂れる原因を理解し、正しい方法を選ぶことが大切。
「よく聞く噂」の真相にも迫り、本当の垂れ乳改善につながる知識を身に付けましょう。
「垂れ乳にコンプレックスがある」「どうにか以前のようなバストを取り戻したい」と悩む方は必見です。
垂れ乳はなぜ起こるのか

出典:photoAC
バストが垂れる原因は、年齢だけではありません。
皮膚や靭帯、筋肉、ホルモンなど、体の複数の要因が重なって垂れを引き起こします。
誤ったケアや姿勢も影響するため、まずは垂れ乳の仕組みを正しく理解するところから始めましょう。
■バストが垂れる主な原因と「よく聞く噂」の真相
バストが垂れる主な原因は、胸を支える「クーパー靭帯」の伸びや断裂、皮膚の弾力低下といわれています。
クーパー靭帯の主成分は、コラーゲン。
年齢とともにコラーゲンが減少したり質が低下したりすると、クーパー靭帯も弱くなってしまいます。
また、もともとあまり伸縮性がないうえ、妊娠や筋力の低下などでクーパー靭帯に負荷が増えると、伸びたり切れたりしやすくなります。
女性ホルモンの変動もバストの垂れに影響を及ぼします。
産後や閉経後は女性ホルモンの分泌低下によって乳腺が萎縮し、バストがボリュームダウン。
余った皮膚などにより垂れ乳につながるケースがあります。
「授乳をすると胸が垂れる」という話をよく耳にする方もいるでしょう。
アメリカのAesthetic Surgery Journalに掲載された研究(Brian Rinker, 2008)*によると、授乳がバストの外観に悪影響を与えることはないと結論付けられています。
そのため、実際には授乳そのものではなく、妊娠による急激な体重増減や乳腺の収縮が関係していると考えられています。
*参考文献:Brian Rinker, MD(2008)『The Effect of Breastfeeding on Breast Aesthetics』/Aesthetic Surgery Journal
■垂れ乳のセルフチェック方法
自分の胸の状態を知ることは、垂れた胸を戻すためのケアを始めるうえで欠かせません。
まずは簡単なセルフチェックで、垂れ乳かどうかチェックしてみましょう。
鏡の前で肩をまっすぐにして立ち、鎖骨の中心と左右のバストトップ(乳頭の位置)を結んで三角形の形を確認します。
正三角形が理想的ですが、縦長の三角形の場合は垂れ乳の傾向にある可能性が高いといえます。
より正確に知りたいという場合はメジャーで三角形の辺の長さを測ってみましょう。
また、肘の位置を基準に胸の垂れ具合を確認する方法もあります。
一般的には、バストトップが肘のラインより下にあると下垂傾向にあるといわれています。
垂れ乳の改善に効果が期待できるセルフケア

出典:photoAC
垂れた胸を改善するためには、まず日常生活の中でできるセルフケアを取り入れてみましょう。
ここでは2つのセルフケアをご紹介するので、ご自身の生活に合わせて実践してみましょう。
■筋トレと姿勢改善でバストを支える筋肉を鍛える
垂れ乳の改善には、バストを下から支える大胸筋を鍛えることが効果的です。
自宅でできる簡単なトレーニングとして、壁に向かって行う「壁腕立て伏せ」や、胸の前で両手を合わせて押し合う「合掌ポーズ」があります。
どちらも特別な器具を用意することなく手軽に取り組めるので、今日からでも始められます。
また、猫背の姿勢を改善するだけでも垂れ乳の改善に効果が見込めるでしょう。
背筋を伸ばすと胸の位置が上がって見えるうえ、垂れ乳の予防にもつながります。
知らず知らずのうちに丸まっている体を意識して整えていきましょう。
■ナイトブラや補整下着を正しく選ぶ
就寝中や日常の重力による引っ張りから胸を守るには、ナイトブラや補整下着の活用が有効。
ナイトブラは就寝中もバストをホールドしてくれるので、バストを正しい位置に保ち、垂れ乳を防ぎます。
選ぶ際は「サイズが合っていること」「締め付けすぎないこと」「通気性のよい素材」である点が重要です。
また、垂れた胸をしっかりと支える昼間用ブラジャーの着用も大切です。
サポート力とフィット感を重視し、自分の体型に合っているか定期的に見直しましょう。
合っていないブラジャーを着用していると、せっかくの補整効果が十分に発揮されません。
日常生活でできる垂れ乳の予防習慣

出典:photoAC
「垂れ乳にならないために」もしくは「垂れ乳がひどくならないように」予防習慣を取り入れることも大切です。
■姿勢・体重管理の見直し
姿勢の悪さは胸が垂れる大きな要因の1つです。
セルフケアでもお伝えしましたが、日頃から姿勢を意識することが垂れ乳の予防になります。
肩甲骨が内側に寄り、背骨は体を横から見た時に自然なS字を描く状態が理想的です。
また、急激なダイエットで脂肪が減ると、バストボリュームの減少と皮膚のたるみを招く可能性があります。
バランスのとれた栄養摂取を行いながら、緩やかな体重管理を心がけましょう。
■睡眠・栄養・ホルモンバランスの関係
質のよい睡眠と栄養バランスのとれた食事は、バストのハリを支える肌・筋肉・ホルモンの働きに密接に関係しています。
バストの成長に関わる女性ホルモンや成長ホルモンは、睡眠が不足すると分泌量が減少傾向に。
とくに、成長ホルモンの分泌は入眠直後に大量に放出されるため、睡眠サイクルを考慮すると、22時前後の就寝がより望ましいといわれています。
食事では、たんぱく質・ビタミンE・大豆イソフラボンなどを意識すると、女性ホルモンのバランス維持に役立ちます。
とくに大豆イソフラボンは、女性ホルモンに似た働きを持つとされ、ホルモンバランスを整えたりバストのハリをキープしたりする効果が見込めるといわれています。
垂れ乳改善をサポートする美容医療の選択肢
セルフケアを続けても垂れ乳改善に大きな変化を感じにくい場合、美容医療を検討する人も少なくありません。
バストのたるみやボリューム不足に対しては、メスを使わない施術から外科的手術まで幅広い方法があります。
それぞれの特徴を理解し、自分の希望やライフスタイルに合った選択を行うようにしましょう。
■メスを使わない施術「ヒアルロン酸注入」「脂肪注入」
メスを使わない垂れ乳改善方法としては、ヒアルロン酸注入や脂肪注入があります。
ヒアルロン酸注入は、もともと体内にある成分であるヒアルロン酸をバストに注入して、ボリュームや形を整える施術です。
比較的リーズナブルなうえ、ダウンタイムが短いため「プチ豊胸」ともいわれる方法でもあります。
自然な仕上がりが期待できる点からも選ばれやすくなっていますが、効果は半永久的ではない点には注意しましょう。
効果をキープしたい場合、定期的に施術を受ける必要があります。
一方、脂肪注入は自分自身の脂肪を採取して注入する方法で、自然な仕上がりで、半永久的な効果が得られる点が特徴です。
ヒアルロン酸注入に比べるとダウンタイムは長めで、脂肪吸入部分のかゆみや肌の表面がボコボコする症状が数ヶ月にわたる場合があります。
いずれも「胸の垂れを戻す」直接的な手術ではなく、ボリュームを補うことでバストラインを整える施術であることを理解しておきましょう。
■外科的施術「バストリフト」
垂れた胸を根本から戻すためには、外科的な施術であるバストリフトを検討しましょう。
これは、余分な皮膚や脂肪を除去し、乳頭の位置を適切な高さに整える方法です。
手術は局所麻酔または全身麻酔で行われ、クリニックによって術式が異なりますが、いずれの場合も一定期間のダウンタイムが必要です。
まとめ
垂れ乳の改善は、加齢や妊娠などで変化した体を受け入れながら、段階的にケアを重ねていくことが大切です。
姿勢や筋肉のトレーニング、正しいブラジャー選びといったセルフケアを続けることで、自然なバストラインを保つサポートができます。
さらに、美容医療を取り入れる場合は、施術の種類やリスクを正しく理解し、後悔のないよう自分のライフスタイルに合った方法を選ぶことが重要です。
信頼できる専門医のアドバイスをもとに、自分らしい美しさを目指していきましょう。
この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事
| ・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。 ・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。 ・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。 |
【施術の内容】豊胸術
【施術期間および回数の目安】通常1回 ※状態によって異なります。
【費用相場】
・シリコンバッグ豊胸:約 ¥600,000~ ¥1,000,000
・ヒアルロン酸豊胸:約1ccあたり ¥3,000~ ¥4,000(使用量は個人差があります)
・脂肪注入豊胸:約 ¥800,000~ ¥1,200,000
・ハイブリッド豊胸:約¥1,300,000~¥3,000,000
※各クリニックによって異なります。本施術は自由診療(保険適用外)です。
【リスク・副作用等】内出血、血腫、感染、痛み、傷口の赤み・硬さ・突っ張り・色素沈着、アニメーション変形など
【未承認機器・医薬品に関する注意事項について】
・本施術には、日本国内において薬事承認を受けていない未承認の医薬品や医療機器、または承認された使用目的とは異なる用途での使用を行う場合があります。
・施術に用いる医薬品および医療機器は、医師の判断のもと導入しています。
・同一成分や性能を有する他の国内承認医薬品および医療機器は存在しない場合があります。
・重大なリスクや副作用が明らかになっていない可能性があります。
・万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。