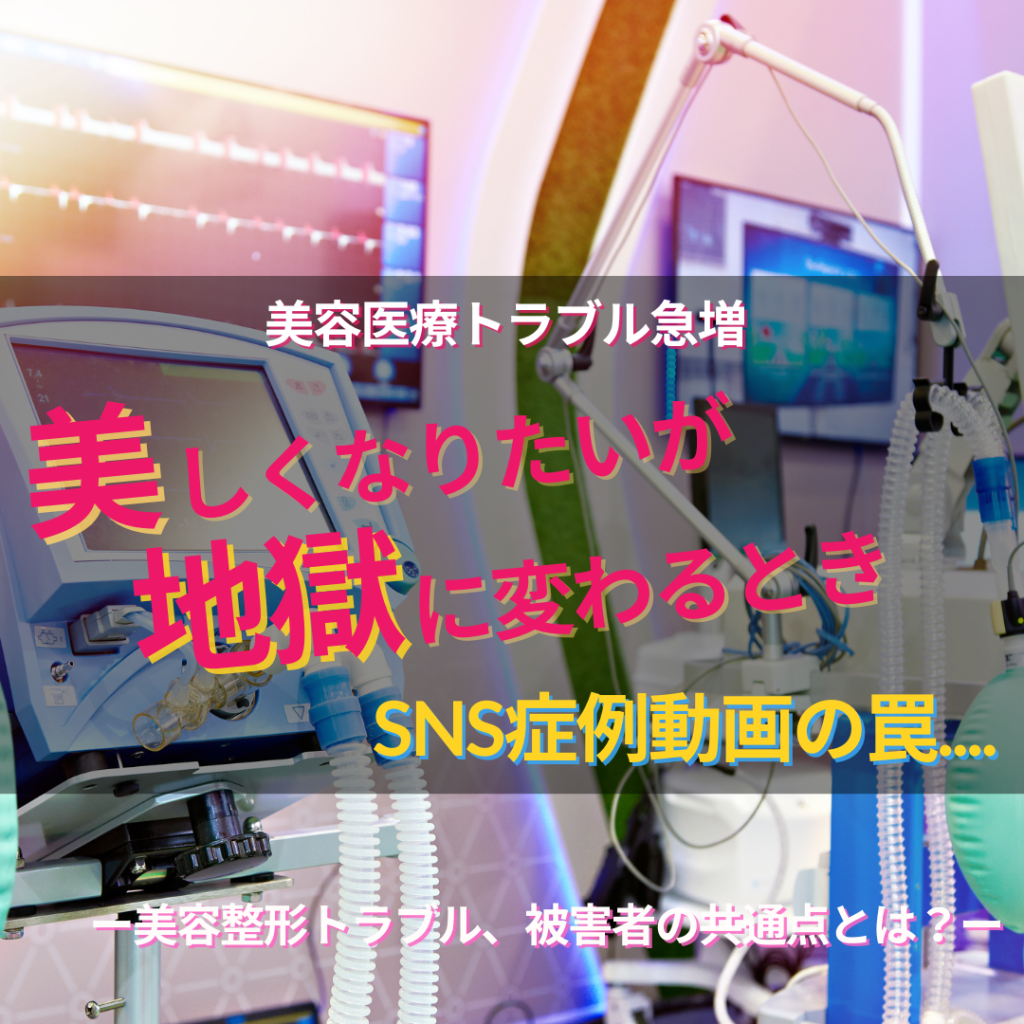
INDEX
NEROが美容・健康医療に関する注目のTOPICSをとりまとめ!
参考文献
▼以下、参考内容/
▲以上で終了▲
NEROでは美容医療に関連するニュースをキャッチ次第、投稿していきます!
編集長のコメントも記載していくので、情報をトレンドキャッチしたい人はぜひお気に入りに登録してくださいね。
美容医療トレンド
2025.06.30
安達 健一
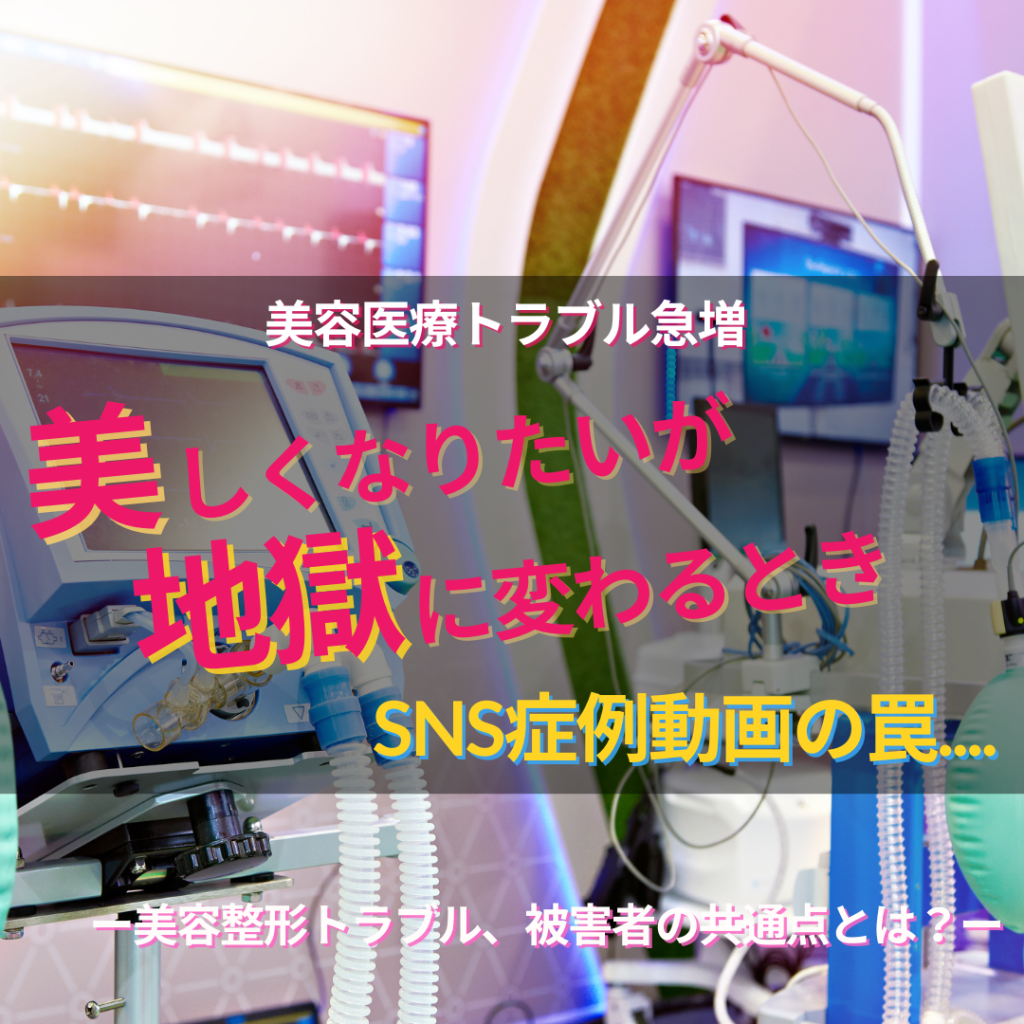
INDEX
▼以下、参考内容/
▲以上で終了▲
NEROでは美容医療に関連するニュースをキャッチ次第、投稿していきます!
編集長のコメントも記載していくので、情報をトレンドキャッチしたい人はぜひお気に入りに登録してくださいね。