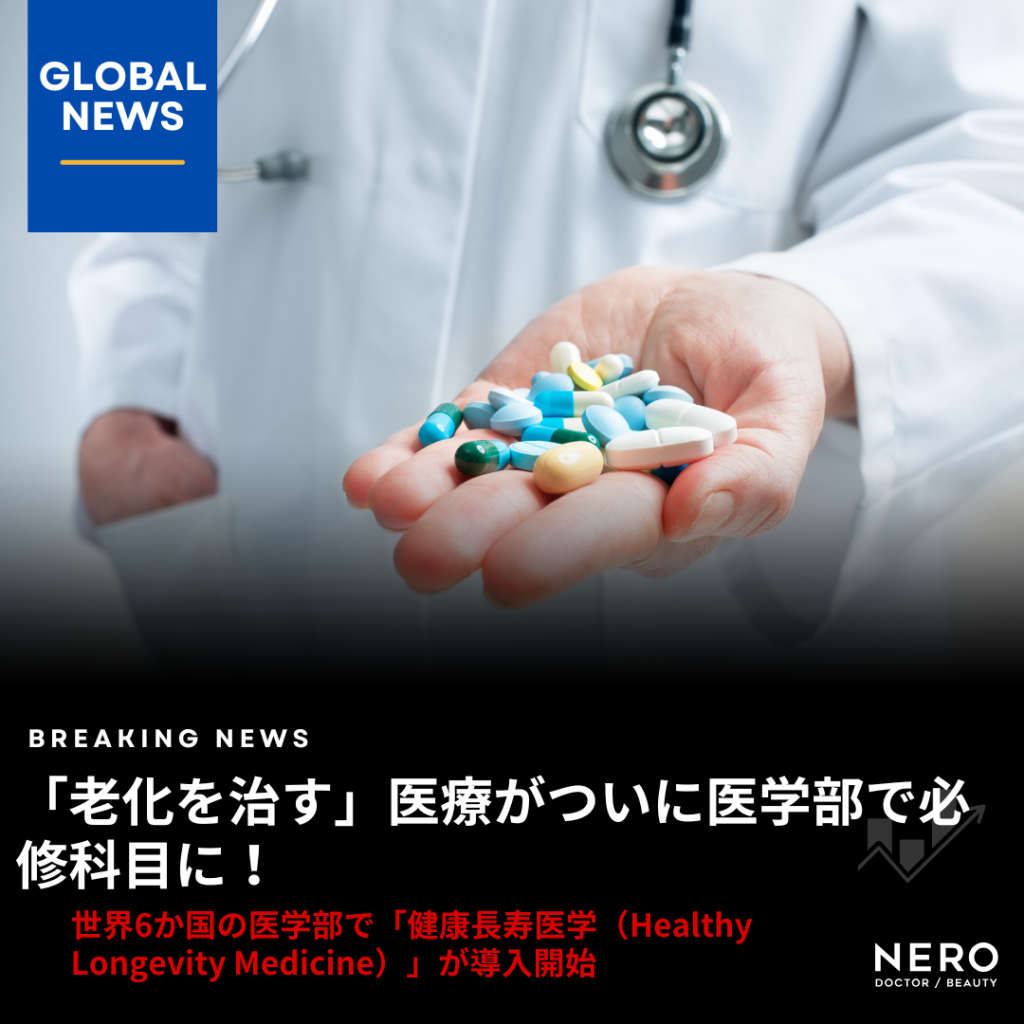📌 記事をざっくりまとめると…
-
「健康長寿医学(HLM)」=老化を遅らせ、健康寿命を延ばす新しい医学分野
-
LEH(Longevity Education Hub)が世界の医学部カリキュラムに導入開始
-
アジア(インドネシア・タイ)が先行、2030年には初のHLM修了医師が誕生予定
-
欧州・中東・南米でも拡大中
-
医療教育が「疾患治療」から「老化制御・機能維持」へ転換する歴史的フェーズへ
◆ 医学教育における“長寿革命”
2020年に創設されたLEHは、老化科学・予防医療・個別化医療を包括的に学べる世界初の長寿教育プラットフォーム。
設立当初からオンライン講座を無償提供し、2025年時点で13,000名以上の医療専門職が受講している。
今回、LEHは健康長寿医学(HLM)を正式に医学部教育へ組み込み、
医学生が臨床・基礎・地域医療の各ステージで「老化を治療対象として学ぶ」仕組みを確立した。
これにより、医療教育の焦点は「疾患治療」から「老化制御」「機能維持」「健康寿命の延伸」へと広がる。
◆ アジアが先陣を切る
世界初の導入大学は、インドネシアのマカッサル州立大学。
LEHインドネシア支部長ビラウ・ウィラクソノ博士の主導で、
47名の医学生がすでにHLMの授業を開始しており、516時間にわたる統合教育が行われている。
生理学や生化学、臨床実習に加え、地域ヘルスプロジェクトや問題解決型チュートリアルが導入され、
アジア初の「老化医療を体系的に学ぶ医学生」が2030年に誕生する見込みだ。
続くタイでは、キングモンクット工科大学ラドクラバン校が
4年生対象にHLMモジュールを必修化し、29名が初年度プログラムを修了。
さらにタイ予防医療協会では、ライフスタイル医学専門医課程にもHLMを統合し、176名の臨床医が受講中だ。
アジアがリードする形で、長寿医療教育が医療現場の主流に入りつつある。
◆ 欧州・中東・南米へ広がる波
欧州ではリトアニア保健科学大学がLEHと協働し、個別化医療修士課程の開設を計画。
ボスニア・ヘルツェゴビナでは、サラエボ科学技術大学(SSST)が選択科目「Longevity Medicine – Healthy Aging」を導入し、
連邦教育科学省の支援を受けて人気科目に成長している。
ブラジルではリオデジャネイロ州立大学(UERJ)と協定を進め、
アラブ首長国連邦(UAE)では「Institute for Healthy Longevity Abu Dhabi」 と提携し、
中東・湾岸諸国における認定長寿プログラムの共同開発が進行中。
◆ LEH創設者らが描く未来
LEH共同創設者でありシーバ長寿クリニック医療ディレクターのエヴェリン・ビショフ教授は、
「HLMを必修科目として導入することは、長寿医学を“正式な医学分野”として確立する決定的な一歩です」 とコメント。
また、Insilico Medicine CEO アレックス・ザヴォロンコフ博士はこう語る。
“Integrating Healthy Longevity Medicine into mandatory MD curricula ensures that the next generation of doctors can lead clinical trials targeting aging mechanisms.”
「健康長寿医学を必修化することで、老化メカニズムを標的とする臨床試験をリードできる医師が誕生します。」
この教育改革は、老化を「不可避な衰退」ではなく、
“測定・介入・改善できる臨床プロセス”として扱うことを可能にする。
編集長POINT
「稼働年齢を延ばす」医療教育の幕開け
HLMカリキュラムの導入は、医学が“延命”から“稼働寿命”を延ばすステージへ移行した象徴だ。
美容医療・再生医療・予防医療の分野においても、
老化を「見た目の問題」ではなく「機能の最適化」として扱う視点が求められる。
この流れは、医師教育の構造変化=自由診療の未来戦略でもある。
「病気を治す医師」から「健康を維持する医師」への進化が、
次の医療市場を形づくることになるだろう。
まとめ
-
LEHが主導する「健康長寿医学(HLM)」が医学部教育に正式導入。
-
アジア(インドネシア・タイ)を中心に、欧州・中東・南米へ波及。
-
2030年には初のHLM修了医師が誕生予定。
-
老化を“治療可能なプロセス”として扱う教育改革が進行。
-
医療のゴールは「寿命延長」から「稼働年齢の延伸」へ。
NEROでは、アジア各国における医療の制度変容と自由診療の構造分析を継続的に報じている。
今後も「医療市場の倫理とサステナビリティ」をテーマに、
日本がどこまで自由診療を拡張すべきか、その境界を問い続ける。