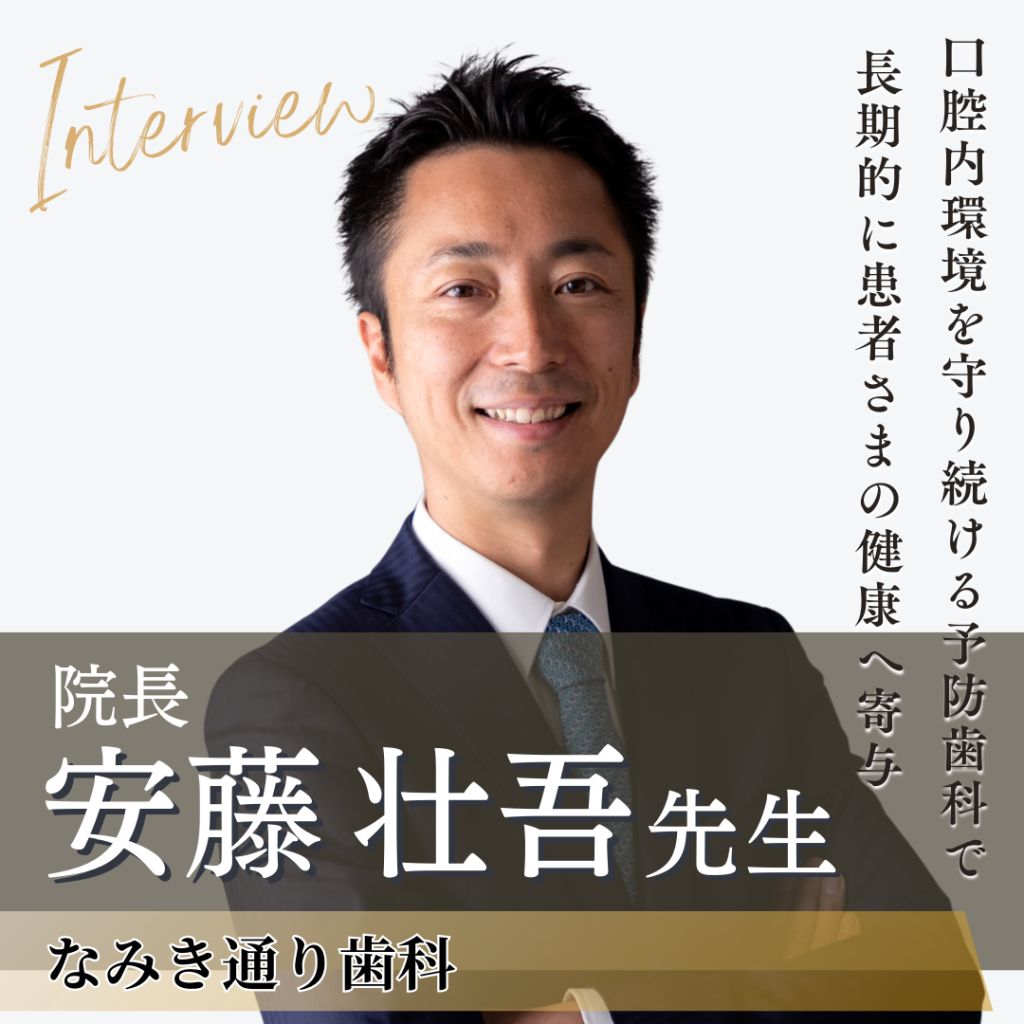
なみき通り歯科 院長 安藤 壮吾先生へインタビュー。安藤先生は、歯科医療業界におけるKOL*として注目を集める歯科医師です。開業後、治療主体型から予防主体型の歯科医療へとシフトし、患者さまのQOL向上に力を注いでいます。今回は、安藤先生の予防歯科医療への哲学や、「なみき通り歯科」の革新的な予防歯科医療の取り組みと使命、さらに今後の歯科医療業界へ期待することなどを伺いました。最後には読者へのメッセージもいただきましたので、ぜひご覧ください。
*KOL…キーオピニオンリーダー。特定の分野・業界で影響力を持つ人物や専門家のこと。
INDEX
ドクタープロフィール
なみき通り歯科 院長
安藤 壮吾(あんどう しょうご)先生
技術・設備・コミュニケーションのいずれも妥協せず、「すべてを兼ね備えた唯一の歯科医院をつくり上げる」がモットー。【予防歯科医療】を主軸とし、患者さまの口腔内を継続的にメンテナンスしてQOL向上を目指す。また、「なみき通り歯科」のスタッフは、一人ひとりがプロ意識を持ち続けることで幅広いスキルを磨き、チーム一丸となって日々患者さまの治療にあたっている。
| (経歴) 2006年 朝日大学歯学部歯学科 卒業、愛知学院大学歯学部附属病院 入職 2013年 なみき通り歯科 開業 2021年 なみき通り歯科・矯正歯科 移転 2021年 なならの丘デンタルクリニック 開院 (所属学会・資格) 日本歯周病学会 歯周病専門医 EAO(ヨーロッパインプラント学会)認定医 日本臨床歯周病学会 認定医・中部支部理事 OJ(Osseointegration Study Club of Japan)正会員・理事 日本口腔インプラント学会 PHIJ(Perio Health Institute Japan) Co-Director 日本歯科医師会 愛知県歯科医師会 名古屋市南区歯科医師会 |
▷なみき通り歯科の公式HPはこちら
▷安藤 壮吾先生公式インスタグラム(@shogo_dentist)はこちら
歯科医師としての背景 ~インプラント・歯周外科・セラミック修復を極める~

―――歯科医師を目指したきっかけを教えてください。
私の父が歯科医師で、幼いころから働く父の背中を見て育ちました。当初は別の医療職を目指していたものの、最終的に父と同じ歯科医師を目指すことにしました。そもそも自分が医療分野に魅力を感じた背景には、父の存在が潜在意識にあったのではないかと思います。
―――安藤先生は歯科医師になった後、さまざまな場所で研鑽されてきました。開業前までの経緯をお聞かせください。
勤務医時代は、壊滅的な状態に陥った患者さまの口腔内をドラマティックに復興させるために、インプラント・歯周外科・セラミック修復などの知識や技術を一所懸命学びました。「歯科治療を通して患者さまのQOL(=生活の質)を上げることこそ、僕が目指す道だ!」と、熱い想いで診療にあたっていましたね。
しかし、いくら丁寧に治療をしても、同じ患者さまがお口のトラブルで再び来院されることも少なくありません。僕が思い描いていたような治療のゴールや患者さまのご希望までたどり着けないことが、専門性を極めるほどに高い壁となって立ちはだかりました。基本的に、口腔内の修復や再建は再生能力のない人工物を使います。冷静に考えると、天然の口腔内が崩壊するような環境に人工物を入れても、人工物を長期に安定して機能させることは難しいですよね。しかし当時は、「自分の知識や技術が足りないせいだ」と、さらに歯科の勉強を深めて行きました。
予防歯科医療へのこだわり・熱意 ~口腔から全身の健康まで考える~

―――勤務医時代に行っていた治療主体型から、予防主体型の歯科医療へ重点をシフトしたのはなぜでしょうか?
あるとき、お口のトラブルを抱えた患者さまを受け入れて、そのたびに人工物で置き換える医療を一生やり続けたいか?と自分自身に問いかけました。僕の答えはNOでした。
その理由は、専門的な知識や技術を徹底的に極めても、人工物を使った治療ではトラブルを繰り返すということに気づいたから。そこで、「このままではいけない。患者さまの口腔内を健康に保ち続ける【予防歯科医療】を主軸に据えよう」と方向性を変えました。歯科勤務医生活も終わりに近づいた開業の直前に、僕の頭にはそのようなビジョンが浮かんできたのです。
―――開業後、予防歯科医療についてはどのように学んだのですか?
開業から1年が過ぎた頃、テレビや新聞などで何度も取り上げられるほど有名な「日吉歯科診療所」理事長の熊谷 崇先生に教えを請う機会をいただきました。名古屋市から熊谷先生の診療所がある山形県まで当院のスタッフ全員で見学に行き、予防歯科医療のシステム・方法・哲学などを徹底的に学びました。それを持ち帰り、忠実に再現して行こうと当院のスタッフ全員で取り組み始めたのが「なみき通り歯科」における予防歯科医療の始まりです。
―――安藤先生が理想とする予防歯科医療を実現するにあたり、「なみき通り歯科」で最初に行ったことを詳しく教えてください。
歯が失われる理由の大半は、虫歯か歯周病。まずは、それらの予防をしっかりやろうと思いました。一般的に、虫歯は虫歯菌によって歯に穴が開いた状態で、虫歯になった部分を削り、セラミック・金・銀などで埋めるのが虫歯治療、というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。しかし、実は虫歯という疾患は、口腔内で歯の脱灰*と再石灰化*のバランスが崩れてしまった状態を指します。
口腔内の環境を整えたうえで治療できれば良いのですが、環境が整わない状態で歯を削ってそこにどんな材料を詰めたとしても、結局はお口のトラブルがくり返されてしまいます。だからこそ、虫歯の引き金となる歯周病が起きた時点で原因をしっかりと見極めることが重要です。原因が生活習慣・歯みがき・虫歯菌の数・ほかの生活因子のどこにあるのか、いわゆるスクリーニングを歯科衛生士が患者さま一人ひとりに行うようにしました。そうして、歯のトラブルにつながる原因を取り除いたうえで、必要であれば歯科医師が治療するという流れを最初につくったのです。
*脱灰…虫歯の原因菌が食物中の糖を分解してつくった酸により、歯の表面にあるエナメル質からカルシウムやリン酸が溶け出すこと。
*再石灰化…だ液が酸を中和して、脱灰で溶け出したカルシウムやリン酸がふたたび歯に取り込まれること。
―――「なみき通り歯科」で予防歯科医療をさらに推進するため、続いて取り組んだことは何でしたか?
歯科衛生士の徹底的なスクリーニングと歯科医師の治療をもってしても、お口のトラブルを防げない事例も起きてきました。そこで、次に行ったことは患者さまへの過去についてのヒアリングです。
例えば、「口呼吸を指摘されたことがある」「アレルギー体質だった」「指しゃぶりをしていた」などの過去の情報を患者さまから教えていただきました。幼少期の背景が成人期・壮年期の口腔環境に悪影響を及ぼすのではないかと考えたからです。さらに、成人期・壮年期の虫歯や歯周病にスポットを当てるのではなく、子どもの頃からアプローチして口腔機能の成長を正しく導くことが重要だと考えました。
子どもの口腔環境を考え続けていると、口腔機能のすこやかな発達のためには、乳幼児期の離乳食や間食もポイント。それらを指導できる管理栄養士が院内に必要だ、というアイデアが浮かびました。すると今度は、胎児や生後間もない赤ちゃんのことも気になり始めて「妊産婦さんの頃からできることはないだろうか?」と。そのように、患者さまの一生をどこまでも遡って行きました。
そうして、患者さまがお母さんのお腹にいるマイナス1歳~成人期・壮年期に渡る口腔内の健康をサポートするという当院の予防歯科医療の流れが完成して行きました。
―――最終的に、安藤先生がたどり着いた予防歯科医療の哲学について教えてください。
子ども時代は口腔機能発達不全症*のコントロール、大人になったら虫歯や歯周病の予防、高齢期は口腔機能低下症*への対策。つまり、ライフステージに合わせた予防歯科医療が一生涯に渡って途切れることなく必要だということです。口腔内の環境を守り続ける予防主体型の医療=長期的に患者さまの健康へ寄与できる、というのが僕の哲学です。
*口腔機能発達不全症…明らかな原因がないにも関わらず、食べる・話す・呼吸するなどの機能が十分に発達していない、または正常な機能を獲得できておらず、専門的なサポートが必要な状態のこと。
*口腔機能低下症…加齢・疾患・障害などのさまざまな原因で、口腔機能が低下している疾患。放置すると咀嚼障害や摂食嚥下障害などを引き起こし、さらに進行すると全身の健康状態に悪影響を及ぼすこともある。
「なみき通り歯科」の強み ~予防歯科医療をベースに患者さまの人生に寄り添う~

―――経営的な視点では、予防歯科医療をどのようにお考えですか?
予防歯科医療を教える立場になってきた今、「予防歯科医療だけでは、実際問題なかなか経営が厳しいのでは?」というご意見をよくいただきます。でも、僕はそうは思いません。予防主体型歯科医療がメインの当院は歯科衛生士の人数が非常に多く、歯科衛生士が主体となって患者さまの口腔内を継続的にメンテナンスして健康に寄与するというスタイルが基本。予防主体型の医療であれば患者さまは継続的に来院されます。
また、歯科衛生士の雇用不足が問題になっている中、当院ではスタッフ向けの無料保育所をつくったり、育休・産休の取得も推奨したりしています。妊娠・出産によってキャリアが途切れることなく歯科衛生士が長く働き続けられるように、環境整備のための投資も行っています。
収益性の高い治療をたくさん行えば、利益は上げられるでしょう。しかし、患者さまと二人三脚でコツコツと健康を積み上げながら年月を重ねて行く方が健全な医療であり、かつ利益も担保し続けられるのではないかと思います。歯科医院としての目先の利益より、患者さまの人生に大きな価値を創造することが、成功のカギになるでしょう。
予防歯科主体の経営が難しいとは思いませんが、僕が今もしつまずいたら、若手の先生方が予防歯科医療に取り組みづらくなりますよね。ですから、予防歯科医療をベースにした歯科医院の経営で成功しなければならないと自分自身にプレッシャーをかけています。
―――「なみき通り歯科」ではスタッフの総合力を高めるために、どのような取り組みを行っていますか?
当院では、知識や哲学を共有する目的で、10年以上にわたり症例検討の時間を毎日意図的につくっています。歯科医師・歯科衛生士・放射線技師・管理栄養士が参加し、午前と午後の診療前それぞれ15分間ずつの時間を症例検討に当てています。歯科衛生士が持ち回りで、受け持ち患者の予防プログラムについて発表し、質疑応答も行うのです。
この症例検討のメリットは、2つあります。1つ目は、院内のスタッフ全員で患者さま情報のシェアができること。2つ目は、与えられた時間内に簡潔にまとめて話す練習ができること。歯科衛生士は患者さまへの説明とカウンセリングのスキルが非常に求められる職種ですよね。自分の考えをアウトプットする練習を続けることで、歯科衛生士としての視点や方向性が明確になり、説明力が磨かれていきます。
―――今後、「なみき通り歯科」の展開についてはどのようなビジョンをお持ちですか?
10年以上集中的に予防歯科医療へ取り組み、医院規模も大きくなってスタッフの総合力もますます上がっています。そして、地域医療として患者さまの健康に寄与してきた努力が認められ、現在は行政の子育て支援センターや保健所などで講演させていただけるようになりました。この講演活動は以前から僕自身が目指してきたもので、今後も継続して取り組みたいと思っています。
また、予防主体型の健康的な歯科医療を日本中に広めるために、歯科医師や歯科衛生士の教育にも力を入れたいです。だからこそ、当院への見学はいつでも歓迎しています。
故・野村克也監督の名言「財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すを上とする」に僕は非常に感銘を受けていて。僕が関わった歯科医師や歯科衛生士のみなさんが10~20年後により良い医療を築き上げるためのお手伝いができればうれしいですね。そして、スタッフが永続的に医療に携わり、家事・育児・仕事のバランスが取れるような環境づくりも、一経営者である僕の使命かなと思っています。
歯科医療業界の展望 ~予防歯科による長期管理型の歯科医院がベースに~

―――歯科医療業界において、予防歯科医療は現状どこまで認知されているのでしょうか?
以前は、歯科医師の仕事はとにかく歯を守ることがメインでした。しかし、ここ5年間くらいで、治療主体型から予防主体型、さらにその先を見据えたムーブメントが起こっていると感じています。当院同様、正しい摂食嚥下と整った腸内環境での栄養吸収を行うために、管理栄養士が必要だと考える歯科医院も増えています。また、歯列矯正は単純に審美性を求めるだけでなく、歯並びが整ったことで摂食・嚥下・睡眠にも好影響をもたらすため、「顎口腔系は全身の健康につながる」という考え方も広まってきています。
そうした概念を歯科医療業界から社会に発信したいですね。そして、「自分の歯を守ることは、全身の健康に関わること」という認識が広まり、患者さまの行動変容につながることを目指しています。
―――今後の歯科医療業界に期待することは何ですか?
僕が期待しているのは、【長期管理型の歯科医療への転換】と【デジタル化】の2つです。今後、日本の人口はますます減少すると予想されますが、これはもう仕方のないことです。その中で、歯科医師の人口も減るでしょうから、分院展開して行く歯科医院は少なくなるだろうと考えています。
しかし、継続的な健康のサポートを目的とした、いわゆる長期管理型の歯科医療のニーズは高まり続けるでしょう。今後は歯科衛生士が予防歯科医療をメインで担うことになり、患者さまの健康を長期的に管理していくことが歯科医院のベースになるかもしれません。人口が減るとはいえ、予防歯科医療をベースに行うのであれば歯科医院の数は足りなくなるでしょう。
予防歯科医療のニーズが増えると、オペレーションやほかの業務を効率化させるために院内のデジタル化がすごく大事になってきます。その理由は、医療人がなるべく医療だけに集中できる環境をつくることが大事だからです。デジタル化の導入もたくさんの歯科医院で積極的に行われてほしいですね。
読者へのメッセージ ~『歯科医院は予防歯科医療を行う場所』という認識を広めたい~

老後の楽しみは、食事と旅行だと僕は思います。おいしいものを食べて、好きな場所へ行けるということは老後のQOLをきっと高めるでしょう。ただ、歯や体の健康は自重しないと二度と取り戻せないこともありますよね。老後にどれだけ資金の蓄えがあっても楽しみを奪われると、QOLはものすごく下がってしまうでしょう。
ですから、自分自身が生まれ持った天然の歯を本当に大事にしていただきたいです。高齢になっても健康な歯で毎日の食事から栄養が摂り続けられるって、本当にすごく幸せなこと。残念ながら、歯を失ってからその大切さに気づく患者さまもたくさんいらっしゃいます。
虫歯や歯周病になってからの治療に比べたら、予防はとても簡単です。毎日コツコツと口腔ケアを行って、予防をメインに歯科医院に通っていただければと思います。予防のために歯科医院を頼ってくださる患者さまが増えるよう、当院のある地域だけでなく日本全国にも目を向けて、スタッフ一丸となり努力し続けます。








