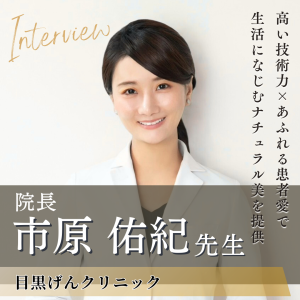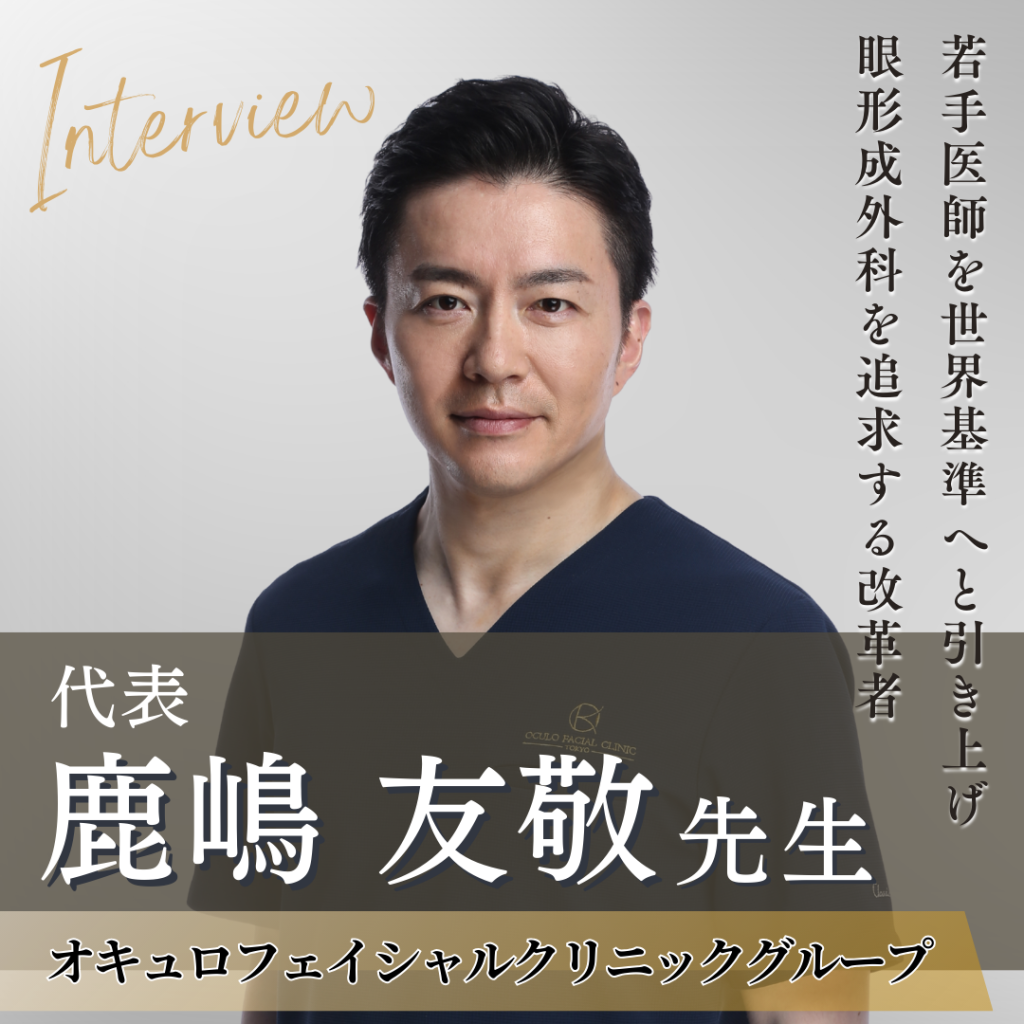
オキュロフェイシャルクリニックグループ 代表 鹿嶋友敬先生へインタビュー。所属医師のほとんどが眼科医の同グループ代表を務め、医師・教育者・経営者としてご活躍されています。
2025年に日本眼形成美容学会を設立し、眼形成外科と美容医療の発展に貢献。現在も国内外の学会に招待され、多くの講演を行っています。
今回は、鹿嶋先生が眼形成外科という領域に進んだ背景や、今後の課題、展望などについて詳しく伺いました。
INDEX
ドクターズプロフィール
オキュロフェイシャルクリニックグループ 代表
鹿嶋 友敬(かしま ともゆき)先生
これまで10年以上にわたって日米で多数手術を行ってきた実績を持つ、日本眼形成外科のパイオニア。
まぶたや眼窩、涙道に特化し、2024年1月1日〜12月31日の眼形成の手術件数は11,143件にも上るオキュロフェイシャルクリニックグループの代表を務める。
2025年には、日本眼形成美容学会(JSOPRAS)を設立。
| (経歴) 2002年 群馬大医学部卒 群馬大学 眼科学教室 2004年 伊勢崎市民病院 2005年 群馬大 眼科 2007年 聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科へ国内留学 2009年 群馬大にて眼形成外来を開設 2012年 学位取得 群馬大学眼科 助教 2010年 アジア太平洋眼形成学会理事 2015年 カリフォルニア大学 ロサンゼルス校へ留学 2017年 新前橋かしま眼科形成外科クリニック 開院 2018年 オキュロフェイシャルクリニック 東京 開院 2019年 The NewYork Times特別企画「Next Era Leaders 2019」選出 2020年 アメリカ眼形成学会(ASOPRS)会員 |
▷オキュロフェイシャルクリニック公式HPはこちら
▷オキュロフェイシャルクリニック東京インスタグラム(@oculofacial_clinic_tokyo)はこちら
▷鹿嶋 友敬先生公式ブログはこちら
▷日本眼形成美容学会公式ホームページはこちら
眼科医としての出発点と開業までの道のり ~眼形成外科を目指したきっかけ~
―――鹿嶋先生が眼形成外科という領域に強く惹かれたきっかけを教えてください。
私の学んでいた群馬大学の医局が得意としていた分野は、目の中の硝子体や網膜の手術でした。
もちろん私も眼科医として、その分野を極めていこうと思っていたのですが、同様の分野を志す若手医師が多く、このままでは横並びになってしまうと感じていたんです。
そんな時、角膜を専門とするメンターが角膜外来を担当しており、目の表面の治療に触れる機会を得ました。そこで、目の病気だけでなく、瞼や目の周囲を含めた治療の重要性を実感しました。
例えば、顔面麻痺の患者さまは、目の下の皮膚が下がることで目が乾きやすくなります。そのため、目の周りの皮膚や瞼にアプローチしなければ十分な治療はできません。
ところが当時の群馬には、その領域を担える眼科医がほとんどおらず、根本的な治療手段が欠けていました。
「どうにかして治せないものか」と模索してみると、「聖隷浜松病院」が眼形成外科に力を入れていることを知り見学へ。そこで国内留学という形で2年間研修する機会を得たのです。
今から17年ほど前、眼形成外科はまだ日本では認知度が低く、眼科といえば白内障や硝子体といった目の中の手術が主流でした。
多くの医師がそちらに進むからこそ、私は未開拓の分野に挑戦しようと決意しました。
―――鹿嶋先生は、海外の学会や留学経験が豊富でいらっしゃいます。外から日本を眺めることで、どのような心境の変化があったのでしょうか?
「聖隷浜松病院」の研修が終わる頃、シンガポールの病院を見学する機会がありました。
そのとき、現地の先生に、これまでに作成したプレゼン資料などを見せたところ、興味を持っていただき、若手医師向けの講師を依頼されたのです。
当時の私は英語に自信がなく、不安も大きかったのですが、「若手のうちはNOといわず挑戦してみよう」と決めていたので、半年かけて準備して講演に臨みました。
無事に終えたあと、シンガポールの先生から海外の学会のたびに声をかけてくれるように。
日本から参加する眼形成外科医が他におらず、いつしか日本から唯一の眼形成外科医として年に4回ほど国際学会に参加するようになりました。
その後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ見学に行く機会があり、フェローとして留学することに。
海外の学会に出席する中でも感じていましたが、アメリカで目にした医療は、日本とはまるで違う発展を遂げており、「このままでは日本の眼形成外科が世界の潮流から取り残されるのではないか」と危機感を抱きました。
私は幸運にも、国内留学やアメリカ留学と幅広い学びの機会を得ました。しかし、私のように多くの学びの場を得た眼形成外科医は、日本にはほとんどいません。
だからこそ、習得した知識や技術を日本に持ち帰り“日本の眼形成外科を変えなければいけない”、“患者さまに還元しなければいけない”という使命感が芽生えたのです。

―――数々の経験を通じて、眼形成外科クリニックを開業しようと思ったのはなぜでしょうか?
当時、日本で眼形成外科を専門に開業している医師はほとんどいませんでした。
日本の眼科医の多くは目の内部の手術に携わっており、目の周囲の疾患は「専門医がいないから治らない」と片付けられてしまうことも少なくありません。
しかし世界に目を向ければ、「治らない」とされていた病気が、当たり前のように治療されていました。
専門家がいないために、患者さまに適切な治療が行われない、その現実に強い悔しさを覚えたのです。
また、大学病院から最新の治療法を日本全体に広めるのは時間や地域性と付随する組織の壁もあり非常に困難です。一方、開業して全国に分院を作れば、日本全国に治療技術を広められます。
もちろん不安はありましたが、アメリカでは重い疾患でも日帰り手術や全身麻酔による治療が行われていたので、日本でもできるはずと開業を決断しました。
眼形成外科医の美容医療への気づき ~数々の逆風の中で垣間見た日本の立ち位置~

―――日本とアメリカの美容医療に対する専門医のギャップは、大きかったですか?
私がアメリカに行ったのは2015年。当時すでにアメリカの美容医療業界では、目の周りの施術は眼形成外科医の領域となっていました。
目の構造を理解している眼形成外科医が治療すべきだというのが、美容外科医の共通の常識だったのです。
一方で、日本の美容医療では、現在でも美容外科医による目の周りの施術を担当することができます。
アメリカの医師に「日本の美容医療では、まだ美容外科医が瞼などの施術をしている」と話すと、「アメリカも30年前は同じだった」と言います。
しかし、論文を発表するなどアクションを起こすことで、少しずつ環境を変えてきたと聞きました。
このように、日本の美容医療は、アメリカと比べて30年遅れているといっても過言ではありません。
海外の学会に参加する眼形成外科医が少なく、専門家が育たなければ、日本の眼形成外科がどんどんガラパゴス化してしまうと強い危機感を覚えました。
―――鹿嶋先生はある意味、改革者として見られることがあったかもしれません。数々の逆風の中で、どのように乗り越えられたのでしょうか?
「聖隷浜松病院」への国内留学を経て、群馬大学に眼形成外来を開設することになりました。当時としては、眼形成外来は新たな取り組みで、たしかに賛否両論ありました。
ただ、私自身は、世界の動向を把握しているからこそ、自信はありました。
眼科はオペ枠を取りにくい中、教授が理解を示しオペ枠を空けてくれるなど、サポートしてくれたおかげで実績を積み、学会発表の機会を広げられました。
海外の学会でも積極的に発表を重ねることで、国内外から少しずつ評価を得られるようになったのです。
目の前のことをコツコツと極めていくことで、少しずつ周囲への理解が深まり、眼形成外科の希少性が上がって結果的に唯一無二の存在として認められたのだと思います。
美容医療業界の課題 ~鹿嶋先生が危惧する未来とは~

―――世界を知っているからこそ、日本の美容医療業界で思うことはありますか?
眼形成外科医と形成外科医の視点は全く別のものです。眼形成外科は、0.01mmのズレが視力に直結するほど、精密さが求められる分野です。
一方で形成外科は診療範囲が広いため、すべてをカバーできるという強みはありますが、そのぶん一つの分野を極めにくい側面があります。
結果として、経験の浅い治療を行うことで患者さまに不要なリスクを背負わせてしまう可能性も否めません。
現状、美容医療業界全体を見ると、医師への教育の仕組みが機能していないのではないかと思うときがあります。
教育とは、これまでの偉人たちが発見した知識や技術を指導者から教えてもらいながら、石を積み上げるように高みを目指すようなものだと考えています。
実際私も、多くの先輩医師から指導を受け、習得した知識や技術をもとに、さらなる発展的な治療を見出してきました。
しかし、今の美容医療業界では自身で学んでいくスタイルが中心です。これでは技術が属人化するだけで、業界の発展にはつながりにくい――だからこそ必要なのは、専門分野に特化したスペシャリストの育成です。
症状に合わせて医師同士で紹介し合う仕組みがあれば、患者さまはより安心して施術に臨むことができ、業界自体の発展にもつながると考えています。
―――今後、少子高齢化やAIの発達が急速に進む可能性が高いとおっしゃっていましたが、それによって医療業界に、どのような影響が出るとお考えですか?
社会保障制度の担い手である現役世帯が減る一方で、高齢者数が増え続ければ、今のような日本の社会保障制度は維持できないでしょう。近い将来、これまでの常識が変わる瞬間がくるはずです。
そうなると、保険診療に頼る病院の経営は難しくなると思います。その半面、主に自由診療を行う美容医療クリニックが有利なのかというとそうでもありません。
世界的に見ても美容医療クリニックのマーケットサイズは大きくなっており、美容外科医も急増しています。そのため、専門性が曖昧なクリニックには淘汰されてしまうでしょう。
だからこそ、保険診療と自由診療の両方に対応できる体制が重要になると思います。さらに、専門性が高ければ、保険診療ではなく「自由診療でも受けたい」と選んでもらえるクリニックを実現できます。
私は、眼形成外科という専門性を軸に、保険診療と自由診療の隔たりをなくし、ワンストップで治療できる環境をつくりたい。それが、これからの時代に患者さまにとって最も有益な医療のかたちだと考えています。
今後の展望 ~鹿嶋先生が描く眼形成外科医の予想図~
―――鹿嶋先生は医師・教育者・経営者として、今後どのような夢を描いていらっしゃいますか?
経営のことを考えれば、マニュアルを作成し、どのレベルの医師でも治療できるクリニックを全国に展開するのが効率的かもしれません。
しかし、それでは患者さまの期待に応えられないケースも出てくるでしょう。
やはりマニュアルどおりのクリニックより、三つ星レストランのように医師一人ひとりが卓越した技術を持つ、専門性の高いクリニックを全国に広げていきたいと考えています。
眼形成外科の発展のために、日本各地に医療技術を教える拠点を設けなける必要があります。
そして、世界の潮流に乗りつつ日本の眼形成外科を世界最高基準に引き上げ、日本独自のものをアレンジして世界最先端に位置づけることを目標としています。

―――鹿嶋先生の夢実現のために、どういったことが必要だとお考えですか?
日本の眼形成外科の発展のため、2025年に日本眼形成美容学会を設立しました。
眼形成外科と美容医療の知識や技術を共有し、世界に出ても負けない眼形成外科医の育成すること。
そして、世界レベルの眼科美容医療モデルを構築し、今後を担うリーダーを輩出することを目指しています。
日本の眼形成外科は常に発展しており、すべての手術に顕微鏡を使ったり、眼窩減圧術で目の周りの脂肪を除去したりする手術は、まだまだ世界的に見ても珍しい日本独自の強みです。
これからも、眼形成外科の未来のために、私が先陣を切って常に走り続けます。
そうすることで、他の医師が「まだまだ勉強しなければいけない」と感じ、眼形成外科医が一丸となって高め合っていけると信じています。
▷日本眼形成美容学会公式ホームページはこちら
読者さまや若手医師のみなさんへ ~患者さまの病気を治すことに情熱を~

―――最後に、美容医療をお考えの読者さまや、若手医師のみなさんへメッセージをお願いします。
読者さまから見ると、医師はすべて同じに見えるかもしれません。しかし、それぞれに専門があり、知識や技術などのレベルが異なります。
“選択は一瞬ですが、後遺症は一生”だからこそ、初めから安全に治療を受けられるクリニックを選ぶようにしてください。
次に、若手医師のみなさんへ。これから美容医療業界は競争が激しくなります。まずは病気についてしっかり学び、自分で考えて積極的に行動できる人になりましょう。
海外に目を向けることも大切です。そして、保険診療に頼らない収益確保の方法として、専門性を磨いて自由診療を活かせる人材になってほしいと考えます。
眼形成外科業界は、常にアップデートしています。自ら学び、皆で成長できる環境を用意していますので、高みを目指す挑戦がしたい方はぜひご相談ください。
この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事
【施術の内容】眼窩減圧術
【施術期間および回数の目安】通常1回 ※状態によって異なります。
【費用】¥1,980,000 ※本施術は自由診療(保険適用外)です。医師によって異なります。
【リスク・副作用等】出血、腫脹、複視の出現または悪化、視力障害、過矯正、低矯正など