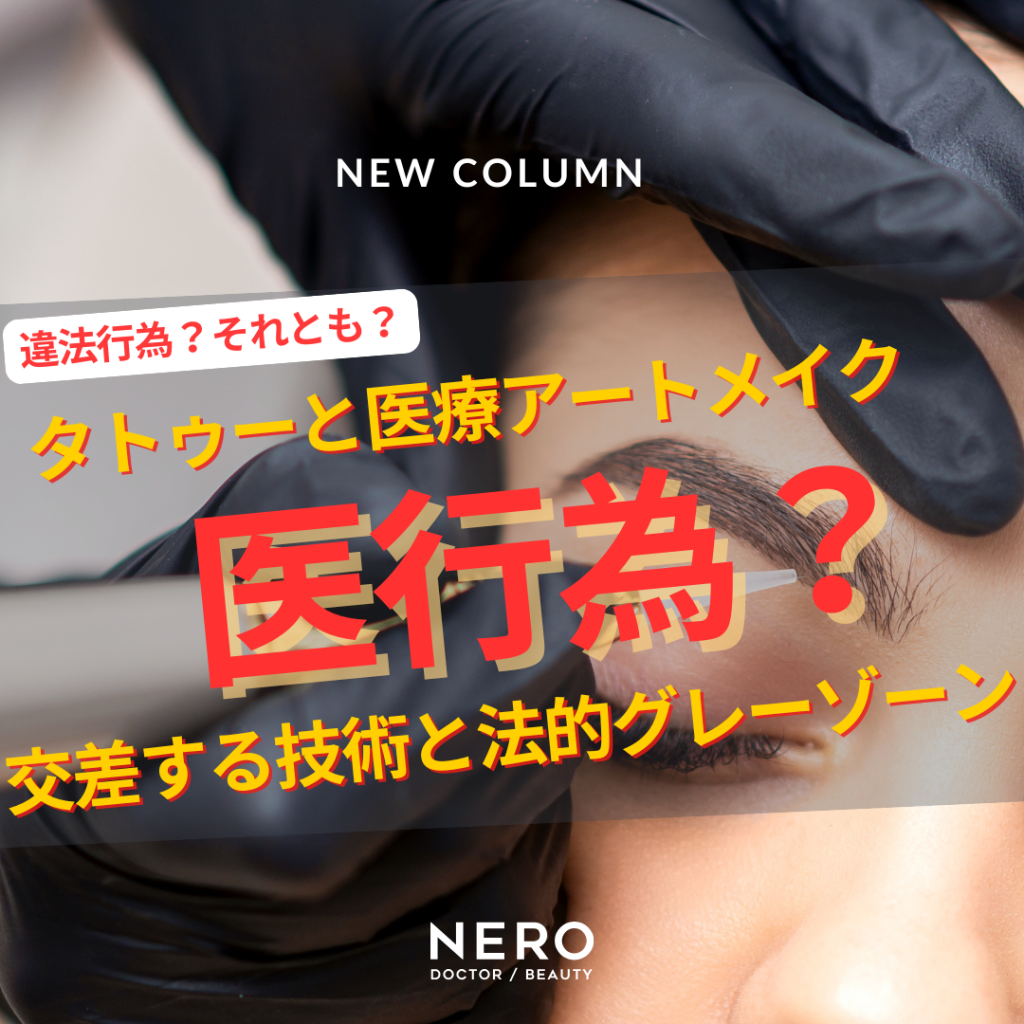
美容の現場で耳にすることが増えた「インクメイク」と「医療アートメイク」
どちらも「針で皮膚に色素を入れる」という点では同じ技術ですが、目的・施術者・法的位置づけはまったく異なります。
さらに近年は、最高裁判決が「刺青は医療行為ではない」と判断した一方で、厚労省は「アートメイクは医療行為」と通知しており、行政や現場対応に揺らぎを生む要因にもなっています。
そのため、患者や利用者にとって安心感をどう担保するかが大きな社会的課題となっています。

📌 記事をざっくりまとめると…
インクメイク=美容師資格による美容行為
医療アートメイク=医師・看護師による医療行為
技術は同じでも、目的とリスクの違いが境界線
最高裁判決と厚労省通知の食い違いでグレーゾーンが拡大
制度整理が進まなければ、安心・信頼の確保に影響
インクメイク ― 美容師が担う領域
インクメイクは、美容目的で行われる施術です。
心身ともに健康な人が「美しさの追求」を目的に選ぶケースが中心で、美容師資格を持つプロフェッショナルが担当します。
メイクやヘアと同じ延長線上に位置づけられ、医療行為とは切り離されるのが原則です。
医療アートメイク ― 医療従事者が担う領域
医療アートメイクは、失われた外見や機能の回復を目的とした医療行為です。
乳がん術後の乳輪再建や、手術痕のカモフラージュなど、医療上の必要性を伴う場合に選ばれます。
そのため、医師や看護師といった医療資格者のみが施術でき、クリニックなど医療機関で実施されます。
グレーゾーンが生まれる理由
問題は、「同じ技術」が美容にも医療にもまたがって存在することです。
-
最高裁判決 → 刺青は医療行為ではない
-
厚労省通知 → アートメイクは医療行為
この2つが併存することで、解釈が揺れる余地が残されているのが現状です。
行政対応や現場での判断に一貫性が欠け、結果的に利用者が戸惑う要因となっています。
編集長ポイント
~無資格施術の拡大と規制強化 問われるのは“安全の線引き”~
「名前を変えても医療行為は医療行為」
美容と医療の境界線が曖昧な領域では、誤った情報がすぐに拡散しやすい。
しかし、アートメイクにおいては厚労省の見解がはっきりしています。
一方で、タトゥーとの線引きは極めて難しい。
一部のタトゥーだけを取り出して「医療行為」と定義しようとする厚労省通知は、現場ではすでに機能不全に陥っています。
下部行政機関が通知を「無視せざるを得ない」状況に追い込まれていることこそ、制度の歪みの証左です。
厚労省は、現場の混乱を放置するのではなく、タトゥーとアートメイク双方を正しく整理した新たなルールを示すべき時期に来ています。
患者を守るのは“正しい情報”と“実効性ある制度”。
この二つをどう整合させるかが、いま問われています。

まとめ
-
インクメイク=美容師による美容施術
-
医療アートメイク=医師・看護師による医療施術
-
法的立場の違いがグレーゾーンを拡大
-
制度整理なくして、安心と信頼の確保は難しい
参考文献
▼以下、参考内容/
▲以上で終了▲








