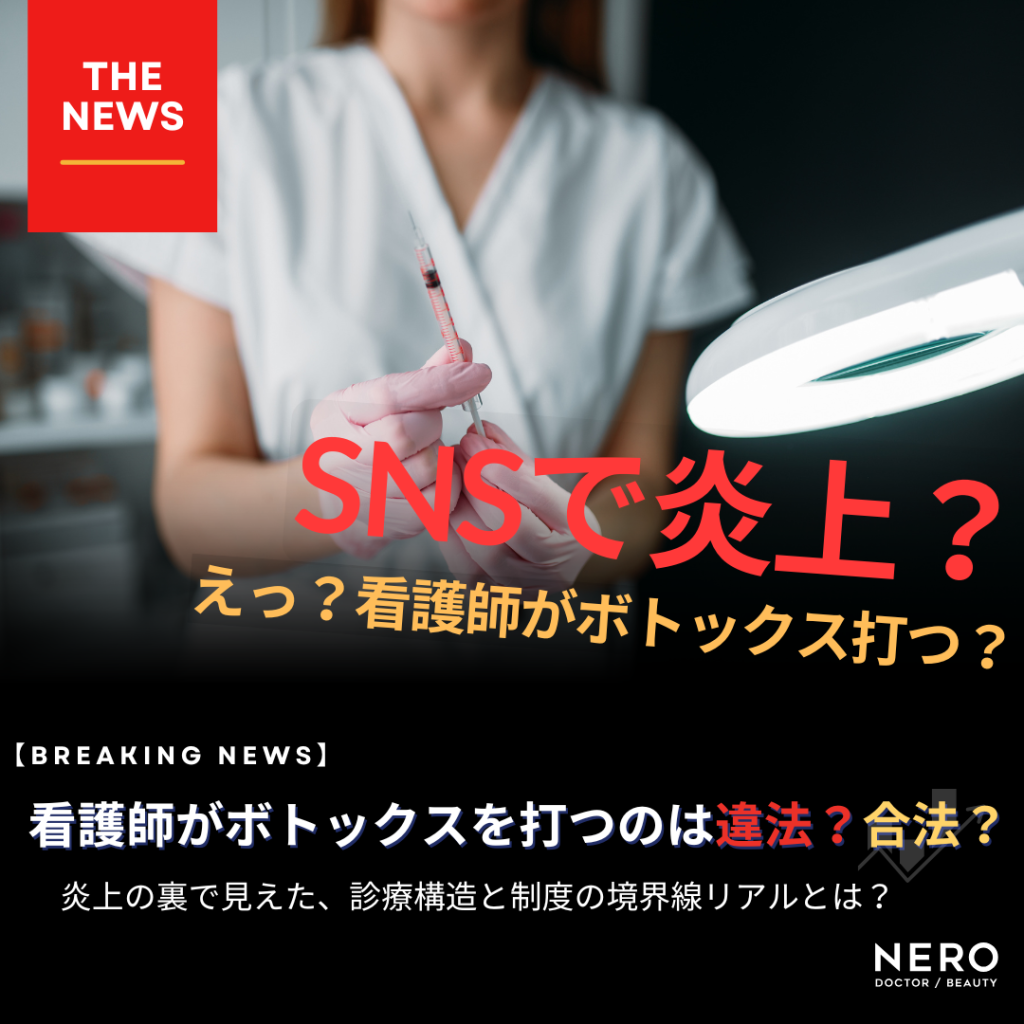
SNSで「看護師がボトックスを打っていた」という投稿が拡散し、医療界・美容業界のあいだで議論が広がっている。
「医師しか打てないのでは?」「違法ではないのか?」——そんな声が急増する一方で、
現場では“医師の指示のもとでの看護師施術”が広く行われているのも事実だ。
いま必要なのは、誰かを責めることではなく、
「制度」「現場」「社会」がどこですれ違っているのかを理解すること。
NEROは、この問題を法・現場・国際制度・心理構造の4つのレイヤーで読み解く。
INDEX
1. SNS発の誤解——「見えない構造」が炎上を生む
火種はあるSNS投稿だった。
「ナースがボトックス打ってた。医師は説明だけでいなかった。これって違法じゃないの?」
引用:X(旧Twitter)@qxgp_(2025年10月投稿)
※本引用は報道目的による一部引用であり、投稿者への批判意図はありません。
投稿の意図は「不安の共有」だったが、
コメント欄では「看護師が打つ=違法」との認識が拡散。
この“違法感”の多くは、法律上の誤解と体制の不可視性から生じている。
医師が診察しても、施術に同席していないと「監督がない」と見られがちだ。
結果として、制度上は合法でも、患者からは「責任の所在が不明」に映る。
この「正しい体制が見えない構造」こそが、SNS炎上の根源である。
2. 法律で見る「ボトックス施術の線引き」って?
■ 医師法第17条:医行為の独占
「医師でなければ、医業をなしてはならない。」
(出典:e-Gov法令データ提供システム[医師法(昭和23年法律第201号)第17条])
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
医師以外が医療行為を行えば、医師法違反となる。
違反すれば「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処される可能性がある(同法第31条)。
■ 保健師助産師看護師法第5条:看護師の業務範囲
「看護師は、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者の療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする。」
(出典:e-Gov法令データ提供システム[保健師助産師看護師法 第5条])
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
ここに定められる“診療の補助”の範囲は広く、
医師の診察・指示・監督のもとであれば、看護師が注射・点滴などを行うことが認められる。
■ 厚労省通知:医行為の定義と解釈
厚生労働省は「医師法第17条の解釈に関する通知(2009年8月28日)」で、
「医行為とは、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為」と定義している。
(出典:厚生労働省「医師法第17条・歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0828-1c.pdf)
したがって、医師の診断・指示を前提とした注射(ボトックス等)は“診療補助”に該当し得るかもしれない。
ただし監督が形式的であれば、医師法違反になる可能性もある。
3. 行政処分例に見る「違法化の境界」
これらの事例はいずれも「医師の監督が形式的だった」点が問題視された。
つまり、“看護師が打った”こと自体ではなく、医師の責任体制が見えなかったことが処分の原因になっている。
行政処分例もあったか(参考元ツイート)
・2018年/東京都:看護師が医師不在時にヒアルロン酸・ボトックス注射 → 医師法違反で医師に行政処分。
・2021年/関西圏:医師が診察のみ、注射は看護師担当 → 保健所立ち入り・業務停止処分。
引用:X(旧Twitter)@dr_nobutomi(2025年10月投稿)
※投稿内容は報道目的の一部引用です(投稿者への批判意図はありません)
合法か違法かは「施術者」ではなく、「監督体制の実態」で決まるかもしれない。
ここで問われるのは、「誰が打ったか」ではなく、「医師の監督が実質的に存在していたか」という点だ。
4. 現場のリアル:説明不足が“誤解”を生むケースも?
美容医療の現場では、医師が診断と指示を行い、
看護師がその指示に基づいて施術する「チーム医療」体制が一般的。
しかし、患者に十分な説明がないまま施術が行われると、
「医師が関わっていない」と感じられることがある。
問題は行為ではなく、体制の透明性か??
「正しい行為も、見せ方を誤れば誤解される」という構造がここにある。
5. 海外比較:米国では「教育と監督」で職能を守る
例えば米国では州によって異なるが、
看護師が特別なトレーニングを受け、医師の監督のもとであればボトックス注射を行うことが認められている。
各州の看護委員会・医療委員会が細かいガイドラインを設けており、
多くの州では以下の条件を満たすことで合法に施術可能だ。
-
有効な看護師免許を保持していること
-
美容注射(ボトックス・フィラー等)に関する専門研修を修了していること
-
医師が現場または遠隔で常時監督できる状態であること
「看護師は医師の監督下であれば、ボトックス注射を安全に行うことができる。
医師・看護師・その他の医療職が協働することで、メディカルエステティックはより安全で多様な分野へと進化している。」
——National Laser Institute(U.S.)
つまり、「教育+監督」という二層構造が、看護師の地位向上と診療連携の両立を実現している。
6. 日本の動き:診療補助の可視化へ
2025年7月、一般社団法人 日本診療補助協会が設立された。
協会は、診療補助行為の標準化・教育化・倫理化を目的とし、
「誰が・どこまで・どのように施術できるのか」を可視化する取り組みを開始している。
主な活動内容は以下の通り:
-
ボトックス注射・アートメイク・医療脱毛などの施術マニュアル策定
-
看護師を対象とした実技研修・法制度セミナーの開催
-
診療補助認定看護師制度による技能・倫理の証明
「医療従事者が不安や誤解の中で業務にあたる現状を変えるために、
診療補助に関わるすべての人が誇りを持てる社会を目指す。」
——日本診療補助協会 公式理念より
このような“制度の下支え”が、いずれは「安心して任せられるチーム医療」へと進化する可能性を秘めている。
7. 三者の視点で見る「構造的なすれ違い」とは?
| 立場 | 感情・懸念 | 実際の構造 | 今後の課題 |
|---|---|---|---|
| 患者(SNS投稿者) | 「医師がいない=不安」「説明不足」 | 法的には医師の指示下で看護師施術が可能 | 体制説明・開示の標準化 |
| クリニック側 | 「合法でも誤解される」 | チーム医療として監督・記録を実施 | 可視化と説明スクリプトの整備 |
| 社会・制度側 | 「医師法との線引きが曖昧」 | 法整備が追いついていない | 教育・監督・認定の制度化 |
この問題は「対立」ではなく「情報の非対称性」による構造的摩擦とも捉えられるかもしれない。
編集長POINT|“違法かどうか”より、“見える安心”をどう設計するか
SNS炎上は、制度の不備ではなく“安心のデザイン”の欠如から生まれる。
医療は、本来「正しい行為」よりも「正しく見える構造」で信頼される。
どれだけ法的に正しくても、患者が“関係性の断絶”を感じれば不安は消えない。
これからの美容医療に求められるのは、
技術や資格の線引きも重要だが、“信頼が可視化される体制”が求められるかもしれない
医師・看護師・患者が“同じ医療物語の登場人物”として見える社会設計こそ、
信頼の回復ではなく「信頼の再構築」への第一歩になると筆者は考える。
まとめ
-
看護師によるボトックス施術は、医師の監督下であれば合法
-
問題は「体制の透明性」と「説明責任の欠如」にある
-
行政処分は、監督不在や形骸的な指示が原因
-
アメリカでは教育+監督体制で看護師が合法的に注射可能
-
日本では診療補助協会の発足で、現場と制度の橋渡しが進み始めた
-
“違法かどうか”よりも、“どう信頼を見せるか”が次の時代の焦点
NEROでは、医療制度の誤解と現場の努力を可視化し、
美容医療が「信頼されるチーム医療」として進化する過程を追い続けます。
NEROでは美容医療に関連するニュースをキャッチ次第、投稿していきます!
編集長のコメントも記載していくので、情報をトレンドキャッチしたい人はぜひお気に入りに登録してくださいね。








