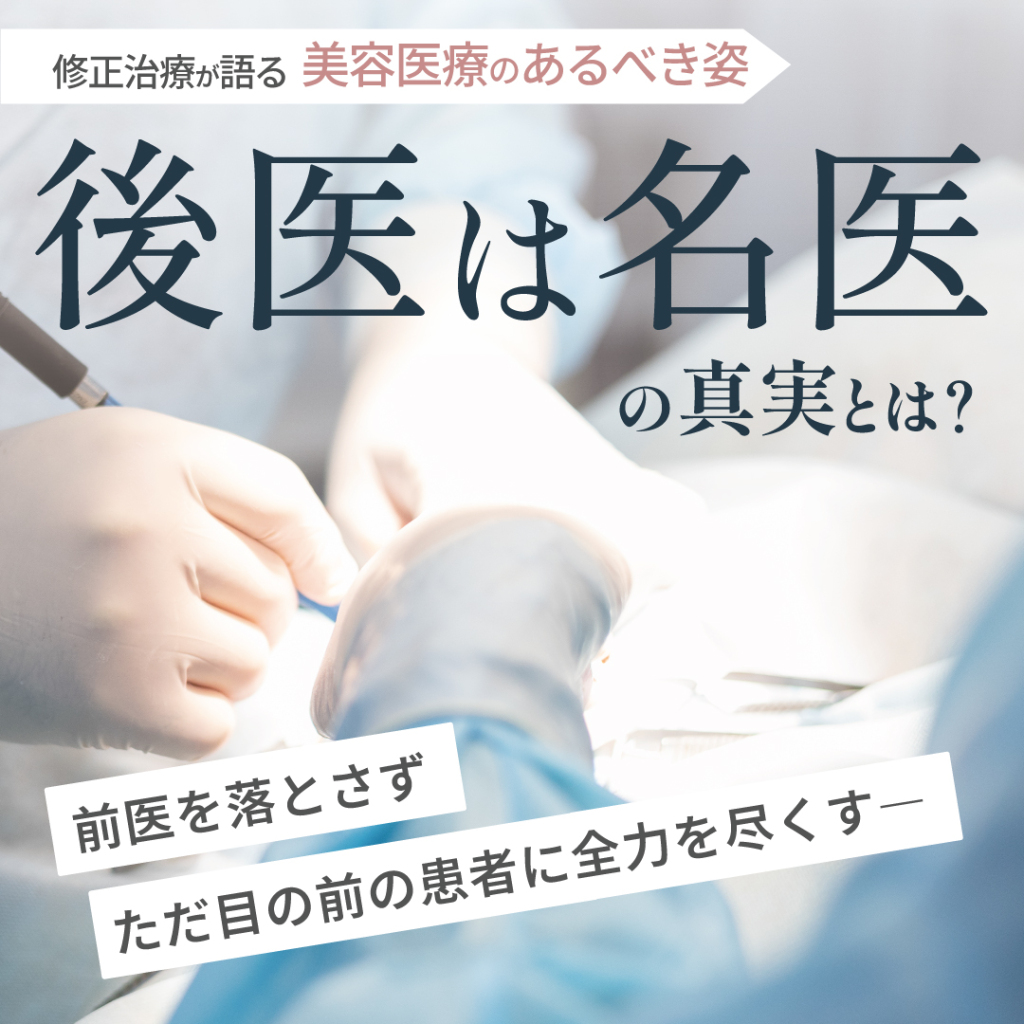
『後医は名医』とは、医療分野でよく用いられる格言です。美容医療の分野においては、修正治療や後遺症対応をした医師が後医となり、トラブルに見舞われた患者様に対応したときに用いられます。
そういった場合に、なかには前医を否定する姿勢を見せるなど患者様への配慮が欠けた医師がいることも事実。修正治療には美容医療の現場が抱える課題や、美容医療に携わる医師のモラル・倫理観不足などの問題が大きく関わっています。
そこで、今回は後遺症外来や修正治療を専門とする医師への取材を通じ、前医に対する評価や患者様側の責任、そして美容医療業界全体の向上に向けた提言を掘り下げていきます。
INDEX
1.『後医は名医』って知ってる?医療全般→美容医療に置き換えると…?

医療の分野で語られることの多い『後医は名医』という格言は、美容医療にも通じるところがあります。詳しく見ていきましょう。
格言『後医は名医』の成り立ち
医療業界で広く知られる格言『後医は名医』を知っていますか?
『後医は名医』とは、簡単に言うとあとから診察した医師は名医といわれやすいという意味であり、一方で、前医への感謝とリスペクトの意味、前医・後医共に一緒に診療に誠実に当たるべき、という医師としての心構えも込められている言葉ともいえます。
たとえば、発熱して咳もひどいと内科を受診し風邪と診断されたとします。しかしなかなか熱が下がらず再診するも、血液検査の結果ウイルス性という判断。熱が下がらず咳がひどくなったため別の病院を受診すると、肺炎という診断で入院となったというケースも珍しくないでしょう。
こういった場合、患者様ははじめにかかった医師よりも後から診断した医師の治療結果が効果が高かったと感じることは想像に難くありません。
しかし、前の医師の技量が不十分だったのかというと、必ずしもそうではありません。病気の初期段階では判断するに十分な症状や検査所見が出ていないことも多く、優秀な医師であっても正しい診断ができないことも往々にしてあります。
発症からある程度時間が経過しており、前の医師から診察を受けた経緯などの情報がある分、後から診断した医師の方が正しい診察を下しやすくなります。
前回の診断を参考にできること、そして時間の経過により症状がはっきりしてくることなどの要因により、『後医は名医』になりやすいのもうなずけます。
『後医は名医』の美容医療での使われ方
医療業界はもちろん、美容医療でも同じことが言えます。美容医療では主に、修正治療や後遺症対応を行う医師の経験から用いられることが多いでしょう。例えば以下のような事例により、修正治療や後遺症対応が必要なケースも少なくありません。
<美容医療での修正治療や後遺症対応の事由>
◆二重幅に左右差ができた
◆脂肪吸引で皮膚がくぼみ傷跡が残った
◆ヒアルロン酸注入で頬が腫れた
◆鼻の形や高さが不自然になった
美容クリニックで施術を受けたものの理想通りにならなかった、傷跡が気になる、後遺症が生じたなど、審美面や機能面に問題があった場合、修正治療や後遺症対応を受けることになります。
『後医』による修正治療が求められる理由
美容医療において、他院修正は増加傾向にあります。基本的には、前回の施術情報を保有する同じクリニックで、自分を治療した医師に修正手術を受けることが望ましいでしょう。しかしながら、他院修正を希望する患者様が多いのは、以下のような理由が考えられます。
◆期待値と現実とのギャップ
◆説明やアフターケアの不十分さ
◆美容医療の技術の進化
◆合併症の発生
◆修正治療の拒否
まず考えられるのは、思ったような仕上がりにならなかったなど、期待値と現実とのギャップ。期待値が大きいと思ったような仕上がりにならなかったときの落胆は大きく、「同じクリニックで修正してもダメかもしれない」と思う方もいるでしょう。
カウンセリング時の説明やアフターケアの不十分さなどにより不信感を抱き、別のクリニックに助けを求める患者様もいます。
また、美容医療の技術の進化により、他院修正を選ぶケースもあるかもしれません。美容医療業界は新しい技術が次々に登場しており、以前はできなかった治療もどんどん導入されています。
同じクリニックではできない治療方法を導入しているクリニックの門を叩き、より理想に近づくための修正治療を求める方もいるでしょう。
残念ながら、施術を受けたクリニックで修正治療を対応してもらえないケースもあります。技術的に対応できない場合もあれば、主治医が失敗と認めず取り合ってもらえない場合もあるでしょう。
そういったときは、ほかの医療機関と提携して橋渡しを行うのがベストな対応ですが、十分なアフターケアをしていないクリニックもあるのが現状です。かかったクリニックで対応がしてもらえず、途方に暮れる患者様も少なくありません。
2.修正治療から考える「医療のあるべき姿」

修正治療を行うということは、時間も費用も余分にかかってしまうということ。当然ながら、修正治療はないに越したことはありません。美容医療の修正治療が増えている背景から、医療のあるべき姿を考察してみましょう。
修正治療の難しさ
他院修正は、対応しているクリニックとしていないクリニックが存在します。修正治療の難易度が高いというのがその理由。一度手術をした部位は表面に傷跡があり、内部には瘢痕組織ができ硬くなっている状態です。
そのため、手術を繰り返すほどに手術の難易度は高まり、きれいな仕上がりにもなりにくい傾向にあるなど、専門的な技術が必要です。簡単な治療で生じたトラブルが簡単な治療で治るとは限らず、他院で失敗した症例の修正治療は、総じて難易度が高くなります。
さらに、美容後遺症の治療は症状の幅が広く、傷ややけどなどさまざまな知識が必要です。年齢によってもアプローチ方法が変わってくるため、治療をパターン化できないという側面もあります。
さらに、患者さまが求めるのは、マイナスの状態をゼロに戻すことに加えて、患者様がもともと目指していた状態に近づけること。さらに前医の医師を尊重しつつ、患者さまともコミュニケーションを図りながら治療を進めていく、リスクの高い治療といえるでしょう。
修正治療増加の背景
美容医療の修正治療増加の背景には、直美と呼ばれる医師が増えている点も挙げられます。
直美とは直接美容医療の略症で、保険診療を経験せずに美容医療に進む医師を指す言葉です。もちろん直美だから必ずしもスキルが劣るというわけではありませんが、保険診療などの一般診療の経験がトラブルへの対応力や多くの知識・経験に生かされる面も無視できません。
▽美容医療現場から見える変化と可能性についてはこちら
信頼関係の重要性
他院修正を希望する患者様は、不安を感じて来院されることがほとんど。患者様と信頼関係を築くことが、後医を担う医師の果たすべき役割です。
悩みや希望をきちんと把握したうえで、リスクや可能性をきちんと説明し、患者様に納得してもらうこと。納得しないまま修正治療を行い悪い結果になった場合、患者様はさらに後悔することになります。
患者様としっかりコミュニケーションを取り、治療選択をサポートすることが大切です。たとえ治療を断る場合であっても、理由を明確に示すことで、納得もしやすくなるでしょう。
また、患者様側も、受けた施術についての情報はできるだけ詳細に伝えることが大切です。美容医療も医療行為の一環であり、修正手術の際もこれまでの治療との相互作用を考えて検討する必要があります。
しかしながら、日本の美容医療では他院とのカルテの共有はできず、前院で起きたことをきちんと把握するためには状況に加え患者様の言葉で伝える必要があります。過去に受けた施術や現在進行中の治療、診断結果などをきちんと申告することが、適切な施術選択につながります。
3.前医批判ではなく、前医で起きている事象を集約し、業界の進化へ取り組むしかない

美容医療業界を良い方向に進めるためには、修正治療の際に前医を落として積極的に『後医は名医』にするのではなく、前医で起きた事象を集約し最善を尽くすことが大事なのではないかというのがNERO編集部の考え。修正治療の在り方から、今後の美容医療業界の未来像を深掘りしてみましょう。
前医否定はリスクを伴う行為
修正治療の際、前医の施術や対応が悪い場合において、後医は前医を否定できる立場にあります。
しかし、美容施術を受けた事実を否定したり、執刀した医師を否定したりすることは、大きなリスクを伴う行為です。美容医療業界は拡大しているものの、一歩踏み入れることに漠然とした不安を抱えている患者様も少なくありません。
そのうえで患者様は美容医療を受けることを決め、一度は前医を信頼して施術を受けています。
修正治療を受けなければならなくなったことに対しても精神的や経済的な負担がかかっている状態で、後医からの否定はさらなる精神的な負担でしょう。
そのような状態では、たとえ修正治療がうまくいったとしても、美容医療に対して不信感を抱く可能性もあります。ひいては美容医療全体への印象が悪くなり、さまざまな悪影響につながることも懸念されます。
前医を落として自分の評判を上げるというスタンスは、前医だけでなく患者様への配慮が欠けた行為と言えるでしょう。
必要なのは、前医や後医という立場にとらわれるのではない、目の前の患者様の想いを叶えるために全力を尽くすのみというスタンス。患者様のこれまでや前医の治療を否定するのではなく、すべて受け止めたうえでこれから良くするための方法を検討していく必要があります。
修正治療が示す未来像
今後重要となってくるのは、医師によるリスク管理の徹底と、患者様側の健康リテラシーの向上です。
美容医療業界のさらなる発展のため、医師が学び合う場も次々と登場しています。
たとえば、最新の美容外科技術や知識を共有し合う「Cutting Edge(カッティングエッジ)」や合同勉強会「Creation Lab(クリエイションラボ)」、成長したいと希望する医師や看護師がフラットに学ぶ「あきラボ」もその1つ。
2025年1月には「あきラボ」で美容外科後遺症診療医である朝日 林太郎(あさひ りんたろう)先生が登壇し、美容後遺症や解決策について議論しました。
美容医療も医療の1つであり、安全な美容医療を提供していくことは目下の課題です。美容医療に携わる医師が修正治療や後遺症対応について積極的に理解を広げていくことが、美容医療の質の向上につながります。
▽朝日 林太郎先生の登壇した「あきラボ」についてはこちら
▽朝日 林太郎先生のインタビュー記事はこちら
施術を受ける側がリスクや副作用、術後のメンテナンスなどの知識を十分に備えていないことがトラブルの一因になっているケースもあります。美容医療にはメリットもありますが、同時にリスクや副作用の可能性も潜んでいます。
クリニック側がデメリットをきちんと伝えることも大事ですが、同時に患者様側も自分を守るためにきちんと知識をつけておく必要もあるでしょう。
どんな治療も絶対はないという前提のもと、万が一のときにアフターケアまでしっかり対応してくれる医師やクリニックを選ぶという視点も大切です。
まとめ
美容医療の広がりの影でトラブルに悩む方が増えているのも現状です。美容医療を持続的に発展させていくには、良い面ばかりにフォーカスするのではなく、トラブルも起こりうることをきちんと周知していく必要があるでしょう。
前医を落として『後医は名医』にするのではなく、目の患者様に全力を尽くすことが、美容医療に携わる医師に求められるモラル。安心して施術を受けてもらえる場所が増えることが、NERO編集部の願いです。
この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事
| ・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。 ・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。 ・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。 |














