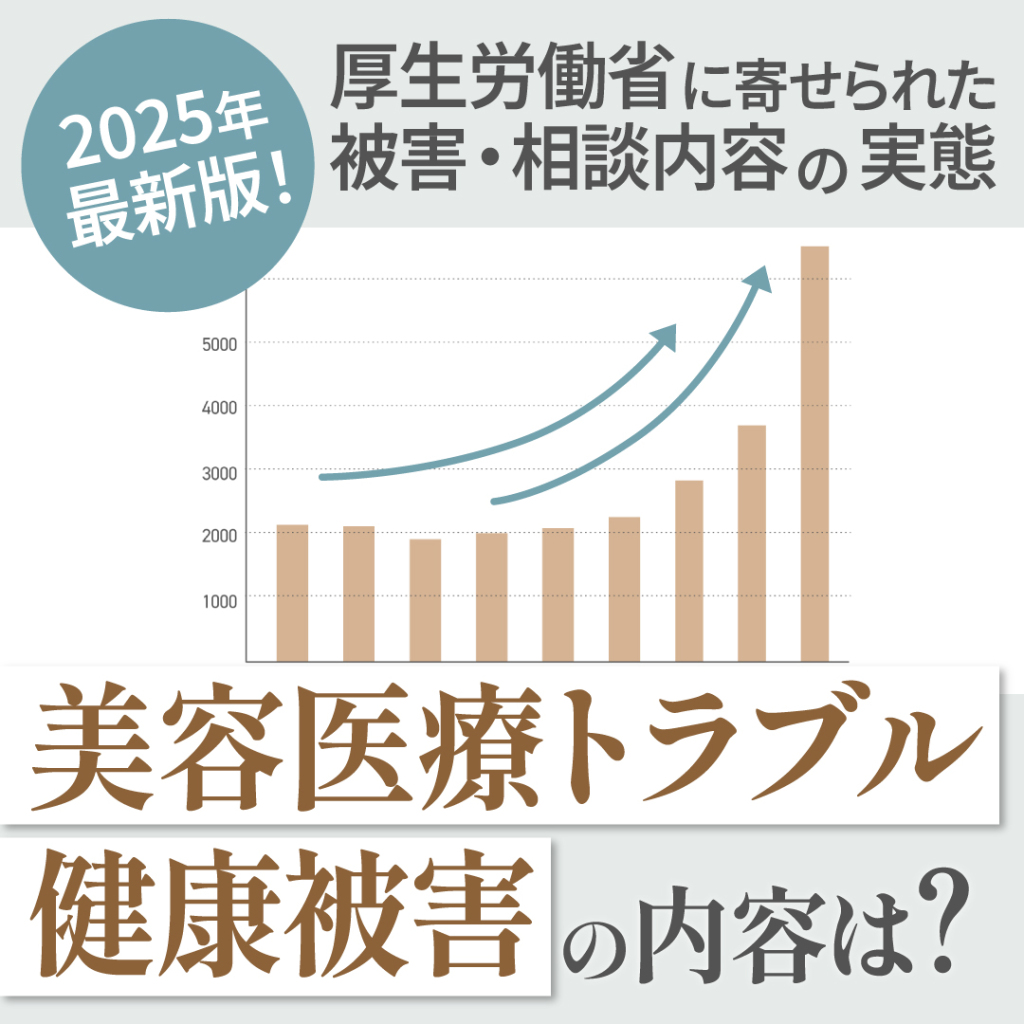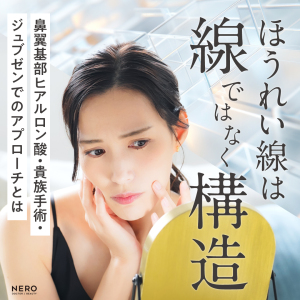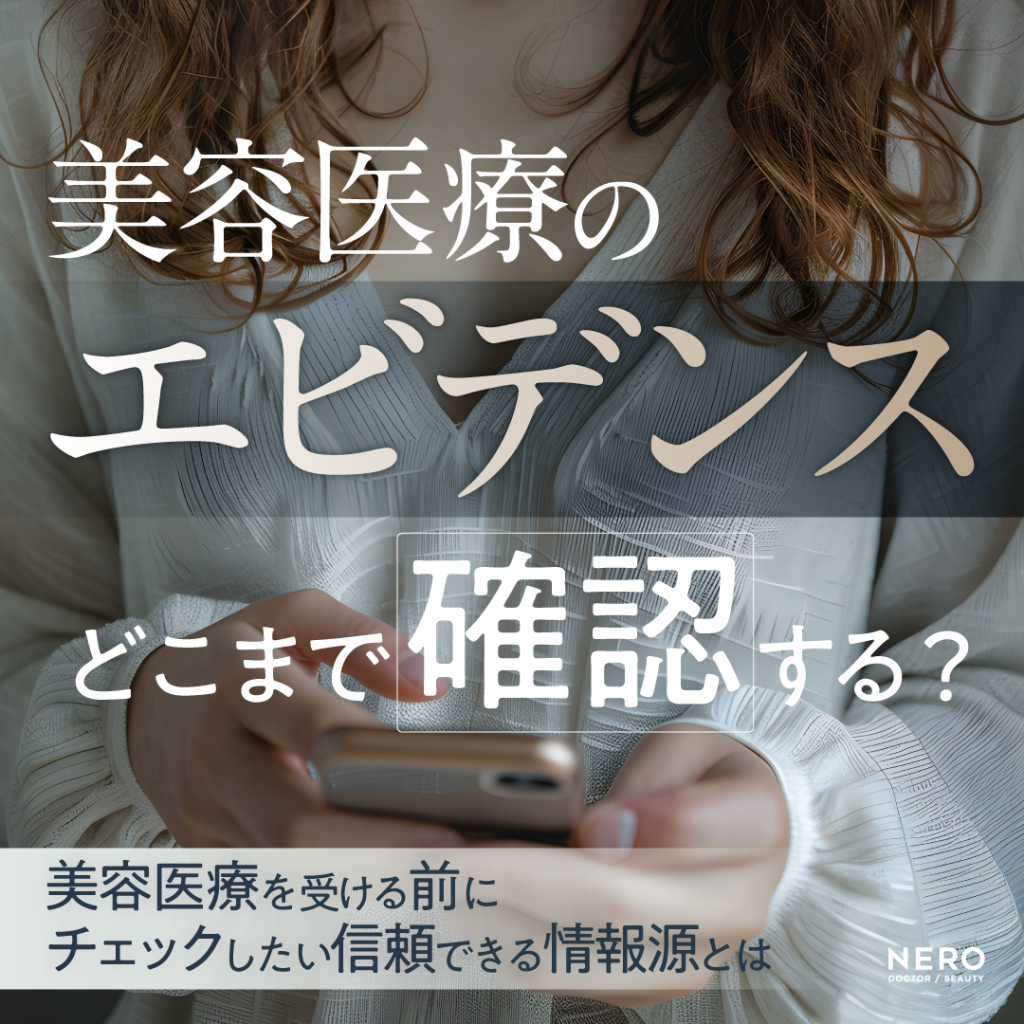
美容クリニックでのカウンセリングの際、医師から「エビデンスに基づいた治療法です」という言葉を聞いたり、ホームページやSNSで「エビデンスに基づいた安全かつ効果的な治療を提供します」といった言葉を目にしたりすることがあります。
エビデンス(evidence)とは、証拠や根拠を表す言葉。
医療・美容医療分野では、治療の効果や安全性を裏づける“科学的根拠”を表します。
また、一口にエビデンスといっても情報源によって、効果や安全性への信頼度が変わるんです。
今回は安心して美容医療を受けるために知っておきたい情報の受け取り方、日本と海外のエビデンス文化の違いについて深掘りしましょう。
日本 vs. 海外—エビデンス文化の違いと治療承認プロセスの壁
 新しい治療が承認され患者に提供されるまでには、国の機関が安全性や有効性を審査するプロセスが存在します。
新しい治療が承認され患者に提供されるまでには、国の機関が安全性や有効性を審査するプロセスが存在します。
日本と海外(主にアメリカやヨーロッパ)では、このプロセスの重視する点やスピード感に違いがあります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
■海外(アメリカ・ヨーロッパ)における新治療承認プロセス
アメリカ食品医薬品局(FDA) には新治療や新薬剤の承認において「迅速承認」という制度があり、最低限の臨床データに基づいて患者に新治療や新薬が早期に提供されるケースがあります。
適用の条件は、深刻な疾患に対して既存の治療法よりも新治療のほうに改善の見込みがあると判断された場合。
迅速承認の適用に向けてFDAが企業に協力・指導を行うケースもあり、新たな治療法の開発を促進し、迅速に患者に届けるための承認プロセスが確立されているのです。
また、ヨーロッパの欧州医薬品庁(EMA) でも新治療や新薬剤に対し、リスクよりも患者に対するベネフィットが上回ると判断された場合に早期承認される「条件付き承認」というシステムがあります。
いずれの承認プロセスにおいても承認後に一定期間、追加で臨床試験データの提出が求められます。
アメリカとヨーロッパでは、こうしたトライ&エラーをサポートする制度によって、技術が発展してきた背景があります。
■日本における新治療承認プロセス
一方、日本では厚生労働省が新治療の承認までのプロセスを厳格に管理。
審査から承認までは長期に渡り、すでに海外では効果が証明され承認済みの治療・薬剤であっても、日本の医療現場で用いるためには厚生労働省の一連の審査をクリアすることが条件です。
アメリカとヨーロッパの「深刻な疾患に対してはある程度のリスクが許容される」という姿勢に対し、日本はまず安全性を重視し慎重な審査のもと承認することが基本となっています。
しかし近年日本でも、先駆的な治療法に対して早期承認を行う制度「先駆け審査指定制度 」「先駆的医薬品指定制度 」を導入するなど、少しずつ変わりつつある状況です。
また、美容医療は保険適用されない自由診療であるため、保険診療と比べて法律に基づく指導や監査が限定されている分、自由診療が発展しやすい状況にあります。
【PICK UPコラム】FDA・CEマーク・PMDAの違いって?美容医療に用いられる機器や薬剤などの製品は、それぞれの国の規制をクリアし認可を受けてから患者に提供されます。 アメリカ・ヨーロッパ・日本それぞれの規制機関の承認基準や特徴についてまとめました。 ●FDA /アメリカFDA(Food and Drug Administration)はアメリカ食品医薬品局のことを指し、日本の厚生労働省に相当する政府機関です。 美容医療分野 では、レーザー・ハイフ・フィラーなどの医療機器、ボトックス・トラネキサム酸・トレチノインなどの医薬品、スキンケア製品をはじめとする化粧品の承認審査を実施。 長期に渡る厳格な臨床試験で得られたデータをもとに、品質や有効性を評価します。 FDAが定める規制基準をクリアした適正な製品はFDA認証が与えられ、販売が許可されます。 FDAは世界でも新技術の導入が早く、世界初の承認を受ける機器や薬剤が多くあることが特徴です。 ●CEマーク /ヨーロッパ
CEマークは、EU(欧州連合)の安全性や品質、環境負荷に関する規制基準をクリアし、流通が許可された製品に貼付されるマーク。 美容医療分野 では、レーザー・ハイフ・IPLなどの医療機器、ボトックス・ヒアルロン酸フィラー・幹細胞などに関連する再生医療製品といった医薬品、 スキンケア製品をはじめとする化粧品が対象です。 特徴的なのは、治療は自然な仕上がり・注入薬剤は控えめな使用が重視される点。 CEマークはEU市場だけでなく、日本をはじめとするアジアなどで国際的に高い安全性の証として認識されています。 ●PMDA /日本PMDAとは、日本の厚生労働省が管轄する「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」のことで、医薬品や医療機器の承認審査・安全対策・健康被害救済を行う機関です。 美容医療においては、機器や薬剤の安全性や有効性が最新の科学に基づいて証明できるか、データを重視して評価。 他国に比べて規制基準が厳格であるため、国際製品の導入は海外に比べてやや時間がかかり、海外で用いられている機器や治療でも日本では承認されていないケースが多くみられます。 これまでに承認した美容目的の薬剤や機器は、アラガン社製ボトックスをはじめ、ジュビダームなどのヒアルロン酸製剤や医療脱毛機器など。 |
■ 「論文がある=安全」は誤解?出版と治療の関係
論文とは治療の研究成果や知見をまとめた文書で、その分野の複数の専門家の査定を経て、学術誌に掲載されたものを指します。
専門家による査定システムのことを「査読」といい、査読をクリアして学術誌に論文が掲載されることは、客観的に見ても一定の信頼性のある治療であることの証明となります。
しかし、「論文掲載の実績がある治療=すべて安全」とは言い切れないためご注意を!
査読なしの学術誌に掲載された論文である場合、信頼性が低いケースも。
また、査読付きと称する学術誌の中には、出版料さえ支払えば論文を掲載できるものも存在します。
また、論文はあくまでも研究や実験上の成果をまとめたもの。
臨床現場で実際に患者に対して治療を行った実績とは別であるため、あくまでエビデンス(科学的根拠)の一部が証明されたものと捉えると良いでしょう。
Xなどで拡散される美容医療情報の中には、「論文に基づいている治療だから、高い効果が見込める」といったフレーズがみられます。
しかし、 その治療が“自身の症状や悩みに適応するかどうか”は別問題。
論文掲載実績だけでは、患者一人ひとりに対する治療効果の信頼性にはつながりにくいのです。
エビデンスの信頼度マトリクス—美容医療における情報の取捨選択
 美容医療の新たな治療や機器、薬剤について知りたいとき、ネット検索すると出てくるのが論文や学会発表、医師のSNS投稿やメーカー発表データ。
美容医療の新たな治療や機器、薬剤について知りたいとき、ネット検索すると出てくるのが論文や学会発表、医師のSNS投稿やメーカー発表データ。
どの情報源を信用するべきか迷うこともあるでしょう。
それぞれの情報源は、確認したい内容や目的によって取捨選択するのがカギ。
本項では、論文・学会発表・医師のSNS投稿・メーカー発表データの信頼度とともに、どのように使い分けるべきかをまとめました。
| 情報源 | 特徴 | 活用のポイント |
| 論文(査読付き) 信頼性★★★★★ |
厳格な審査を経たエビデンスがあり再現性がある。ただし数年前のデータであったり、実際の臨床とは乖離していたりすることも。 | 治療の科学的根拠を確認したいとき、安全性や効果の裏付けが知りたいときにチェック。 |
| 学会発表 信頼性★★★★☆ |
研究途中の段階でも発表されるためエビデンスが少ない。
最新技術やトレンドを把握できる。 |
論文になる前の注目の研究成果をチェック。今後、主流になるかもしれない新たな治療法を知る。 |
| 医師のSNS発信 信頼性★★☆☆☆ |
臨床現場のリアルな声。
医師の主観的な意見や症例紹介が多い。 |
治療中の雰囲気や効果の実感をチェック。ただし“誰が言っているか”は重視するべき。 |
| メーカー発表の データ 信頼性★★☆☆☆ |
自社に有利なデータが多い可能性があるが、最新技術の動向はつかめる。 | 新たな機器や薬剤の動向やトレンドの把握に。他の情報源も併せて確認するのがおすすめ。 |
情報源の使い分け方のイメージは以下のとおりです。
- 新しい治療法の存在を知りたい ⇒ 学会発表・医師のSNS
- その治療の科学的な効果と安全性を検証したい ⇒ 論文(査読付き)
- 実際の症例写真やダウンタイム、現場の声を知りたい ⇒ 医師のSNS
- どんな技術を使っているのか確認したい ⇒ メーカー発表のデータ
このように複数の情報源を組み合わせることで、治療について多角的に網羅できます。
効果と安全性について信頼性の高いデータが欲しい場合は、専門家の査読をクリアした論文が最適。
実際の施術後の変化や治療の痛み、医師ごとの施術のこだわりなど、患者目線の情報が欲しい場合はXやInstagramなどの医師のSNS発信をチェックすると良いでしょう。ただし、内容には個人差があります。
また、「自クリニックで取り扱っているものを優位にするようなポジショントーク」もよく見受けれらるのが現状です。そのため1人の医師の声を鵜呑みにしすぎず、複数の医師の投稿を参考にしてみてくださいね。
また、どんなに信頼している医師であっても、新しい薬剤などに対する姿勢などは異なったりすることもあります。あくまでも「長期エビデンス」なのか「情報元はどこなのか」など意識するのが大切でしょう。
■新治療の導入基準—実際の症例数はどれくらい必要か?
新しい治療や技術が続々と登場する美容医療業界。
しかし、どんなに話題の治療であっても、医師は安易に飛びつくことはなく「患者にとって安全かつ高い効果がもたらされるか」「自院の信頼性を保てるか」などを加味して慎重に導入するかどうかを判断します。
治療の開発者やメーカーがどのくらいの症例数を提示しているかも、導入の判断材料になりますが「〇例あれば導入できる」という明確な基準は設けられていないようです。
実態としては症例数以上に、信頼する他院の医師との交流の中で「治療の再現性が高い(実際に患者に治療を適用しても臨床試験と同様の効果を得られ、信頼性が高い)」という確証を得てから導入を検討する医師が多くみられます。
そして、自ら治療を受けたりトレーニングや見学をしたりする中で、実際に症例を確認し「再現できる」と判断することが導入のポイントとなるようです。
■新治療の導入には「フォロー期間」の長さが重要?
また、新治療導入の基準は症例数だけではなく、「どのくらいの期間、効果が継続しているか」を示す経過観察データも影響します。
たとえ施術後の短期間は効果がみられたとしても、「数ヶ月後にトラブルが発生した」というケースもあるためです。
症例の数と質、そして経過観察データをとる「フォロー期間」の長さが導入判断の重要なポイントとなっています。
■日本と海外での治療の広まり方の違い
ご紹介してきたように、日本は承認プロセスが長く安全性重視。
新しい治療法が登場しても「慎重に広まる」のが一般的です。
自由診療が中心となる美容医療では、「患者により良い選択肢を用意したい」と、先進的な治療の導入に前向きな医師も多くいます。
しかし、新治療によってトラブルが起こってはクリニックの信頼性が揺らぎかねません。
そのため「科学的な根拠を持った治療の効果と安全性」を自身の目で確かめるまでは “様子見”のスタンスをとることが多いでしょう。
一方、アメリカやヨーロッパは、医療機器や薬剤の承認が比較的早く行われるため、新治療が市場に出回るスピードも早く、それに伴いエビデンスが蓄積するペースも早まります。
その結果、新しい治療がすぐに広まるという流れが生まれやすいのです。
なお、日本ではSNS上で医師や美容系インフルエンサーが施術中の様子や経過を投稿するのが一般的になっており、それを見たフォロワーが「自分も受けてみたい!」と予約する流れが確立されつつあります。
新治療の承認から導入判断までは「じっくり慎重」の日本ですが、一般層への認知は一気に広がる傾向にあるでしょう。
実際の臨床と論文の違い
 医療の理論上の有効性や安全性を証明する「論文(エビデンス)」ですが、論文での検証結果がそのまま実際の臨床現場で再現されるわけではありません。
医療の理論上の有効性や安全性を証明する「論文(エビデンス)」ですが、論文での検証結果がそのまま実際の臨床現場で再現されるわけではありません。
例えば「論文でこの成分は肌に良いとされているけれど、実際には刺激が強くて肌荒れしてしまった」「高い効果を発揮するはずの機器だけど、ドクターの技術によって結果に差がある」といったことは、美容医療でよく耳にするもの。
ここからは、論文と臨床のズレについて3つチェックしていきましょう。
〈論文(エビデンス)と臨床(リアルな現場)のズレって?〉
- 治療の検証時の条件
論文での治療効果の検証は、対象者の年齢や肌質、生活習慣などが限定的であることが特徴。
ある程度コントロールされた好条件のもと検証を行うため、良い結果が出やすいでしょう。
しかし、実際の臨床現場での患者さんの年齢・肌質・生活習慣は千差万別で、さらに「痛みに弱い」「過去に肌トラブルがあった」など、一人ひとり事情を抱えています。
患者によっては向いていないなど、論文の検証結果の通りにはいかないことが前提です。 - 効果あり/なしの評価の仕方
論文では「肌の水分量が〇%増加した」というように、その治療や機器によってどのくらい治療部位が良くなったかを“数値”で評価します。
対して臨床現場では、患者やスタッフの「治療後になんとなくハリを感じた」「若々しく見られるようになった」という感覚的な評価が多いことから、差が生じやすいのです。 - 施術者のスキル
論文を書くための検証を行う施術者は、研究スキルが高く安定していることが多いのに対し、臨床現場の施術者(医師)のスキルはさまざま。
同じ治療や機器であっても、医師の経験値や機器の設定に関する知識などによって、効果の出方にバラつきがあります。
論文(エビデンス)とは、「条件がそろえば、理論上このくらい効きますよ」というモデルケースを示すもの。
新治療についての情報の“土台”である安全性・メカニズム・有効性を知りたいときに活用すると良いでしょう。
加えて、実際に治療を受けた人の感想や経過、信頼できる医師の経験談といった臨床現場の感覚的な評価もチェックすることで、より安心して美容医療を選択できるようになるはずです。
まとめ
次々と登場する新しい美容医療の治療や機器ですが、「エビデンス(科学的根拠)」を確認することは美容医療を安心して受けるための第一歩です。
論文や学会発表は効果や安全性を数値で示す信頼度の高い情報源ですが、実際の臨床現場では患者さんの肌質や生活習慣、医師の技術によって結果に差が出ることも……。
医師の発信やSNSの声もある程度参考にしながら、ポジショントークとポジショントークのぶつかり合いなどに惑わされず、複数の情報を組み合わせて、治療を選択することを意識してみてください。
この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事
| ・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。 ・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。 ・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。 |