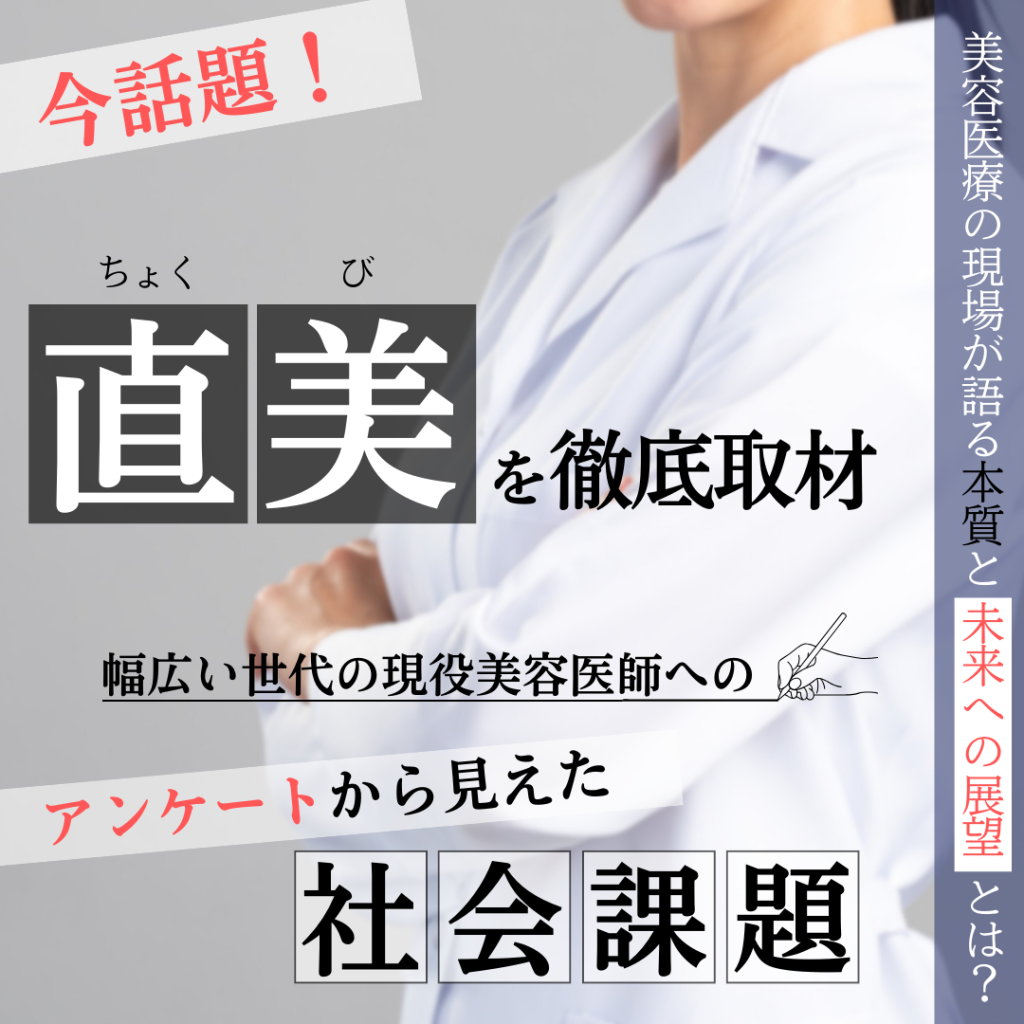近年、初期研修後に他の科目での経験を積むことなく美容外科の道へそのまま進む若手医師が増えています 。
こうしたキャリア選択は“直美(ちょくび)”と呼ばれ、現役医師からは問題視する声も少なくありません。
本記事では、医療業界を騒がしている“直美”の実態について解説。
今後の医療業界への影響や、医療トラブル増加への懸念などについても、詳しくお伝えします。
今、医療業界で増えつつある“直美”とは
直美(ちょくび)とは、「直接美容医療」の略称で、保険診療の経験なく自由診療である美容医療へ進む医師を指す言葉です。
日本では、医師国家試験に合格し、2年間の初期臨床研修を修了すれば、美容医療の分野にすぐに進むことができます。
まずは、美容医療業界の現状と”直美”の実態から見ていきましょう。
■世界的に需要が高まる美容医療
さまざまな医療分野の中でも、美容医療は年々勢いを増している1つです。
美容医療の施術数は、2020年にコロナ禍で一時減少するも、2021年からは年々大きく増加。
とくにボトックスやヒアルロン酸、ケミカルピーリングなど非外科的手法は、急増傾向にあります。
美容医療市場の拡大とともに増えているのが、美容外科医を志す医師です。
厚生労働省が公開した「医師・歯科医師・薬剤師統計」によれば、美容外科医(主たる診療科別)は、2012年から2022年の10年間で約3倍に増加。
また、2012年には、美容医療に携わる医師のうち20歳代・30歳代の若い医師が占める割合が約3割であったのに対し、2022年には5割以上が30歳代以下と推移しています。
このように若い美容外科医が増加している背景には、世界的な美容医療への需要拡大が挙げられるでしょう。
また、勢いのある分野で医師としてのスタートを切りたいと野心を抱く医学生も増えているのかもしれません。
■”直美”とは何か?美容医療に急進する若手医師の現状
一方で、問題視されているのが若手医師の“直美”と呼ばれる現象。
”直美”とは、2年の初期臨床研修を修了した新人医師が、他の診療科を経ずに美容クリニックへ直接就職することをいいます。
日本美容外科学会(JSAPS)理事長を務める武田啓氏(北里大学医学部形成外科・美容外科学教授)は、年間200名ほどの医師が”直美”を選択している可能性があると指摘。
また、2023年12月に日本医学会連合が公表した「専門医等人材育成に関わる要望書」 の中には次のような記述があります。
(前略)医学部卒業生や臨床研修医が十分な臨床的修練を経ずに保険診療以外の領域への大量流出(確定的な数値ではありませんが、2023年度の関係諸機関の調査で、美容領域で医学部 2 つ分に相当するような多数の新規の医師採用がありました。)に繋がる危険をはらむこと、(中略)から、これらの危険を回避する対策を講ずる必要があります。
この「医学部2つ分」という表現には、多くの医師が衝撃を受けたことでしょう。
それほど、医師を目指すなら長い年月をかけて高い技術と豊富な知識を得なければならない、というのが多くの現役医師たちの共通認識でした。
なぜなら、医師として就職するまでには、次のようなステップを踏むのが一般的とされてきたからです。
- 医学部へ入学(6年間)
- 医学部を卒業し、医師国家試験に合格(医師免許を取得)
- 初期臨床研修(2年間)を修了
- 眼科や外科など19科目から専攻科を選択し、3~5年間の後期研修を修了
- 専門医資格を取得
- 医院やクリニックへ就職
ただし、専門医資格は必ずしも必要ではありません。
法律上は、医師免許を取得し、初期臨床研修を修了できていれば、医師として診療を行うことができます。
つまり、“直美”も法に触れるわけではなく、医師のキャリア選択としては問題ないといえるでしょう。
しかし、2024年7月、医療メディア『Medical Tribune』 が現役医師602人を対象に”直美”に関するアンケートを行ったところ、現役医師たちの約半数が”直美”を認知しており、否定的な意見が半数以上という結果に。
その理由については、後ほど詳しくご紹介しましょう。
■なぜ“直美”現象が増加?医師たちの選択の理由とは
『Medical Tribune』による同アンケート では、”直美”が増えている理由についても医師たちに質問 。
最も多かった回答は「報酬面での魅力」となり、全体の約7割の票を集めていました。
医師といえば高収入なイメージが強いですが、その中でも美容医療は高い報酬が得られる印象があるようです。
その次に多かったのが、「就労環境における高待遇」。
多くの医師たちが、他診療科での厳しい労働環境の反動から “直美”が増えている、と考えているのでしょう。
日本美容外科学会(JSAPS)理事長・武田啓氏も、過去のインタビューの中で 他診療科の厳しい労働環境を挙げ、その“回避行動”として美容外科医を選択する若手医師が増えている、と語っています。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査 (2018年)」によると、美容外科・美容皮膚科の医師平均年収は群を抜いて高額に。
同じ20代の若手医師でも、2倍以上の年収差があるといわれています。
また、当直やオンコールなどもなく、診療時間内の外来治療のみのため、医師にとっては理想的な労働環境なのかもしれません。
また、「美容への意識の高まり」や「社会的需要の増加」という回答も多くありました。
若手を中心に美容医療への注目が高まっていることは、他分野の医師も感じているようです。
美容医療への需要が増えている背景には、医師に対して新たな役割が求められるようになった、という事実もあります。
その役割とは、医療によって命を救ったりケガを治したりするだけでなく、患者の自己肯定感や生活の質を高めたりすること。
そのためには、病気やケガではない患者に対して手術をするケースもあるでしょう。
”直美”増加の裏には、医師としての在り方を以前よりも自由に選べるようになったというのもあるかもしれません。
▽NERO独自アンケート調査!美容医療業界で活躍する医師らの「直美」に対する想いについてまとめた記事はこちらから
“直美”というキャリア選択がもたらす影響と課題
 ”直美”には、次のような課題があるとされています。
”直美”には、次のような課題があるとされています。
■未熟なスキルによる医療トラブルも…専門医資格を取得しないリスク
第一に挙げられるのは、医師としてのスキルや経験不足です。
2年の初期臨床研修の後、すぐに美容クリニックへ就職するとなれば、後期試験を修了し、専門医資格を取得した医師とスキル差が生じてしまうのは当然といえるでしょう。
そのため、このまま”直美”の医師が増えれば、美容医療業界の安全性や施術の質が低下し、医療トラブルのリスクが高まるのではと懸念されています。
美容医療であっても、他診療科と同様、患者の体へ何らかの侵襲を加えることに変わりありません。
ピーリングやヒアルロン酸注入のような非外科的施術であっても、医療知識は必要不可欠です。
もし麻酔を使う場合には、万が一のトラブルに備えて救急対応もできなければならないでしょう。
それらすべてを2年の初期臨床研修で身につけることは、かなり難しいといわざるを得ません。
実際に、前出の『Medical Tribune』が現役医師を対象に行ったアンケート では、”直美”の問題点として「修練不足の美容外科医の増加」が最も多い結果に。
回答した医師たちからは、”直美”の医師に対して次のような厳しい意見もありました。
- 一般的な医療知識や技術が欠如した医師になる
- 美容医療を甘く考えている
- 技術の低い医師に治療してもらう患者さんが不幸
他診療科と比べてビジネス色が強くなりやすい美容医療では、利益追求を第一の目的とせず、患者に寄り添った施術を行うことが大切。
こうした医師としての倫理観や志も、”直美”というキャリア選択ではなかなか身につかないのでは、といわれています。
共立美容外科理事長の久次米秋人氏も過去のインタビューの中で、「医師としてのモラル、患者さんの気持ち、辛さを理解するマインドなど、臨床に携わるための最低限の素養」を身につけるために、他診療科での3年程度の臨床経験は必要である、と語っています。
■地方や診療科での医師不足…医師体制への影響
“直美”という選択肢ができたことで、若手医師のキャリア選択の幅が広がったという見方もありますが、一方で今後の医療体制へ影響を与えるのでは、と懸念されています。
・ 地域医療の崩壊リスクが高まる
近年深刻化する地域医療の医師不足。
今では地方だけにとどまらず、首都圏でも医師が足りていない地域が出てきています。
こうした事態に拍車をかけているのが、昨今の”直美”問題。
美容クリニックは都市部に多くあることから、”直美”によって美容外科医が増えるとますます地域格差が大きくなるのでは、と問題視されているのです。
・診療科によって医師数の偏りが進む
“直美”のルートで美容医療の道へと進む若手医師が増加するということは、その分、他の診療科を選ぶ医師が少なくなるということ。
とくに厳しい労働環境を強いられるような現場では、医師数が減ることでますます過重労働を強いられるという悪循環もあるようです。
厚生労働省が公開した「医師・歯科医師・薬剤師統計(2022年度) 」によれば、前年比で医師数がもっとも増えたのは美容外科となった一方、気管食道外科・小児外科・外科・心療内科・耳鼻咽喉科などが減少しているという結果に。
診療科によって、医師数の増減に偏りが出ていることが分かります。
今後の医療体制は?”直美”への規制強化も
今後、医療の現場ではますます医師数の偏りが顕在化してくるとともに、”直美”という選択肢も常態化してくるかもしれません。
政府や医療業界では、どのような対策が取られているのでしょうか。
■診療科ごとの収入格差や厳しい労働環境の改善
“直美”を選ぶ若手医師が増えている理由は、一言でいえば「年収が高くて働きやすい環境」だから。
裏をかえせば、医師全体の労働環境や低収入を改善できれば、地域医療での医師不足や他診療科との医師数差の一番の解決策となるでしょう。
厚生労働省ではこうした地域や診療科ごとの医師偏在問題について対策を講じるため、医師偏在対策推進本部を設立。
また、医師の労働環境改善を目的として、2024年4月からは「医師の働き方改革」も推進されています。
■美容医療の規制強化
現状、大学病院では美容外科を学ぶ機会はほぼなく、”直美”の医師の技術や知識習得は就職したクリニックに委ねられているといいます。
しかし、多くのクリニックでは教育システムが十分に備わっていないことが多く、医師の土台が不完全なまま現場に立つことも少なくないのだとか。
日本美容外科学会(JSAPS)理事長・武田啓氏は、「美容医療の質担保には、何らかの専門医の取得が必要」としながらも、自由診療の専門医取得を義務化すると真摯に取り組む美容外科医やクリニックの負担になりかねない、としています。
美容医療のクリニックに対しては、治療内容や広告内容など法に触れることのないように監視を強めることは必要といえそうですが、最も大事なのは患者自身が信頼できる医師を選べるよう知識を身につけること。
そのためにも、今後は医療の現場から患者への注意喚起や正しい情報の発信が求められるでしょう。
▼美容医療クリニックへの広告規制については、こちらの記事もご覧ください。
患者が知っておくべき”直美”の医師との向き合い方
 患者の立場からすれば、自分の担当医が臨床経験の少ない医師だと分かれば不安な気持ちも増すでしょう。
患者の立場からすれば、自分の担当医が臨床経験の少ない医師だと分かれば不安な気持ちも増すでしょう。
最後に、医師選びのポイントをお伝えします。
■医師の資格と実績を確認しよう
クリニックを選ぶ際には、担当医のキャリアに注目してみてください。
大学を卒業後、どのようなキャリアを経て現在のクリニックに在籍しているのか、どのくらいの実績があるのか、しっかりとチェックすることが大切。
とくに専門医資格を有しているかは、クリニック選びにおいて重要なポイントです。
専門医資格の重要性や医師としてのキャリアなどの知識は、一般にはあまり知られていないものがほとんどです。
しかし、美容医療を受けるのであれば”直美”の現状についても知っておいて損はありません。
▼初めてのクリニック選びで気をつけたいポイントについてはこちらの記事をご覧ください。
■美容医療のリスクを正しく理解しよう
美容医療のほとんどは自由診療です。
保険診療と比べて治療費が高い分、高い効果を期待してしまう方も多くいるでしょう。
しかし、美容医療の治療で100%安全といい切れるものは存在しません。
安全性の高さをうたっている治療法であっても、多少のリスクはあります。
そのため、患者側もリスクを伴うことを正しく理解し、施術を受けることが重要。
成功事例だけでなく失敗事例も参考にしながら、美容医療にチャレンジしてみることが大切です。
まとめ
近年、医療業界で話題となっている”直美”は、若手医師や女性医師のキャリア選択の幅をひろげ、医療の現場へ新たな風を吹き込むきっかけとなるかもしれません。
しかし、現状ではネガティブに捉える声も多く、美容医療に携わる医師のスキル不足や医療トラブルの増加、他診療科や地域医療の医師不足…など、問題が山積みです。
NEROも多くの美容医療関係者とかかわる中で「必ずしも直美がいけないとはいいきれない」と思う気持ちもある一方、「今の激戦状態を踏まえると、直美はおすすめしない」というドクターが多いのが特徴的に感じます。
少し前であれば数も少なく、働くドクターにとっても、患者側にとってもメリットもあったかもしれませんが、現在一定の飽和状態にもある業界環境などを踏まえても、おすすめできるキャリアではないかもしれないですし、社会問題としても課題があります。
解決するためには、美容医療だけでなく医療業界全体での大きな改革が必要とされていますが、それには長い年月を要するでしょう。
そのため、まずは患者側が美容医療のリスクや医師のキャリアについて正しく理解し、選ぶ目を養うことが大切。
美容医療を受けている方、受ける予定の方は、”直美”という新たな言葉についても知っておいて欲しいと願います。
この記事を読んだあなたにおすすめの関連記事
| ・当サイトは、美容医療の一般的な知識をできるだけ中立的な立場から掲載しています。自己判断を促す情報ではないことを、あらかじめご了承ください。また、治療に関する詳細は必ずクリニック公式ホームページを確認し、各医療機関にご相談ください。 ・本記事は、執筆・掲載日時点の情報を参考にしています。最新の情報は、公式ホームページよりご確認ください。 ・化粧品やマッサージなどが記載されている場合、医師監修範囲には含まれません。 |